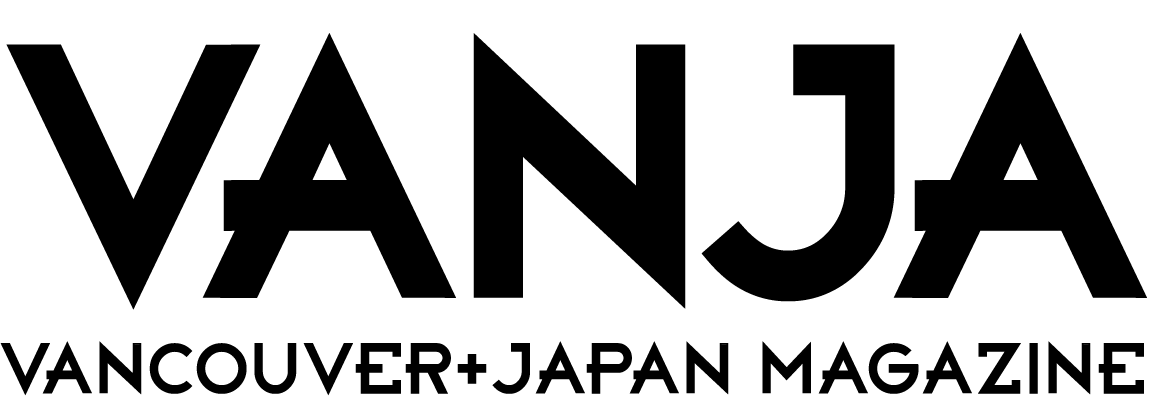今年のトロント日本映画祭の上映作品のうち『あのこは貴族』は、山内マリコの同名小説を映画化した作品で、日本では2021年2月に公開された。
東京で生まれ育ち結婚に悩む箱入り娘と、地方から上京して進学し生活や仕事に苦労する女性を中心に、同じ東京に生きながら住む世界の違う者同士の関わりを通して、今の日本社会が浮き彫りになっている。
そんな本作は、自身も地方出身の女性で、今は金沢市に移住しながら意欲的に映画を作っている岨手由貴子監督が映画化したもの。この作品を映画化するに至った経過や、移住を経てのご自身の変化や作品との関わりなどについて、岨手監督にお話を伺った。
小説『あのこは貴族』からの映画化について
ー山内マリコさんの原作小説を映画化するに至った経緯を教えてください。
前作の映画『グッド・ストライプス』のパンフレットに、山内マリコさんにエッセイを寄稿していただいたご縁がありました。山内さんは日本の地方都市である富山県がご出身で、私はそれに近い田舎の長野県出身です。山内さんが書かれる女性像は自分自身とリンクするところが多く、これまでずっと共感を持って読んでいました。
『あのこは貴族』では、東京生まれのあるソサエティで生きてきた女性像という、今までの山内さんが書かれていなかったタイプのキャラクターを描いていて、すごく興味を持ちました。
自分自身も東京で暮らしていたとき、こういう人たちの存在を感じていたところが、東京の文化論として物語に組み込まれていて、こういう仕組みになっているのかと、新たな発見として読んだんです。
自分が共感できる田舎出身の女性の物語と、東京で育ってきた女性の生き方がハイブリッドされた小説だなと思い、自分の手で映画化できないかなと考えたのがきっかけです。
ー監督が原作を読まれて、映画化のアプローチをしたのでしょうか。
そうです。原作が単行本で出版される前、文芸誌での連載段階から読んでいました。注目されている作家さんの作品は、出版後すぐにドラマ化や映画化の話が決まるので、これは単行本化される前にオファーしなければと思い、単行本の出版記念イベントにプロデューサーと一緒に行きました。サイン会の列に並んで、私に映画化させてくださいと直接お願いしました。
ー前作のパンフレットへの寄稿もあって山内マリコさんも岨手監督をご存知で、話はすんなり進んだのでしょうか。
そうですね。もともと面識がありましたし、私の作風も知っていただいていたので、その場で「任せたよ!」と言っていただき、後日、出版社に正式に連絡しました。
ー最初から監督ご自身が原作を脚本化する予定でオファーしたのでしょうか。前作『グッド・ストライプス』はオリジナル脚本で、原作小説を脚色した長編映画を監督するのは今回が初めてだったと思いますが、脚本化は問題なく進みましたか。
そうですね。今、日本で映画を作る場合、すごく有名な監督でない限りオリジナル脚本である程度の予算を集めるのは難しいんです。それで映画化できそうな原作を探していた中で、連載中だった『あのこは貴族』を見つけました。『グッド・ストライプス』はオリジナル脚本でしたので、次は原作ものをやってみたいという気持ちもありました。
ーオリジナルの脚本と原作のある脚本は、どういった違いがあるのでしょうか。
今回の山内さんに限っては、原作で訴えているテーマを曲げないのであれば、描き方としては自由に改変してくれていいよと言ってくださいました。山内さんご自身が大学で映画の勉強をされていた方なので、映画に対して造詣が深く、だからこそ自由を与えてくださいました。実際に映画で原作にないシーンは沢山ありますし、メインのキャラクター像も少し変えたりしました。
面白い点としては、原作と全然違うシーンや原作にまったくないシーンだけど、あたかも原作にあったかのように観られましたと言ってくださる観客がいたことです。山内さんが原作で書かれた物語ですけど、そこから第三者である私がそのテーマを広げる感覚がありました。世の中に投げ出されたひとつのテーマを、映画化という形で私が広げたり、受け手の観客がその新しい解釈を広げたり、そういう形でいろんな人の手を渡って物語が広がっていく感覚が、原作ものを映画化する面白さなんじゃないかなと思います。
逆に難しかったところは、他の方が書いた物語であるという大前提があるので、大事にされているものは変えないよう気を付けないといけなかった部分です。オリジナルとは違って好き勝手にはできないところですね。
映画と原作小説との違いや、注力して描いた点について

ー今回、全体として原作に忠実に進んでいく中で、原作との細かな違いが原作のテーマを増幅しているように思えました。特にそれを映像で見せているところが素晴らしく、原作になかった自転車での移動は、タクシーとの対比や動きが、女性同士の絆を表すのにもとても効果的に使われているなと思いました。自転車を取り入れるところは、脚本の構想段階からあったのでしょうか。
そうですね。脚本段階から、自転車のシーンは結構大切に書いていたところです。水原希子さんが演じた美紀の友達役として山下リオさんが演じた里英というキャラクターは、原作ではそんなに分厚く書かれていませんが、私には個人的に彼女みたいな友達がすごく多く、共感するキャラクターでした。なので、美紀と里英の関係を描こうとすると、自然に自転車のシーンが浮かんできました。乗り物の対比とか、公開後に評論で褒めていただくことか多かったんですが、映画的な技法として乗り物で対比しようみたいなことでもなく、キャラクターをどう描くかが先行していました。彼女たちだったら東京でどんな乗り物に乗るだろうかと考えたら自転車かなとか、キャラクターに忠実に表現していったら、自然と対比が生まれただけです。
ーあの2人が起業の相談をするところも、原作にはない印象的な場面でした。2人の関係を膨らませていったら、あのようになったのでしょうか。
そうですね。昼からビール飲もうよというあの空気感は、私と女友達の間に流れている空気感でもあります。そういう意味では、原作には描かれていなくても、自分が映画化するうえで自分が描くべき関係性とか、描くべき時間だと思う部分を忠実に再現したというところですね。自分の中で美紀と里英の関係を分厚く描くことは不可欠だったので。
ーこの映画の中で、特に監督が思い入れを持って描いたところはありますか。
原作で山内さんが一番大切にされていたところは、女性同士が争わないことだと思います。タイプの違う女性の話って、これまでもいろんな小説や映画で描かれてきたと思いますが、落としどころとしてよくあるのは、親友になるかライバルとして認め合うかだと思います。
山内さんの原作で発明的だと思ったのは、タイプの違う二人の女性の共通点として、日本の貴族的な階級の世界と日本の田舎の社会がすごく似ていると指摘したことでした。それもあって、二人が友情を結ぶということではなく、彼女たちが生きてきた背景を緻密に描くことに注力しました。彼女たち、華子と美紀は、理解し合って友達になったわけではなく、それぞれ背負っている背景が似ているから、争わずに済んだ。そして一瞬すれ違ったときに少しだけお互いに親切にする、お互いを人として認め合うみたいな、そのバランスにすごく気を使いました。べたべたした友情ものにしたくないし、変に闘う感じにもしたくない。彼女たちの背景を通して、この社会のルールを作っているのはどんな人たちなのかを描くこと。そこは、一番注力したところです。
ー確かに、東京の中心にいる貴族階級を描きながら、それは昔から地方に住んでいるお金持ちの振る舞いとすごく似ている印象を受けました。そういうところは、今までは描かれてこなかったなと思います。
脚本を書くときに取材をして聞いたのは、貴族階級の人も閉鎖的な人間関係の中で暮らしている、ということです。また、田舎でちょっと幅を利かせている層も、所得や住むエリアは違いますが行動倫理は似ていて、自分の顔が利くところで生きているような印象を受けました。
さらに言うと、日本の男性社会、家父長制の社会で生きているところも二人に共通する点ですが、それはもう一人の主人公である高良さん演じる幸一郎も同じです。彼は男性だから、女性が経験しているものとは違いますが、精神的にマッチョでいないといけない、強いオスでいないといけないプレッシャーの中で生きています。この男性社会、家父長制の社会で生きているのは、三人に共通しています。男性である幸一郎を悪者にして成敗してやるみたいな描き方は簡単ですが、幸一郎もある種、家父長制の社会の被害者であるという側面を持たせることも、こだわったポイントです。
キャスティングについて

ー美紀も華子も幸一郎も、映画を観た後では、この人以外に考えられないと思うほどでした。キャスティングはどのように進められたのでしょうか。
最初に決まったのが門脇さんでした。脚本を書いていて、華子を演じるのはすごく難しいだろうなと思っていたんです。お金持ちで可愛くて、ただ結婚できないことだけに悩んでいる主人公に、観客がどれくらい感情移入できるのかというところが悩みどころで。そこから地獄めぐりをしていくことにはなるんですけど、冒頭で乗れなかったら観客はついてこられないんじゃないかなと思っていました。そんな華子のキャラクターを魅力的に演じてもらえるとしたら誰だろうと考えたとき、私には門脇さんしか思い浮かばなかったので、最初からプロデューサーに言い続けていました。
ーしぐさや振る舞いは見事に良家のお嬢様なのに、ちょっとぼんやりした感じで結婚にがつがつしてこなかったのかなと思うところも、すごくよく表現されていると感じました。
門脇さんと役について話していると、職人やアスリートと話をしているみたいだなって思うことがあるんです。いろんなことを考えて演じてくださっているし、身体の使い方を含めてその訓練をしっかりとしてきているような。だから完成したときには、やっぱり門脇さんしかいなかったなと確信しました。
ー門脇さんの過去の役柄からは、はっきりとした自我がありそうな印象を受けていて、今回のお嬢様役を、観る前は少し意外に思っていました。それがとてもはまっていたので、監督が最初から門脇さんを思い描いていたことに驚きました。
門脇さんは個性的な役柄をたくさん演じてこられていますが、それが下品にならないのは、ご本人がもともと持ってらっしゃるものがあるからだと思います。
ー水原希子さんのほうはどうでしたか。
華子役が門脇さんに決まり、美紀のキャスティングを考えていたとき、美紀の設定年齢から考えると水原さんは少しお若いので、最初は候補に入っていませんでした。どうしようかと悩んでいると、キャスティング担当の西宮さんが、ちょっと若いけど水原希子さんはどうですかと挙げてくださって、その瞬間、私もプロデューサーも、あ、それだ、と思いました。
水原さんって、パブリックイメージとしてはセレブリティみたいな華やかな印象が大きいと思います。だからこんな庶民的な役は意外だといろんな人に言われますけど、私は水原さんに美紀みたいなイメージを持っていました。自分の意見をしっかりと持って、この世の中をサバイブしている女性というイメージです。
ー出来上がった感じは、監督が思い描いていた通りだったのでしょうか。
そうですね。水原さんと最初にお会いしたとき、美紀みたいな感覚はわかりますかと聞いたら、すごくわかると言ってくれたんです。水原さんも16歳くらいでモデルをするために上京して、いろんなアルバイトをしながらチャンスをつかむために頑張ったと話してくれて。本当にものすごく気さくで、親近感を持てる人なんです。富山の田舎で撮影しているときも、エキストラの女の子が飽きてしまったら一緒に遊んでくれたり。そんな水原さんが演じてくれたことで、美紀のキャラクター像に説得力が生まれて、より繊細になったと思っています。原作の美紀はもっとさばさばしてタフな感じでしたが、水原さんが持っている繊細さを役に投影させたいなと思って、脚本を書きながら美紀のキャラクターを改変していった感じがあります。
監督自身の移住と映画制作の関係について

ーこの作品を観て、勇気づけられた女性は多いのではと思います。監督ご自身は、女性だからこその生きづらさを感じたことはありますか。また、何か伝えたいメッセージがあってこの作品に挑まれたのでしょうか。
原作で描かれているシスターフッド、女性同士が連帯するテーマにはすごく共感しますし、女性のキャラクターを男性本位ではなくリアルに描くことも重要だと思って取り組みました。あと、私自身が4年前に東京から金沢に移住したんですが、人の居場所というものについても、時間をかけて考えました。特に映像業界はそうですが、日本はやっぱり東京がすべての拠点で、そこからある種外れる形で地方に移住したら、新たに見えてきた生き方や価値観がありました。人間、生きていれば東京で暮らす時期もあったり、地方で暮らす時期もある。美紀のように腐れ縁の男と別れられない時期もあったり、ちょっと疎遠だった友達と再会してまた友達になったり。いろんな場所で生きていいし、いろんなフェーズがあっていい。人生は意外と長くて、いいときも悪いときもあるな、なんて思っていた時期でした。
ーお話を聞いていると、この作品と監督ご自身の移住は、すごく関係しているように思います。映画制作と移住は、どんな順序だったのでしょうか。
ちょうど原作権が取れて正式に映画化が決まった頃に移住したので、脚本は新天地の金沢で書いていました。撮影中は家族と離れて単身赴任で東京に来ていたので、自分自身が美紀のように東京に居候している感覚というか。田舎の人でもないし東京の人でもない。じゃあ自分はどこの人なんだろうと考えたとき、人の居場所って物理的に存在する場所ではなく、自分らしくいられる場所のことなんじゃないかなって。だから、ラストで彼女たちが出す答えには、私自身が一番シンパシーを抱いていたかもしれません。
ーそれは、監督が大学進学で東京に出てきたときの感覚ともまた違うものだったのでしょうか。
そうですね。大学進学で東京に来たときは、若さもあって、ここで新しい人生が始まるんだ、というような期待が入り混じっていました。若いときは、仕事や交友関係や遊ぶ場所を考えたら都会はすごく楽しいし、それ以外の選択肢はないくらいに当時は思っていました。今は、今日まさに東京にいるんですけど、なんか出稼ぎに来ている感じですね。ホームは金沢で、今は単身赴任で来ている感じです。
ーもともと映画監督を目指して東京で勉強するために上京されたのでしょうか。どのあたりで映画監督を目指そうと思われたのか、教えていただけますか。
私が大学に入ったときは、ちょうど一般家庭にインターネットが普及し始めた頃だったんですよ。裏を返せば、田舎にいたら何の情報も入ってこないし、何も買えないみたいな感じで。今はネットでいろんな情報にアクセスできますけど、当時は東京に行かないと何も始まらないみたいな感覚があって。大学で何を勉強したいとかじゃなく、とにかく東京に行きたいみたいな感じで大学に入学しました。入学してから、映画がもともと好きだったのもあって、自分で撮ってみたいなと思ったんです。それで大学2年生のときに、大学に行きながら夜間の映画のワークショップに通って、自主映画を作り始めました。
影響を受けた映画や小説について
ー影響を受けてきた映画や小説はありますか。
映画監督として影響を受けた監督はたくさんいますが、好きな監督を挙げるとしたら台湾のエドワード・ヤン監督でしょうか。狭い人間関係を描いているようで、その奥に見える台湾の時代性や、都市の空気みたいな大きなものも描いている。そこにすごく大きな影響を受けました。
あとは、ミラン・クンデラがすごく好きで、小説の『存在の耐えられない軽さ』も10代のときに読んで影響を受けました。人間は環境の創造物であるという考え方というか。恋愛感情だと思っているものが、それぞれ生きてきた文脈によってそう思っているだけ、みたいなところが。私が恋愛感情をキラキラしたものとして捉えていないのは、ミラン・クンデラの影響なんじゃないかと思っています。だから私、恋愛映画みたいなものを撮れる気がしないんですよ。
ーでも『グッド・ストライプス』なんて、すごくリアルな恋愛映画だと思いましたよ。キラキラしていないかもしれませんが。
そうですね。人と人との関係は、キラキラしたものではないけど良いものではあると思っていて、恋愛だとカテゴライズされるものを分解していくと、情だったり、愛着だったり、執着だったり、いろんな感情になると思うんです。たぶんそこを考えていくほうが自分には合っていて、キラキラした要素がなかなか見つかりません。
世界の映画祭での反応や、今後の映画祭への出品について

ー『あのこは貴族』は日本公開からしばらく経ち、その間に世界各地の映画祭に出品されて、様々な反応があったのではと思います。世界からの声で気づかされたことはありましたか。
昨年末にフランスで行われたキノタヨ映画祭に招待していただき、私も現地に行きました。貴族というものが階級として明示されているヨーロッパの文化圏で、この作品がどう観られるかはすごく疑問で、知りたいところでもありました。日本は一応、表向きは貴族なんて人たちはいません、平等です、となっていると思うんです。でも違うんだよという話を、ヨーロッパの方が観たらどう思うのかなと。あとは経済的な部分で、日本のお金持ちは世界のお金持ちとはレベルが違うだろうな、みたいな部分もありますし。ですが、そういう違いは受け止めたうえで、本質的に描こうとしている家父長制の社会で女性がどんなふうに生きているのかといった、本質的なテーマのほうを見てくださっている観客が多くてほっとしました。
あと、ロッテルダムで上映されたときに観てくださった方の感想を読んで、はっとさせられました。「この物語は、ある意味はっきりとせずグラデーションのように進んでいくけれど、それは日本社会が、はっきりとは言わないけれど確実に存在する格差をはらんでいるからだ」などと書いてくださっていて。自分で意図的にそうしようと思って描いたわけじゃないんですけど。実際、日本って「貴族VS地方出身女子」みたいな社会でもないと思うんです。一見、同じように扱われていて、同じ場所にもいるし同じお店も利用するけれど、お互いが見えていないというか、いないことになっているのが、日本の社会っぽいというか。この映画評を読んでなるほどと思って、そんな発見ができたのも、海外の方に観ていただいたからだなあと感慨深く思いました。
ー今後ますます日本の素晴らしい映画が世界に出て行ってほしいと思っているところです。世界の映画祭で上映していくことについては、どのようにお考えですか。
映画祭に行くと、ティーチインで積極的に手を挙げて質問してくださったり、日本ではなかなか聞けない感想を聞けたり、すごく刺激になるので、映画祭を含めて海外で観てもらえる作品を撮っていきたいなと思います。
あとは、今日本でお話しする機会がある監督で、深田晃司監督や是枝裕和監督など、海外で映画を撮っていらっしゃる方も周りにいるので、すごく刺激になります。日本のマーケットでどういうものが受けるかだけを考えていたら、結果的に日本の観客にも届かないものになるように思いますし、何か作るときに大きな視野を持って作るのはすごく重要だなと思っています。
コロナ禍の影響や子育てをしながらの映画制作について

ーこの2年はコロナ禍で厳しい状況で、この作品も影響を受けたのではないかと思います。そのあたりの大変さはありましたか。
撮影に関しては、コロナが始まる前に撮り切っていたので影響はなかったんですが、公開が少し延びました。撮影では大勢のエキストラの方に来ていただいたので、コロナ禍では絶対に撮影できなかったなと思います。
ー公開が遅れて、困ったことにはならなかったのでしょうか。
そうですね。公開時期に良い映画がたくさん公開されていたので、初週にお客さんがあまり入らなかった、みたいなことはありました。
ーコロナ以外にも、私生活で子育てをしながら映画を作る大変さもあったのではと思います。どのようにうまく乗り切っておられるのでしょうか。
全然うまく乗り切ってないんですけど、『あのこは貴族』を撮ったときは子供が1人いて、撮った後にもう1人産んで、今は2人の子供を育てています。地方在住ということもあり、撮影の期間は数ヶ月単身赴任で一切子供と会わず上京している感じです。
シンポジウムや取材でそういう話をする機会も多いんですが、別に胸を張れることじゃないんですよね。女性の監督で子供を産んで、監督業を続けているってすごいですね、みたいに言われますが、無理しているだけですし、子供のいる男性スタッフがパートナーに任せて何か月も地方ロケに行くのと何ら変わらないですから。若い女性のスタッフや監督にその生き方を勧められるかと言ったら、そんなはずはありません。日本の映画の制作現場が、朝は普通に集まって夜は子供が起きている時間に帰れるサイクルで撮影できるようになれば、性別を問わず子供を望む人がそれを選択できるようになると思います。
でもそれは、プロデューサーや監督ひとりの権限でどうにかなるものではなく、業界全体で変えていかないといけないと思います。だから、自分が今無理をしないと監督業ができない事実をお話しすることで、業界全体が変わっていく機運を高められたらいいなと思っています。
ー今、監督の周りのスタッフさんの男女比率はどんなものでしょうか。
ちょうど今はドラマの撮影中なんですが、プロデューサー陣と現場のジェンダー平等を目指したいと話をして、男女比としては半々くらいで撮影しています。でも、男女半々というのは、人数で言うと実はそんなに難しいことじゃないんです。というのは、チーフが男性でアシスタントは女性みたいなことはよくあるんです。でも今の現場では、撮影助手のチーフやラインプロデューサーが女性だったり、決定権のあるところに女性が多い印象ですね。お子さんがいらっしゃって現場に出ている女性もいて、連日の撮影はとても大変ですが、すごく良いチームだと思います。
ートロントで暮らす日本人には、この映画のように勝手知らない土地で頑張って暮らしている人も多いと思います。そんなトロントの読者にメッセージがありましたらお願いします。
この映画が昨年日本で公開されたとき、まさに今の日本だと言われる作品でした。というのは、オリンピックが開催されるときに当時の責任者であった森喜朗さんが女性蔑視的な発言をして、そんな日本社会と映画の内容がリンクするタイミングで公開されたんです。日本に住んでいる人がこの映画を観て、良くも悪くもいろんな反応があったことが、私はすごく良いことだなと思ったので、トロントに住んでいる方から今の日本の社会がどう見えるのかを、すごくお聞きしてみたいなと思います。
岨手由貴子監督プロフィール
1983年、長野県生まれ。大学在学中に映画制作を始め、短編『コスプレイヤー』(04)が第8回水戸短編映画祭、ぴあフィルムフェスティバル2005に入選。初の長編作品『マイム マイム』(08)がぴあフィルムフェスティバル2008で準グランプリ、エンタテインメント賞を受賞。『グッド・ストライプス』(15)で長編商業映画デビュー。『あのこは貴族』(21)は最新作。現在は石川県金沢市在住。

『あのこは貴族』(英題: 『Aristocrats』)
東京都内で由緒ある家に生まれ育った箱入り娘・華子(門脇麦)は、結婚適齢期ながら相手がなかなか見つからず、やきもきする日々。大学進学を機に地方から上京した美紀(水原希子)は、在学中から実家の経済状況が悪化し、生活も仕事もままならない。同じ街に暮らしながら住む世界の違う2人の女性が、ある出来事から出会うことになる。
監督・脚本: 岨手由貴子
出演: 門脇麦 水原希子 高良健吾
原作: 山内マリコ『あのこは貴族』(集英社文庫刊)
©山内マリコ/集英社・『あのこは貴族』製作委員会
インタビュー・本文:みえ