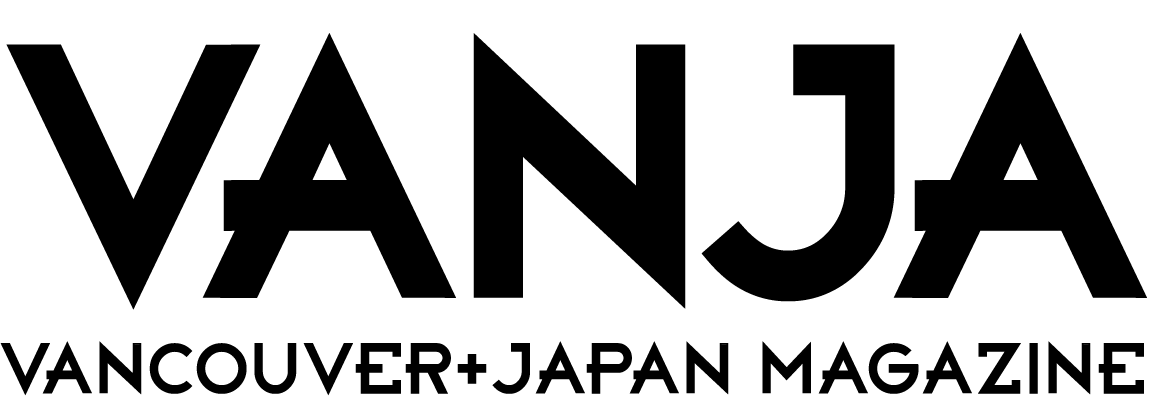過去は変えられないそれでも前を向く
虐待経験者の声を取り上げたドキュメンタリー映画『REALVOICE』が、9月末にトロントで上映された。日本から来加したのは、監督の山本昌子さん(まこ)、出演者の1人のブローハン聡さん(BRO)、撮影と編集に携わった西坂來人さん(ライト)の3人。それぞれがネグレクトや虐待によって児童養護施設で過ごした経験を持ち、メディアや講演会で経験者の声を挙げ続けている。虐待という大きな社会問題をテーマにした90分の映画に、どんなメッセージを込めたのか。前編と後編にわけてお話ししていただく。
みんなと作ったみんなの映画

―なぜ「虐待」をテーマにしたドキュメンタリーを撮ることになったのですか?
まこ: まず私の生い立ちを少しお話しすると、ネグレクトが原因で生後4ヶ月から19歳まで児童養護施設などで育ちました。その経験から、これまで自分でメディアに出て話をしたり、虐待経験者へのメンタルケアと制度を変える必要性を訴える署名活動をしたりしてきました。少しずつ制度が変わってきている現状はありますが、もっと虐待経験者のありのままの姿、ありのままの言葉を届けたいと思ったんです。映画なら多くの人に伝わると思いましたし、大きな力が生まれると感じていました。
ライト: 実は最初、映画監督や映像制作の仕事をしている僕に映画を撮ってほしいと彼女からお願いがあったんです。でも僕よりも彼女が関係を築いてきた人に彼女がカメラを持って話を聞くことでしか撮れない画があると思ったので、ぜひ監督をしてほしいと逆にこちらからお願いしました。
まこ: ライトさんにはサポートしてもらってありがたかったです。私が監督ではありますが、みんなと作ったみんなの映画だと思っています。より多くの人に見ていただきたくて、無料公開に踏み切りました。これまで日本各地で約40回上映会をして、今回トロントでも上映できて嬉しいです。学校や児童相談所などでも映画を自由に使っていただいていて、そこで講演することもあります。まさに子どもに関わる仕事をしている人に届けたい声がたくさん詰まった映画なので、それを研修などで見ていただけるのは嬉しいことですね。
出演者70人の共通点は虐待経験

―映画に出演したのはどういう人ですか?
まこ: 虐待を受けたことのある10代~30代の70人です。映画の中では、そのうち60人が自分の声でメッセージを伝えています。児童養護施設などの施設出身の人もいれば里親に育てられた人もいますし、普通の家庭で虐待を受けながら保護されなかった人、いまだに虐待を受けている人もいます。
―虐待を受けても保護されなかったという事実には胸が痛みます。
まこ: SOSを出していいのかわからなかったり勇気を出せなかったり、自分が悪いんだと責めてしまったりする人もいるんです。でもこの映画で仲間たちが声を挙げる姿を見て、自分も救われるべきだ、抜け出すためにできることをしたいと考えるようになって、親から離れて保護されることになった人もいました。SOS発信に繋がったのはとても大きなことだと感じています。
―そもそもその70人が出演することになった理由は?
まこ: パンデミック以前から施設出身者とはいろんな活動を通して繋がっていましたが、パンデミックの影響で孤独感をより感じる子たちが多くなっていました。それを少しでもなくすために週1回オンラインで繋がる場を作って、結果的に全国約450人と繋がることになりました。今回映画を撮る話をしたら、「出演したい」と言ってくれた人がたくさんいて。SNSを通してこちらから出演を依頼した人もいます。
私は47都道府県出身者が出ることに意味があると思っていて、結果として45都道府県出身の人に映画に出てもらっています。例えば都市部の子だけを取り上げると、都会の話だから、とまとめられてしまいがちです。でも自分の地域の人が声を挙げることで「自分の県に虐待を受けた人がいるの?」と身近に感じてくれるかもしれないという期待がありました。
それぞれの言葉が力になる

―映画を見た当事者の方々の反応はいかがでしたか?
まこ: 最初はフラッシュバックの心配をしていたんですが、実際は「自分と同じ経験をした人たちがこの世界に生きていることを知って勇気が沸いた」、「自分は1人じゃないって思えた」と言ってくれる子ばかりでした。映画撮影をしながらみんなの声を挙げる勇気や辛さ、言葉の重さを感じて「絶対に意味のある映画にしたい」という思いがあったので、みんなの反応はとても嬉しかったですね。
―ブローハンさんは実際に出演されていますね。
BRO: 「虐待に対して思うこと」について自分の考えを1つに絞って伝えました。僕の言葉が誰かにとって希望になってほしいと思いつつ、逆にそれで傷ついてしまう人もいるかもしれないとも思って、どちらの子も置いてきぼりにしないようかなり気を遣いながら言葉を発しました。実際の映画を見てみて、みんな伝えたいことがバラバラで興味深かったです。虐待のメッセージ=ネガティブだけでもないしポジティブだけでもありません。たった5秒くらいの出演だとしてもそれぞれのメッセージ性は強いと感じましたし、他の人のメッセージにすごく元気をもらいました。
「あなたは一人じゃないんだよ」「お母さん、大嫌いです」
「頑張って生きてきたよ」
「助けてなんて言えない。でも、本当は助けてほしい」
―映画の中で一人一人が発する言葉は本当にとても印象的でした。
まこ: 撮影する前、まずは私がかなりヒアリングをしています。この映画自体がみんなの生い立ちの整理のきっかけになればいいなと思っていたんです。まずどういうふうに施設で育ったのか、どんな生い立ちか、今一番伝えたいことは何かを聞いていくつか言葉を絞り出してもらいました。たくさん話しながら泣き続けていた子もいましたね。無理しなくていいんだよと伝えても「これを絶対に伝えたい、ここで伝えたい」と言ってくれて、それぞれいろんな思いを抱えながら映画に出てくれています。
大人になっても終わりじゃない

―映画のメッセージに「虐待は大人になって終わりじゃない」というものがありますよね。終わりがないというのはどういうことでしょうか?
ライト: 1つはトラウマですね。それがきっかけでずっと生きづらさを抱えている場合もありますし、大丈夫だと思っていても何かのきっかけで急に心の不調をきたすこともあります。もう1つは適切なケアが必要だということです。制度によって手厚いケアができるようになれば、心の傷は少しずつ軽減されると思います。
BRO: 僕は当事者として、虐待が自分の人生にすごく影響を与えていることを身を持って体感しています。幼少期、義父から何度も水風呂に沈められた経験があるんですね。例えば海に入ろうとすると、その場面を思い出さないにしても自然と体が反応するんです。銭湯でサウナに入ってから水風呂に入ろうとしても、足先を入れた瞬間に心臓がぎゅっとなって息ができなくなったこともあります。最近は少しずつ克服できていますが、日常のどこに「傷つき体験」の影響を受けた部分があるのかわからないというのは怖いなと思っています。
まこ: 苦しい経験があっても、みんな自分の過去と向き合う方法を覚えていくんだと思います。表面的には何の問題もなく生きているように見える人はたくさんいますが、悲しみや辛さは残っています。過去を乗り越えたのではなくて、誰しも強い自分を見せるという選択をしているだけだと思います。過去は変えられないし変わらない。でも、過去と向き合って生きていこうというみんなの思いが映画には込められています。ケアという意味では、虐待やトラウマの治療には周りの理解や寄り添う姿勢が一番良いという話もあります。虐待を受けた子が実はたくさんいるんだと、まずは世の中が理解することで社会は変わると信じています。
 山本 昌子(ヤマモト マサコ)
山本 昌子(ヤマモト マサコ)1993年生まれ、東京都出身。ネグレクトにより生後4か月から19歳まで社会的養護施設で生活した経験を持つ。児童養護施設出身者へ振袖を着る機会を提供するボランティア団体「ACHAプロジェクト」代表。その他、全国の社会的養護出身者や虐待を経験した若者たちとオンラインで繋がったり、自宅を解放した居場所事業「まこHOUSE」をオープンしたり精力的に活動する。
 ブローハン 聡(ブローハン サトシ)
ブローハン 聡(ブローハン サトシ)1992年生まれ、東京都出身。義父からの虐待が原因で11歳から19歳までを児童養護施設で過ごす。現在は(一社)コンパスナビ 事務局長として、児童養護施設等を離れた若者をサポート。無戸籍、無国籍、虐待などの経験から、講演活動やYouTubeでの情報発信にも力を入れる。
 西坂 來人(ニシザカ ライト)
西坂 來人(ニシザカ ライト)1985年生まれ、福島県出身。父による家庭内暴力から逃れるため、小学5年生から一時期を児童養護施設で過ごす。東京を拠点に映画監督、絵本作家として活躍。
児童養護施設を退所した若者をテーマにした映画『レイルロードスイッチ』公開中。