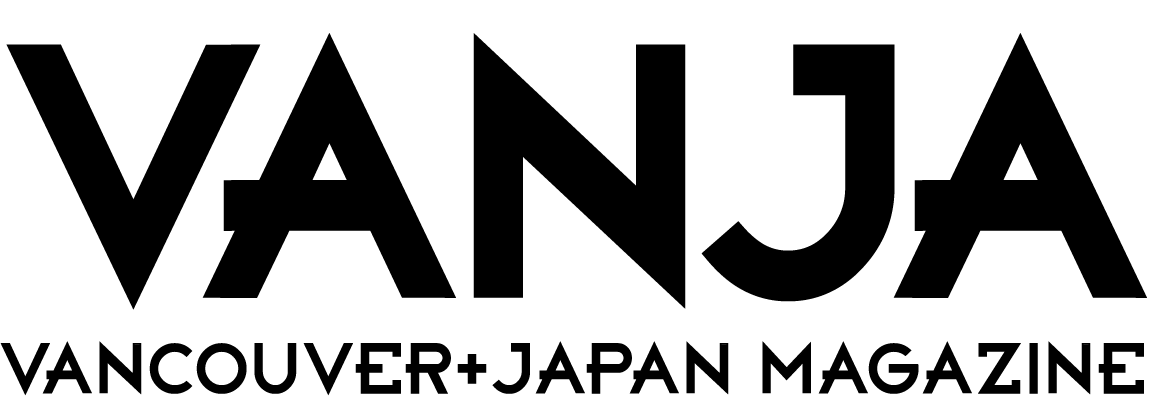深田晃司監督最新作『LOVE LIFE』が、2022年9月5日にベネチア国際映画祭でワールドプレミア上映された後、トロント国際映画祭でも上映された。矢野顕子さんが1991年に発表した同名楽曲に深田監督が着想を得てから約20年を経て映画化に至った本作は、日本でも9月9日に劇場公開され、国内外で話題を呼んでいる。本作の完成に至るまでの経緯と、映画館、映画祭、映画制作などへの思いについて、深田監督にお話を伺った。
『LOVE LIFE』制作の経緯
――20歳の頃に矢野顕子さんの曲「LOVE LIFE」を聴き、この物語を着想したとのことですが、長年かけて完成することになった経緯を教えてください。
矢野顕子さんの「LOVE LIFE」を聴いたとき、衝撃的に好きになりました。最初は男女のラブソングだと思って聴いていたのが、何度も聴いていくうち、それだけではなくいろんな見方ができるなと思う中で、妄想のように物語が膨らんでいきました。22歳か23歳のときにはA4用紙 1枚くらいの短いシノプシスを書いていましたが、だからすぐに作れるというわけでもなかったので、ずっとそれを抱えながらいろんな映画を作っていました。
そんな中、2015年頃に知り合いのプロデューサーから一緒に映画を作らないかと声をかけられたとき、実はまだ撮っていない企画があるんですと渡したのがそのシノプシスで、そこから企画が動き始めました。もともとこの映画の最大のモチベーションは、「LOVE LIFE」という矢野顕子さんの素晴らしい歌を、いかに映画館に響かせるかということでした。自分が今でも変わらずこの歌を好きなので、それがこの映画に向かっていくモチベーションでしたね。
――当時から物語が出来上がっていたわけではないのですか。
大筋の話は出来上がっていましたが、20代前半の頃はまだ途中までしかできていませんでした。夫婦のところに元夫が帰ってきて三角関係になるという前半部分しかできておらず、後半がまったくできていなかったんです。ただラストシーンだけは決まっていて、今映画になっているラストシーンは、かなりイメージ通りになっています。
――当時思い描いていた内容と比べて、完成した作品は思い通りのものになったのでしょうか。
そうですね。すごく別な作品になった印象はなく、自分としては手ごたえがあるイメージに近いものになりました。ただ、脚本を直していったりキャスティングが決まっていったりする中で、最初のイメージから変わっていった部分もあります。
――当時だと実現しなかっただろうなとか、今だからこそできたなという点はありますか。
砂田アトムさん演じる元夫のろう者役は、20年前の当初の企画にはなかった設定です。脚本を直していく中で、東京で隔年で行われている東京国際ろう映画祭のワークショップの講師の依頼を2018年に受けたんです。実際にろう者である牧原依里さんがディレクターの映画祭です。映像制作ワークショップで、行ってみたら生徒さんは、ほぼ全員きこえない方でした。恥ずかしながら、そこで初めてろう者と本当にきちんと接する機会を得たんです。
そこでいろんな発見があり、手話はいわゆる補助器具のようなものではなく、日本語や英語、フランス語のように独立した豊かな言語であることを、まず知ることができました。言語はそれぞれに特質がありますが、手話は特に空間を使うので、非常に映像向きな言語であると思いました。
そんな中で、この物語の主人公と夫と元夫との三角関係に緊張感を持たせるために、何かもうひとつ言語を足したらどうかと考えたとき、だったら手話にしようと思いました。あと、映画祭でろう者と接したことで、逆にこれまで自分が何本も長編映画を作ってきながら、その作品にひとりとしてろう者が出てこなかったことのほうが、実は不自然なことではないかと考えるようになり、この作品には自然とろう者の俳優をキャスティングしようという気持ちになりました。それは、20代の頃にはまったく考えていなかったことですね。
――日本の映画で、ろう者が出てくることは珍しいと思いました。脚本にろう者の設定が増えた段階で、ろう者のキャスティングを考えていたのでしょうか。ろう者の俳優さんありきだったのか、それとも聴者の俳優さんに手話を覚えてもらうことも考えていたのでしょうか。
オーディションは手探りの中でろう者と聴者の両方に開かれた形で行ったので、非常に熱心に手話を勉強して臨んでくださった聴者の俳優もいました。結果的に、ろう者の俳優のリアリティが私が求めるものと近かったので、ろう者の俳優にお願いすることに決めました。

――今回、ろう者の設定はもちろんのこと、さらに韓国手話で韓国籍という設定が珍しいなと思いました。元夫が韓国籍というのは、もともとあった設定でしょうか。
これは、手話とはまったく別のルートで決まった設定で、たまたま重なりました。この映画は、もともと矢野顕子さんの曲「LOVE LIFE」に触発された映画で、その歌詞に、「離れていても愛することができる」という非常に印象的なフレーズがあります。この距離が大きな問題で、映像にすると距離感はどんどん失われていくため、フィクションの世界、特に映像の中でどうやって距離を描くかが難しいと思っています。
それでいくつかの工夫をしていて、団地のA棟とB棟と棟の前の広場での行き来によって物語が進むようにしたり、そこに元夫が帰ってきて距離がだんだんと近づく形にしたり、夫の二郎が少し地方に行って逢引したりと、なるべく明確にわかりやすい形で作中に距離を導入しています。3階と1階で会話して、縦の距離、上下の距離を出したりもしています。そうなると、最後に妙子と元夫が遠くに行かなくちゃいけないとなったとき、これがまた難しいんです。夫の二郎と山崎さんが会う場面を地方で一度描いてしまっているので、それが仮に長野県だとして、妙子と元夫は、そこからさらに遠くに行って岐阜県にしたところで、どっちがどう遠いのか、映像だとほとんど伝わらないですよね。だから横の移動の距離を描くのはすごく難しくて、それまでの物語の生活感からさらに遠くに行くためには、海を越えて違う文化圏に行かなければ今回は伝わらないと思っていました。それで一番近くの外国である韓国という設定になりました。
――濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』でも韓国手話が出てきました。あれがちょうど昨年のトロント国際映画祭(TIFF)で上映されたんです。今年のTIFFでは、『LOVE LIFE』の他に是枝裕和監督の韓国映画『ベイビー・ブローカー』も上映されました。この状況をトロントの観客が見たとき、日本を代表する監督がこぞって韓国の現場や韓国手話を取り上げている点に、何か事情があるのかと思いそうな気がしました。
韓国手話に関しては、こちらの脚本が出来上がって撮影準備が進んだ段階で『ドライブ・マイ・カー』制作の話を聞き、「あ、かぶった」と思いました(笑)。かぶったとは思いましたが、ろう者や手話の設定は決して「一過性のネタ」ではないですし、物語も違うので、そこは全然気にしませんでした。
韓国という設定に関しては、かぶるといえばそうですが、まあ隣同士の国なのでそういうものだろうと思います。カナダ映画にもアメリカの設定は出てくるだろうし、フランスとスイスなど国境が接していればお互い物語に出てきやすいですよね。たぶんそれと同じで、それ以上でもそれ以下でもないと思います。日本に最も近い外国は韓国なので入れやすいし、むしろ多少出てくるのが自然じゃないかなと思います。カナダ映画でもアメリカ映画でも、カナダ人、アメリカ人しか出てこない映画のほうが珍しいんじゃないでしょうか。なので、日本映画に韓国人が出てきても、そんなに驚かなくていいんじゃないかなと思います。

深田監督が描く物語について
――深田監督の作品では、過去の作品から共通して、突然の理不尽な出来事に見舞われる人の生き様を描き続けているように思います。このような物語を作る理由を教えてください。
それほど大きな理由があるは思っていないんですけど、映画を作るときに自分にとって最も信じられることを描きたいと思っていて、家族は自分にとってメインモチーフにならないんです。普遍的なものとは全然思っていないので。
人はいつか死んでしまうとか、人は一人ひとり孤独であるとか。あるいは、私たちの人生は予測不可能性に満ちていて、次の瞬間に何が起きるかわかりません。自分が今この取材を終えた後、車に轢かれて死んでしまうかもしれないし、今突然地震が来て、この建物が倒れてしまうかもしれない。そういう予測不可能性に満ちていることが、自分にとって揺るぎなく疑いようのないものである感覚なので、それが繰り返しモチーフになり、世界観になっています。
――ただ、人生そんなに劇的なことばかり起こるわけではないと思いますが、監督の作品ではものすごく悲劇的なことが起こりがちだと思います。
それは、何が起こるかなと思ったときに良いことよりも悪いことが起きるような気がしてしまう自分の性格を反映しているのかもしれません。ただ、自分の映画で悲劇的なことは起きますが、人の死も含め、どれも当たり前のように人生に起こりえることだと思っています。人生劇的なことばかりは起きないというのはその通りだと思います。物語のクライマックスのような感情を高揚させるドラマチックなことが起きても、大体においてはそこで人生が終わるとは限りません。ドラマチックなことは人生の2%か3%で、あとは淡々と日常が続いていくので、その日常のほうをきちんと描いていきたいと思っています。
往々にして、死とか理不尽なことは、災害や事故もそうですが、何の伏線も理由も目的もなく突然起きがちです。逆に言えば、救いや喜びも理不尽に訪れたっていいんじゃないかと思います。そういった瞬間を、今後はもっと描いていきたいですね。
――今回、ろう者と聴者が出てくることで、通じているようで通じていない瞬間がたくさんありました。現夫が元夫に、聞こえていないのに独り言のようにずっと話しかけるシーンとか、目を合わさないこととか。そういう描写が今回特に多いように思いましたが、何か意図を持ってたくさん描いていたのでしょうか。
特別に意識はしていないんですが、ろう者の設定が増えたことで、聴者とろう者のご夫婦に取材させてもらったり、砂田アトムさんに話を聞かせてもらったりしながら脚本を作っていきました。その中で印象的だったのが、ろう者の方は手話を使う特質上、本当に相手の目を見て話すことです。相手の顔を見て目を見て、向き合って話すという。聴者の感覚では、親しくなればなるほど、そういったコミュニケーションが雑になっていくというか、相手の顔をあまり見なくなりますよね。特に日本人がそうなのかもしれませんけど。だから、その対比みたいなものが脚本上で増えていきました。ただ、もともと聴者同士でもろう者同士でもディスコミュニケーションはあるものだと思っているので、基本的には伝わらないことを前提に、お互いに言葉を届けないといけないし、相手が何を考えているかと想像しなくちゃいけないという点では変わらないと思います。でも、手話と聴者の日本語という2つの言語が入ることで、よりそういった部分にフォーカスされることになったとは思います。
――最後の台詞は、それこそすべてが集約された一言だと思いました。あれは、20年前に思い描いたラストから変わっていないのでしょうか。
いや、変わりました。あれこそ、ろう者という役が増えて取材をしていた中で、本当に最後の最後、クランクイン間近の撮影稿を作る際に増えた台詞でした。
――深田監督の作品では、結論を観客に委ねる印象が強いのですが、怖くはないでしょうか。
どう受け取ってもらっても良いと思っているので、あまり怖くはないですね。
――逆にそれは、こう受け取ってほしいといった作り方をしたくないということでしょうか。
そうですね。なるべく避けたいです。矛盾するようですが、映画作りには自分自身の考え方や世界観が反映されるものだしそうあるべきだと思う一方で、それは啓蒙的にお客さんに押しつけるものではないと思っています。自分自身に世界がこう見えているというのも、ある意味表現のフィードバックだとすると、それをただそっとスクリーンに提示する。それを見たお客さんが何を思うかは、できるだけ自由にしたいし、そこを制限するようにはしたくなくて。
映画の歴史はプロパガンダの歴史だと思っていて、極端な例で言うと、戦争中にはファシズムや軍国主義など様々なプロパガンダに映画が利用されてきたわけですよね。それだけ映画や映像は集団に大きな影響を及ぼしてしまう力があるもので、そういった時代を経て表現を作っている以上、その危うさには全力で距離を取る必要があると思っています。戦争中でなくても本質的な部分は変わりません。例えば男女を撮ればそこにはジェンダーの問題が、家族を撮れば家族制度が映り込む。本人がそれをプロパガンダと意図しても意図していなくても、プロパガンダとして機能してしまいます。例えば、伝統的な家父長制の家族の姿、お母さんがご飯を準備してお父さんがそれを食べるみたいなジェンダーステレオタイプが肯定的にテレビCMに映るだけで、そのイメージは拡散され、社会にある種の抑圧として働くわけですよね。だからこそ、作り手はそういったことに意識的にならなくてはいけない。
じゃあどうすればプロパガンダからできるだけ距離を置くことができるのかと考えたとき、自分に思いつく方法は、できるだけ観た人の中で解釈や印象が分かれるものにすること、それだけです。むしろ観ている人の考え方や思想、世界の見方をあぶり出すようなものになればいいなと思っています。そのためにはできるだけ余白や余韻を工夫して残していく。そういったことを考えています。
国内外での上映について

――TIFFでの上映は、『淵に立つ』『よこがお』に続き三度目となります。近年は新作を発表するたびにトロントで上映されているように思いますが、この状況に対し、どのような心境でしょうか。
もう、呼んでいただいてとてもありがたいです。映画祭に選んでもらえるからこそ観てもらえるお客さんもたくさんいると思うので。私としては作るときにどこか特定の国を観客として想定することはなくて、どこの国の人にも観てほしいと思っているので、とても嬉しいですね。
――積極的に世界の映画祭に出していきたいという思いはあるのでしょうか。
そうですね。映画祭のために作っているわけではないですが、映画祭も結局より多くのお客さんに届けるためのひとつの過程だと思います。映画祭はいわば映画のマーケットですし、魚も市場に並ばないことには買ってもらえないので。特に欧米においてアジア映画はどうしたってマイノリティなので、映画祭の存在はとても重要だと思います。
――これまでにカンヌやベネチアなど様々な世界の映画祭に参加されて、映画祭ごとに違いを感じるところがあれば教えていただけますか。その中で、TIFFはどのような印象でしょうか。
映画祭によって雰囲気は違いますが、カンヌは業界向けの映画祭、業界向けのマーケットの色合いが強いという感じです。トロントは市民の距離が近い感じがあります。観ている人たちとの距離の近い映画祭だなと感じるので、質疑応答が楽しみですね。
コロナ禍を経ての映画祭や映画館に対する思いと、日本の映画制作事情
――前回は2019年の『よこがお』でトロントに来訪され、その後コロナ禍を経て今回『LOVE LIFE』が出品されました。この間で、コロナ以前と何がどのように変わりましたか。
2020年には多くの映画祭が中止になって、『本気のしるし』もカンヌに選ばれたけど完全に中止になり、映画祭に携わる皆さんは本当に大変だったんじゃないかと思います。日本でも映画館が、ミニシアターがたくさん2020年に休業になりました。それまで本当にお正月でも映写機を止めなかったミニシアターが映写機を止めて。そのときに初めて、空気のようにあるのが当たり前だと思っていた映画館が日常から消えました。当たり前のように享受していたものが急になくなった瞬間、映画館で毎日観られる状況が、どれだけ大切な、かけがえのないことだったのか、と感じた人も多かったのではないかと思います。それはトロントでもどの国でも同じだったのではないでしょうか。
だからこそ、ミニシアター・エイド基金というミニシアターを支援するためのクラウドファンディングに、3万人から3億円以上が集まったのではないかと思います。一方で「映画が映画館で観られるのが当たり前」というのも実は東京や都市圏だからこそで、コロナ前からすでに映画館のない地域がたくさんあったことも忘れてはいけないと思います。

『LOVE LIFE』のことで言うと、脚本を直している最中に、たまたまコロナの時代になりました。でも、コロナ禍でソーシャルディスタンスと言われ、人と人との距離が大きな問題になったことで、「離れていても愛することができる」という矢野顕子さんの歌詞が、また新たな意味になって更新された気がしています。今みたいに取材も、オンライン取材が増えました。それは便利でもある一方で、国と国との移動は以前よりハードルが上がりましたし、感染を恐れて故郷に帰れないというケースだってあちこちで聞きます。そんな中で、離れていても愛することができるという歌詞が、いろんな意味でもって響く時代になったなと思います。
――深田監督は、コロナ禍で日本国内の映画館が一斉休業に追い込まれた2020年4月に、濱口監督らと共同でいち早くミニシアター・エイド基金を立ち上げ、日本の映画業界全体のために率先して活動されてきた印象があります。また、各種ハラスメントが今ほど世の中で大きく取り上げられていなかった2019年の時点でハラスメントに対する姿勢を表明するなど、常に時代の先を行く取り組みをされていると感じます。このような行動は、どのような意識から生まれているのでしょうか。
まず、ミニシアター・エイド基金に関しては、自分だけでなく濱口竜介監督を含め5人のメンバーがいたからできたことで、その他にも本当に同時多発的に色々な動きが起こりました。当時、SAVE THE CINEMAという、国や文化庁に助成金や補償を出すよう訴えかける動きも始まり、コロナ禍で、このままだとミニシアターが危ない、とみんなが動いたと思います。たまたま自分と濱口さんはお互い連絡が取り合える立場にあったこともあり、いち早く連携できたのかなと思います。二人とも自主映画出身で、もともとミニシアターと距離が近かったこともあったと思います。
ハラスメントのことに関しては、自分自身が時代の先を行っているとはまったく思っていないんです。自分自身が20歳くらいのスタッフ時代に、現場で殴られたり蹴られたりしていて、それは嫌なことだなと思っていましたが、当時はこの業界では当たり前のことだと思っていました。でも、フランスなど海外の話を聞くと全然違うし、関わった劇団青年団でも2005年に入ったときには、もうセクハラとパワハラに関する厳しいガイドラインができていて、劇団員全体に共有されていました。そんな状況の中で、逆に自分は時代の流れよりも遅れてハラスメントは良くないと思い始めた感じです。映画業界がそれ以上に遅れていたから、相対的に先にいたように見えただけだと思いますし、自分も十分に対応しきれてきたわけではありません。
――劇団・青年団は、わりと時代の先を行っていたんですね。監督は海外での制作経験もおありなので、それで国内の現場との違いを感じていたのかなと思っていました。
もちろんそれもあります。海外の話を聞くと、まったく違うと本当に感じますね。例えば日本の映画の現場でも、「良い映画を作るために人を殺してはいけない」とか「良い映画を作るために犯罪をしてはいけない」と言って反対する人はまあいないとは思うんです。でも、フランスなど海外のスタッフと話していると、良い映画を作るためにスタッフを怒鳴ってはいけないし、良い映画を作るためにスタッフの睡眠時間を削ってはいけない、スタッフが家族と団らんする時間を奪ってもいけない、という感じで、感覚が全然違うと感じます。そういう話は、海外の映画祭に20代後半の頃から行くにつれて、どんどん耳に入ってくるようになりました。
――今の日本全体で、殴ったり怒鳴ったりがなくても、長時間労働は普通にあると思います。そんな中、映画の撮影なんて想定外のことが起きがちで、時間も延びがちだと思いますが、どのようにコントロールされているのでしょうか。
殴ったりするような直接的な暴力は、以前よりは減ってきたとはいえ、でもまだありますね。話には聞きます。自分の映画の助監督をやってくれた方が、前の現場で殴られたと言っていて、それが2019年の話なので、今でも全然ない話ではないと思います。
長時間労働を本当になくすためには、相応の制作予算が必要です。仮に制作予算が300万円増えれば、もしかしたら撮影日数を1日増やすことができるかもしれない。撮影日数が1日増えれば1日当たりの撮影時間を短くできます。
いろいろな要因がある中で、撮影が延びてしまう原因のひとつに、やっぱり監督の責任もあると思います。自分が監督なので、監督に対してはどうしても厳しめに見てしまうんですけど。ある意味で「良心的」なプロデューサーほど、監督がもっと撮りたいと言えば撮らせてくれるんです。粘らせてくれる。でも、本当にこのシーンを粘っていたら徹夜になって、スタッフの睡眠時間がなくなると思ったときに、現場を止めることができるのはプロデューサーか監督しかいません。監督が気持ちいい声で「OK」と言えば、撮影はそこで終わるので。それを決断できるのは監督しかいません。もしかしたら、もっと粘って深夜の3時までやれば撮れた画があるかもしれないし、もしかしたら芝居が良くなるかもしれない。それは「かもしれない」で、そうとも限らないけれど、その「かもしれない」は諦めるしかない。それは最初からないものだと思うしかないと思っています。
自分はよく「ドーピング」という言い方をしますけど、時代によってドーピングの基準も変わってくるわけで、今はもう連日徹夜や長時間労働をしたり、俳優やスタッフを追い詰めたりすることで得られるかもしれない結果はドーピングだと思って諦めるしかない。それはもう最初から拾いに行かない覚悟が必要じゃないかなと思います。どうしたら、旧来のやり方とは違う方向で目的を達成できるかを考えていかないといけません。とは言いながらも自分の現場でも撮影が長時間になってしまうことがあるので、本当にもうちょっと頑張らないといけないし、予算を増やす努力もしなくちゃいけない。そのためには、構造的な改革も個々の努力と同時に進めていかないといけないと思っています。
――どうしても妥協したくないクオリティのラインもあるのではと思います。そのラインと、もう少しやればいけるかも、みたいな兼ね合いは、どのように判断するのでしょうか。
そこはもうせめぎ合いですね。いつも悩みながら撮影に臨んでいます。優先順位を決めて、このシーンは早めに撮って、次のシーンはじっくり撮ろうとか、やりくりをしていって。どうしても時間が足りないとなったら、クオリティを下げるしかないです。それは、それだけの予算を集められなかった自分の責任でもあるし、プロデューサーの責任です。限られた予算や日数の中で非常識な無茶をしなくてはえられないクオリティは、そもそもそれは求めてはいけないクオリティだったと考えるしかないですし、製作側はそれを受け入れるしかないです。
――国内外の映画界の事情を踏まえ、今後はこのような制作現場を作っていきたいとか、このような作品を作っていきたいといった展望があれば教えてください。
いくつか企画は動いていますけど、時代劇が作りたいですね。予算を計算すると10億円以上かかるんですが(笑)。
――最後に、トロントの読者へメッセージをお願いします。
トロントで『LOVE LIFE』が劇場公開されるかまだ分かりませんが、皆さん『LOVE LIFE』というタイトルだけでも覚えておいてもらって、公開されたときに覚えていたらぜひ観に来てください。よろしくお願いします。
1980年、東京都生まれ。1999年、映画美学校フィクションコース入学。2005年、平田オリザ主宰の劇団・青年団に演出部として入団。『ほとりの朔子』(2013)でナント三大陸映画祭グランプリ&若い審査員賞受賞。『淵に立つ』(2016)でカンヌ映画祭「ある視点」部門審査員賞受賞。『本気のしるし《劇場版》』(2020)がカンヌ映画祭公式作品に選出された。トロント国際映画祭への出品は、『淵に立つ』、『よこがお』(2019)に続き三度目。
『LOVE LIFE』
再婚して夫と子供と3人で幸せに暮らしていた女性が、ある出来事の後、突然戻ってきた前夫の世話を焼くようになる。夫のほうも、過去に恋愛関係にあった女性との関係がくすぶり始める。
監督・脚本:深田晃司
主演:木村文乃、永山絢斗、砂田アトム、山崎紘菜、嶋田鉄太、三戸なつめ、神野三鈴、田口トモロヲ
©2022映画「LOVE LIFE」製作委員会 & COMME DES CINEMAS