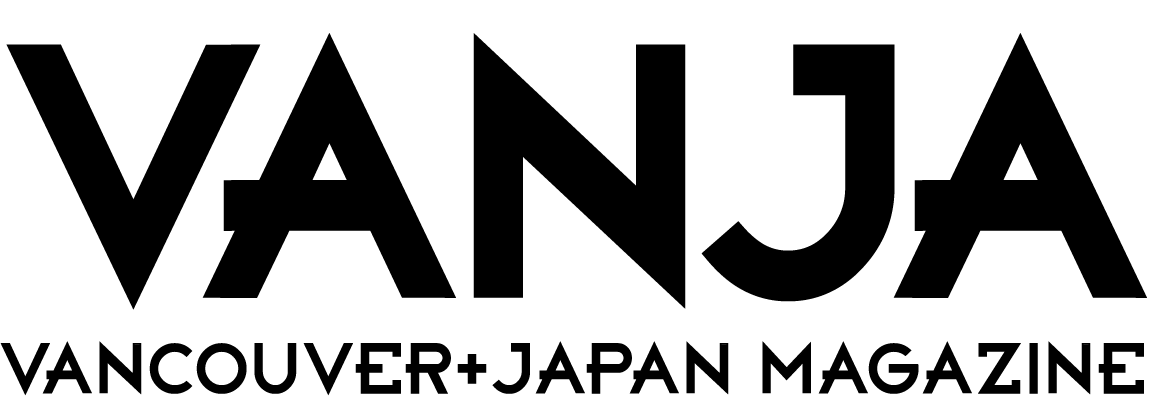2020年12月から、Toronoto Film Magazineでトロント国際女性映画祭の受賞者が発表されている。この映画祭は、女性の製作者が携わった映画や女性を描いた映画を対象としており、最優秀作品賞や最優秀女性監督賞、最優秀女性脚本賞などが毎月発表される。毎月の受賞作品の中から年間を通して選ばれる最優秀作品は、2021年11月にTIFF Bell Lightboxでの上映が予定されている。
6月に発表されたトロント国際女性映画祭のSixth Editionでは、最優秀女性監督賞に『にしきたショパン』の竹本祥乃監督が選ばれた。『にしきたショパン』は、兵庫県の西宮北口を舞台に、ピアニストを目指す幼なじみの男女を描いた物語。竹本監督にとっては本作が初の長編監督作となる。日本では2021年3月に劇場公開され、世界各地の映画祭にも出品されている。初の長編作品で最優秀女性監督賞に輝いた竹本監督に、これまでの歩みや映画製作への思いなどをお伺いした。
映画『にしきたショパン』について
―映画『にしきたショパン』では、ピアニストを志しながら震災が原因の怪我で挫折する青年と、同じくピアニストを志す幼なじみの女性が主人公でした。過去の作品でも音楽が特徴的で、音が聞こえない人が出てくるなど、常に音楽が絡んでいる印象を受けます。そこには何か理由があるのでしょうか。
ピアノを小学校1年から中学校3年まで習っていて、音楽の素養があったことが大きいと思います。それと、音楽を聴いていると映像が浮かんでくることがよくあります。
―クラシックなど歌詞のない音楽でも映像が浮かんでくるのでしょうか。
歌詞がなくても頭の中に映像が浮かんできて、物語ができていきます。あとは、高校生のときに夏目漱石の「こころ」を習ったら、勝手にサイドストーリーが浮かんできて絵を描いていました。音楽でも小説でも、ありありと映像がついてくるんです。小さい頃から映画が好きだったこともあって、少しずつ映像が浮かんでくるようになりました。映画を観ても、感動した場面が長いこと頭に残って、何度も思い返してしまいます。
―映画『にしきたショパン』はピアニストを目指す青少年を中心とした物語で、ピアノ演奏に長けた俳優陣や、劇中で使用する楽曲の編曲者などが必要だったことと思います。適任者を探す苦労はなかったのでしょうか。
それが、とてもうまく見つかりました。オーディションの公募が人づてで広がり、主人公の凛子役の水田汐音さんには、ピアノの先生が応募を勧めてくれました。彼女はピアノの腕がいいのはもちろん、何でもできるスーパー高校生でした。芝居のレッスンを受けたり劇団で演じたりと、ちゃんと演技の素養もありました。鍵太郎役の中村拳司さんは、阪急電車のポスターでもよく見かける現役のモデルさんです。雰囲気を変えるのがとても上手く、彼だとわからないくらいですが。このガラッと空気を変えるところは天性のもので、それが芝居にも活かされています。編曲の沼光絵理佳さんは『のだめカンタービレ』の曲を担当された方で、関西の方です。週末にオペラ歌手をしていた近藤プロデューサーが、知人のパーティーで歌ったときに伴奏したのが沼光さんで、素晴らしい音楽性に惚れ込んで彼女に編曲を依頼しようということになりました。

―そんなふうにうまくつながるものなんですね。
近藤プロデューサーが偉大なんです。彼の人脈と人望で実現した感じで、私はそれに乗っかっています。近藤プロデューサーとは、『Arcadia』という作品を撮影したカフェをお母様が経営されていたのが縁で出会いました。『Arcadia』をカンヌで上映すると言ったら興味を持ってくださり、「こんな本を書いたんだけど…」という話になりました。「マスター先生」という西宮北口にあるバーのマスターをイメージした話でした。『にしきたショパン』に出てくる先生が、本当に凄腕のピアニストだった方が先生になり、震災を経てバーのマスターになった方なんです。そのお店が大好きで入り浸っていた近藤プロデューサーが書いた本を、映画化することになりました。映画化の過程で物語は大きく変えましたが、バーのマスターはどうしても入れたいという近藤プロデューサーの思いがあって、あのような作品になりました。
―映画の舞台を西宮北口にしたのは、そのバーがあったからでしょうか。
近藤プロデューサーの思い入れが強かったことが大きいです。文化の薫り高い街で、ぜひここを舞台にしたいという思いがすごくあったので、それが映画の方向性になりました。土地への思いを始め、プロデューサーの思いが詰まった映画です。

トロント国際女性映画祭での最優秀監督賞受賞と、映画祭に対する思い
―昨年12月からほぼ毎月発表されているトロント国際女性映画祭の各賞のうち、6月に発表されたSixth Editionで最優秀女性監督賞を受賞されました。現在の心境はいかがですか。
トロント国際女性映画祭の最優秀女性監督賞は、メールで連絡が来て驚きました。今やもう、映画祭の受賞者発表がオンライン中心になっているのは、少し寂しいですね。
―竹本監督は、過去の短編作品も今回の初長編作品も積極的に世界中の映画祭に出品されていますが、世界に積極的に出て行かれるのは、どのような思いからでしょうか。
マーケットは日本だけではだめだと思っているんです。Netflixにしろ、時代はオンラインの映画なのに全然追いついていないし、国内向けだけでは先細りだなとすごく思います。

映画製作を志したきっかけについて
―竹本監督は、平日は研究所で研究技術者として仕事をしながら、休日を使って映画製作を続けておられると過去のインタビュー記事で拝見しました。映画製作について専門学校などで学ばれた経験はないのでしょうか。また、それにもかかわらず映画を作り始め、苦労されたことがあれば教えてください。
映画の学校には行っておらず、理系の大学を出て就職しました。ただ、漫画を描いて投稿していたことがあり、話を作ったり画でイメージしたりという基礎はありました。漫画家になりたいと思っていましたが、就職すると時間がなくなりました。でも就職してから、頭に浮かんだ映像を形にしたいという思いが出てきて、まずは学生の自主映画を手伝いに行きました。そのとき、撮影現場を1日見ただけで自分でも作れると思ってしまい、人を集めて撮り始めました。すると、めちゃくちゃ大変でうまくいかず、次はこうしよう、と思いながらやっているうちに、結局は学校で習うスタッフワークにたどり着いていきました。最初から学校で習えば良かったんですが。
―脚本を書くのも、漫画のストーリーを考えるのと近いものがあるのでしょうか。
台詞を言うところは漫画に近いものがあります。また、文章を書くのが好きで、日記を書き続けていましたし、小論文を書くのも得意だったので、脚本は特に苦もなく書けました。
―そうはいっても、いきなり映画を作れるものではないように思うのですが。
1作目はぐちゃぐちゃでした。当日遅刻してくる人はいるし、思うように撮れないし、時間内に終わらないし。それでも何とか、つぎはぎだらけで完成させました。1作目は一人で全部やってしまいましたが、次はもっと役割分担をしました。シナリオも3ヶ月だけ講座を受けに行き、文章の組み立て方や構造をきちんと学びました。自分が役者の気持ちを理解できたら指示もうまくできるのではないかと思って、芝居も1年間、夜間に習いに行きました。やってみたら、自分が無茶振りしていたなとか、いろいろ気づきました。役者のタイプによっても違うしコンディションもあるので、相手によって言い方を変えるとか、役者がベストコンディションになるよう気を配るようになりました。あとは、自分の作品に台詞が多いなと気づいて、次の作品は台詞なしで作ったり。毎回習作のつもりで、次はこうしよう、というのを積み重ねてきました。

―これまでたくさん短編作品を撮ってきておられて、今回は初の長編監督作とのことですが、長編作品を撮ることになった経緯を教えてください。
これまで実現はしませんでしたが、長編のシナリオを書いたり他人の長編を編集したりといった経験はあったので、長編がどれほど大変かというイメージはありました。いつかは作りたいという淡い思いはあったものの、まずお金がかかるので大変ですし、一人では無理です。コンペに企画が通らなかったというのもあります。短編で企画が通ったことはありましたが、金曜に仕事を終えて神戸空港から東京へ行って撮影し、また日曜に神戸空港へ戻ってきて仕事へ行く過密スケジュールで、赤字でした。
―就職する前は映画を作りたいとは思っていなかったのでしょうか。
漫画家になりたいとは思っていましたが、それは夢だと思っていました、職業的に無難な理系コースに進んでしまったし、学生をしながら漫画家としてデビューして安定収入が得られればいいなとは思っていましたが、そんなふうにうまくはいきませんでした。
―そもそも大学で文学部などに行こうとは思わなかったのでしょうか。
15歳くらいで受験を考えたときに急に現実的になりました。芸大に行きたいけれど仕事がなさそうだなと思って。そのときは、アーティストは貧乏か才能がある人か、どちらかしかいないと思っていました。それと私の性格上、万能選手を目指しているようなところもありました。文系科目が得意だけれども、苦手なところができるようになれば万能じゃないかと思って、仕事のある理系に行こう、と思いました。でもどこかで芸事も諦めていなくて、漫画家デビューできればいいなと思ってずっと描いていました。また、社会人になったら時間がないと先輩から散々聞いていたので、学生時代には通信教育をかけもちして、ダブルスクールをしていました。学生時代にいろいろやっておこうと必死でしたが、今思えば学生のときのほうが大変でしたね。

―短編はいつ頃から撮り始めたのでしょうか。
最初の就職先が人生で一番大変で、夜勤もあって自由がありませんでした。そこを辞める前から、映像が思い浮かんで撮りたいと思っていて、次は安定して休みが取れるところで仕事がしたいと思うようになりました。それで映画を作ると決めて転職し、その通りの生活を始めました。映画作りをやってみて、失敗しては勉強して、と実戦で学んでいった感じです。
―『にしきたショパン』が劇場公開されたことで、次回作を期待している観客もいるのではないかと思います。今後のご予定はいかがでしょうか。
次もまた近藤プロデューサーとともに音楽を軸にした長編作品を構想中で、取材したり資料を読んだりしています。今は『にしきたショパン』でやりきって、自分の想いが成就したような気分で、少し落ち着いていたのですが、次も作らなきゃいけないよね…と思っている贅沢な状況です。これまではアマチュアでしたが、今後はプロとしてやっていこうという思いもあります。映画はカット割りの芸術なので、カット割りももっと勉強しようと思っています。
―最後に、トロントの読者のみなさんに一言お願いします。
トロントは、美しい街だと聞いております。観客としてでも、来年度は是非トロント国際映画祭に参加したいです。
2007年頃から映像制作開始。『雲と空』(10)が第32回ぴあフィルムフェスティバルに入選。『お喰い初め』(14)、『青い蝶の夢』(14)、『はみだしっこ』(14)、『受胎告知』(16)、『Indigo Children』(17)、『Arcadia』(18)といった短編をカンヌ国際映画祭Short Film Cornerで上映するなど、数多くの短編を制作。『にしきたショパン』(20)は初の長編作品。

『にしきたショパン』
脚本・編集・監督: 竹本祥乃
出演: 水田汐音、中村拳司、ルナ・ジャネッティ
プロデューサー: 近藤修平
脚本: 北村紗代子
©2020 Office Hassel