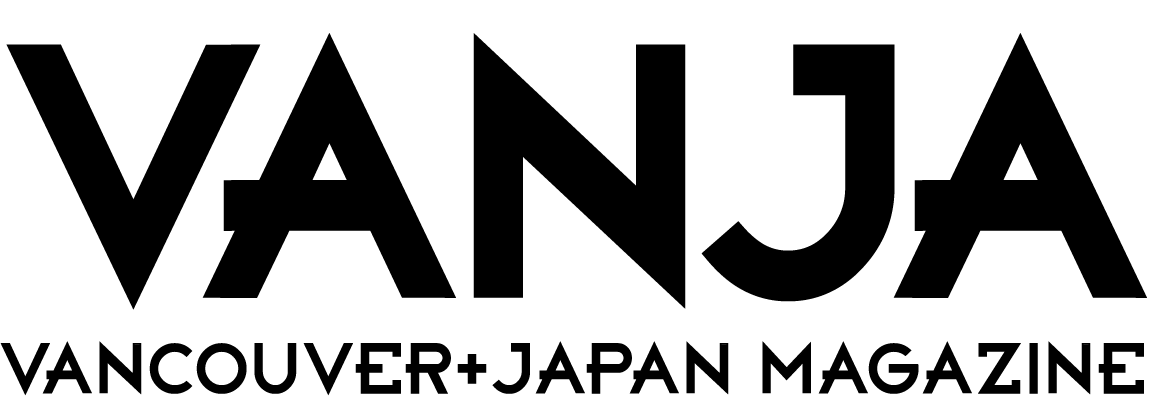メディアを最大化する日本代理店、マスメディアとともに凋落
日本の広告代理店は、長いこと「メディアの代理店」と言われてきました。それは日テレ、TBSといったテレビ局の設立にも大きくかかわった電通の吉田秀雄が作り上げたモデルであり、テレビ局が各都道府県に自社のネットワークを広げていき、「日本全国に放送できる=日本の多くの国民に同時に広告を領布できる≒広告単価を上げられる」という形で、1日24時間のうち限られた割合でしか挟めないTVCMの価値を最大化するプロセスでした。同じ視聴率1%でも、関東圏だけなら30〜40万人でも、全国なら100万人になります。日本全国にネットワークを張り巡らしたキー局のCM枠であれば、東京MXの1%より数倍の価値になる、というわけです。
テレビ局の広告枠は高値で取引され、地方局なら数万円でも、全国向けキー局の夜20時代のゴールデン枠なら30秒1回で500万、といった高額取引されるケースまであります。1時間に流せるCMは30秒枠が多くても20~30本、1本100万円で売れるなら、その1時間で2~3千万円の収益が入ることになります。その収益が番組制作費やテレビ局の運営費になるのです。テレビ局は年1千億円くらいかけてテレビ番組を作ったり買ったりして、それをもってCM枠で2千億円の売上をたてる。代理店もその動きに乗っかります。彼らの15%のマージンは「1時間を2千万で買う企業よりは3千万で買ってくれる企業に」と価格を上げることで最大化するのです。
より高い視聴率を獲得し、より多くのユーザーにCMをみてもらい、その枠をより高い金額で。こうした好循環のスパイラルは1960年代の黎明期から2000年前後まで続きます。2000年代は視聴率こそ落ちてきていましたが、なんとか収入を保つも、リーマンショックとその後のスマートフォンの普及で2010年代は非常に苦しい時代でした。年間平均視聴率は1%さがると広告収入が100億円失われるといいます。この10年もっとも調子が良かった日テレは平均12%前後を保っていますが、一番厳しかったフジテレビは2010年の12・6%から2020年には8.0%、この10年で450億円分相当の視聴を失う状況になりました。
テレビ局の苦しみは、日本においては代理店の苦しみです。ただそれでもテレビはまだ全然マシ、広告費がこの20年で半分以上失われている新聞・雑誌・ラジオでいうと、マスメディアの番人となり、その価値を高めてきた代理店の役割は徐々に縮小しているのです。
広告主を最大化する欧米代理店、2000年代に成長期を迎える
では米国・欧州の代理店はどうでしょうか?実は米国は「広告主の代理店」で、ナイキならナイキの広告費をどのメディアに出すのが一番よいかを選択する立場なのです(それゆえに競合の案件はとれない。ナイキとやっている代理店はアディダスの広告をとれません)。そのため代理店はメディアの盛衰には敏感であらねばならず、「ノッているメディア」にどんどん広告投資を移し替え、広告主が満足するパフォーマンスを上げ続けることが生存戦略になります。世界最大手のWPP(英国)は2兆円近い売り上げ(以前はADKと資本提携もしていました)。Ominicom(米国)、Interpublic(米国)、Publicis(仏国)もそれに続き、すべて1兆円規模の企業です。電通も2012年にAegis(英国)を4千億円で買収し、トップ5に唯一名乗りを上げられた日本の代理店です。ただこれらの世界大手は1995年以前にはそれぞれ2千億程度の売上しかありませんでした。当時はむしろ電通が世界最大手といえたかもしれない状況です。

ではなぜマスメディアが弱体化するこの時代に、欧米の広告代理店はこれほど成長したのでしょうか。それには米国におけるメディアの変遷が大きく起因しています。図1をみると、実は1980~90年ごろは日米でそれほど広告市場の差がないことがわかります。なんなら1980年には日本の広告市場の成長幅は米国を追い抜かんとする勢いすらありました。両国の差は1995年ごろから格段に開きます。これはケーブルテレビ、地方局、シンジケーション(地方・独立局の集合ネットワーク)といった「地上波以外のテレビ」が急激に成長し、新しいプレイヤーによって新しい広告枠が生まれたからです。米国の地上波はずっと140億ドルとこの20年ほぼ成長していません。日本のTV広告2兆円市場のほうが大きいのです。それでも米国には267億ドルまで成長したケーブルTV広告、182億ドルの衛星TV広告が生み出され、さらにはデジタル広告がすでに1千324億ドルとすべてを飲み込む勢いです。先ほど言ったように欧米の代理店は「広告主の代理店」、こうした動きに呼応して、伝統メディアを切り捨て、新規のメディアとともに成長機会を広げていったのです。
日本においては広告代理店の存在感がとても大きい。それはメディア≒広告代理店であり、二者が一緒になって「広告の価値を守ろう」という方向に舵が切られやすいからです。米国の新聞広告が486億ドル(2000年)→58億ドル(2018年)に十分の一になるような激震時代において(雑誌は21億から6億ドル)、日本の新聞広告が1.2兆→0.5兆円と二分の一くらいにしかなっていない(雑誌は4千億→2千億)のは、サブスクモデルもありますが、代理店が一緒にメディアを守ってきたからという特性も色濃く出ています。あながち悪いことばかりでもなく、それがゆえに日本の活字メディアが米国よりもかっちり残っており、伝統が守られている、という見方もできないことはないでしょう。
では日本の代理店も欧米のようになっていくのか?事はそれほど簡単でもありません。実はWPPもPublicisもM&Aを重ねてなんとかその巨体を維持していますが、デジタル広告の業界では完全に負け越しています。経営コンサルのAccentureDigitalはすでに103億ドルの世界最大手のデジタル広告代理店になっており、2位はDeloitteDigitalの79億ドルです。WPPのデジタル部門はまだ19億ドルにすぎません。また広告主も代理店を通さずにグーグルとフェイスブックに直接広告をだすダイレクトモデルに慣れ始め、代理店の存在自体も疑問視される時代になっているのです。欧米の代理店が正解をもっているわけでもないのです。
ここの経緯は第46回で「不動産ディベロッパーのように広告という「場所」を管理していたマス広告代理店」から、「オペレーション力の店舗マネジャーのような仕事になり、中小含めた大激戦になっているデジタル広告代理店」という時代の変化で述べたとおりです。もはやメディアとの関係性は武器にはならず、氾濫するような数えきれないメディアと入札ベースの無数の発注との間で、KPIデータの最適化というテックとオペレーションがモノを言う世界に入っているのです。デジタル広告が我々に与えたものは「広告の民主化」です。1人のユーチューバーが自分で5千円~1万円という単価でも入札を行い、ユーザーを数百名「購入」することができる時代になっています。
テレビはアクションへ、デジタルはブランドへ、スポンサー・PRは維持

10年後、広告市場の未来はどうなるのでしょうか。図2はクレディスイスが予想する2030年の米国広告市場です。新聞・ラジオ・雑誌はもう「マス」メディアとは呼べないでしょう。それら退潮は明確で、すでに半減以下になっているそれらの市場はあと15年でさらに三分の一~五分の一に縮んでいきます。ではテレビはどうかというと「成長している」のです。これはテレビがスマートテレビ化して、PCやモバイルと同じように「ネットコンテンツへのアクセスの箱」になることを意味しています。テレビ局が提供する放送コンテンツではなく、動画配信やユーチューブが提供するコンテンツも含めて「リビングで大画面で家族が複数人で見る箱」としてはPCともモバイルとも違う価値を提供し続けられるはずだという期待も込められています。
面白いのはスポンサーやPRといった効果の見えない「ブランド広告」もずっと3割強という割合は保ちつつ、成長することが予想されている点です。これはネット広告を活用してきたゲーム企業がたどった道ですが、1人1人のユーザーを「購入」するようなデジタル広告は結局ムーブメントを起こせないのです。なんとなくそこに興味ない人も効果があいまいな状態でみる「ブランド広告」、は実は人に潜在的にそのブランドを認知させ、いつのまにかファンになっているようにファンを作り出す。この効果に広告主は今後もずっと3〜4割の広告費は張り続けるだろうという予想です。これは予算の9割がデジタル広告にばかり投じられるアプリゲーム業界の広告効果をみてきた自分も深く同意します。人々は商品を買うために広告をみるわけではなく、広告がもつメッセージにストーリーを読み込み、その商品を取り巻く世界に参加・参入・関与したくて、広告を見に来るのです。押し売りのような5~10秒の「買ってね」「インストールしてね」「いまなら10連ガチャ無料」といったフラッシュなCMではなく、何を売っているかわからないけど胸を打つようなイラストや音楽、一瞬の映像美をもつCMに、突き動かされるわけです。
広告の価値は不変です。1900年からそうだったように、2100年においても、ハコと見せ方は変わっても、資本主義がある限り広告もあり続けます。購買欲を訴求させ、経済をまわす大事な役割を広告は永久的に持ち続けます。ではそれに対して我々が起こすべき変化は…?それは図2でみるような、中長期では皆が思い描いている世界に対して、今このタイミングで直近では具合が悪く、不便であっても、そこに多くのPDCAを回し続けている人・組織・文化なのだろうと思います。