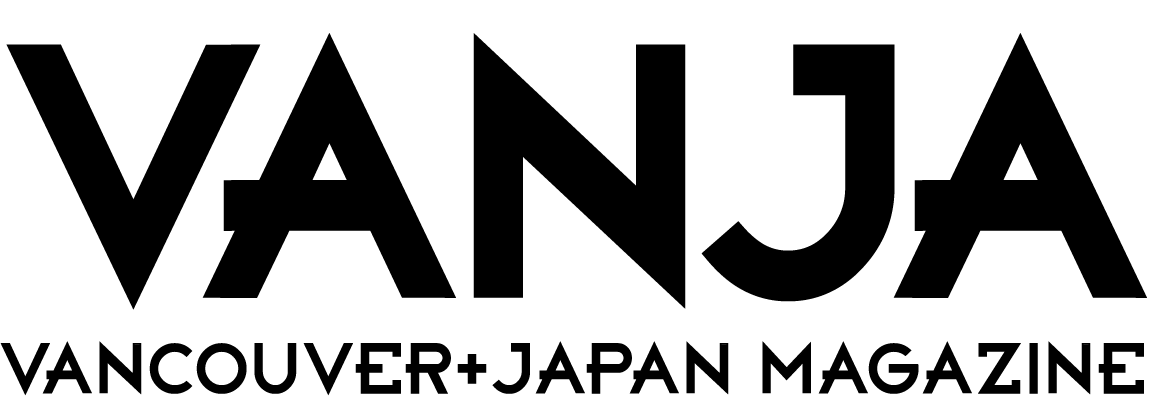1940-60年代:「低俗メディア」アメコミのしがない編集者
ディズニーマーベルは世界中に響き渡っていますが、「スタン・リー」の名前を知る人は少ないかもしれません。2018年に95歳で亡くなった、マーベル・コミックの原作者であり、1940年の18歳の時からマーベルの編集長の地位にあり、〝ハルク〟も〝ソー〟も〝アイアンマン〟も〝スパイダーマン〟も彼の手によって生み出されました。日本の手塚治虫や鳥山明といったマンガ家たちと比べて、著作権を買い上げられる米国出版業界においてはその作家の名はそれほどには知名度が高くありません、8千以上ものキャラクターをもつマーベルを支えてきたにも関わらず。それは絵を描くのは別の人間だったり、プロットも外注するような「チーム制作」が米国のコミックスタイルだから、というのもあるかもしれません。
出版社「マーベル・コミック」は1939年に設立され、〝スパイダーマン〟ブームに沿って、〝キャプテンアメリカ〟をナチスドイツと戦わせた1941年のヒットからはじまります。ですがアメコミ不況の50年代は倒産の危機を味わいながら息も絶え絶え存続し、リーが生み出した61年〝ファンタスティック・フォー〟を皮切りに、62年には「クモ男など売れるはずがない」と社内の大反対を押し切った〝スパイダーマン〟が当たり、〝ハルク〟も〝ソー〟も
〝アイアンマン〟と次々に量産されるなか、50年後の大ブームを支える〝アベンジャーズ〟が1963年に生まれます。
ただ数百万人もの読者がいたこの時代でも、アメコミはまだまだ「低俗メディア」と呼ばれ続けました。子どもや文字に弱い労働者階級の読み物、というイメージもあり、また流通としても、新聞スタンドや書店といった「一般的な場所」では売られず、返本なしの完全買い取り制(すなわち在庫がきれたら二度と手に入らない!)でホビーショップなどの専門店が買い取っていただけの、あくまでコレクター向けの市場でした。またマーベルとしても何度かブームもあったものの、60年代までは75ミリオンドル売上のDCコミックを20〜30ミリオンドル売上のマーベルが二番手で追い上げるという構図でしかありませんでした。
1970-90年代:ミニ・ディズニーを目指しながら資本家の遊び道具

日本のマンガ・アニメがそうであったように、米国もまた業界内で「俺たちはこんな業界で終わる器ではない」といった根底的な自己否定があります。60年代アニメの時代、70年代は玩具の時代、80年代は映画の時代、つねにリーたちは「コミックではない何か」で自分たちのプレゼンスを上げようと必死でした。60年代のマーベルアニメは海外にも放映されましたが、あくまで番組の埋め草のような扱いで出来も悪い。70年代に玩具化など商品化すると、だんだんコミックよりもパッケージに絵を載せるビジネス中心の商売になり、コミックスも凋落気味。1977年に映画化された「スパイダーマン」もリーに言わせると「あまりにお子様向けで何の個性もない」と酷評。地上波最大手のCBSもスパイダーマン、ドクターストレンジ、キャプテンアメリカを実写化したものの、それらも後世に残るようなしろものではありませんでした。
1977年のスターウォーズで映画業界が大活性時代に入り、誰もがハリウッドに憧れる年代に入り始めるころ、リー自身もロサンゼルスに移住してマーベルキャラの映画化に尽力します。だが、NYでは売れっ子コミックライターも、ハリウッドでは新参者の脚本家。500ドルで脚本を叩き売られた挙句映像化もされなかったり、映像化されても映画として全く不出来だったりと、彼が求め続けた「ミニ・ディズニーになる」という夢との差は開くばかり。
映画や玩具業界が大きく羽ばたいた80年代において、米国コミック業界は「置いてけぼり」になった印象が強いです。日本が任天堂やバンダイ、小学館・集英社などの出版社がアニメやゲーム・玩具の商品化の力、そして廉価のマンガ週刊誌の浸透で200〜300億円から1千億円になっていくこの時代に、米国ではアメコミは古いヒーロー型に依存し、どちらかというとカードゲームやアクションフィギュアなど「アングラ」な世界でなんとか収益化に四苦八苦し、最大手のマーベルでも出版では100億円規模を超えることがなかった、(規模の上では)失敗した業界だったのではないかと感じます。
それは資本を取り巻く抗争もまた、マーベルの足かせとなります。最初のオーナーのグッドマン(常にリーのクリエイター路線を否定し、他社の売れたキャラの真似をしろと急き立て、売却タイミングを計ってきた投資家型経営者)は1968年に15ミリオンドルで出版社のケイデンスに売却、それも1986年に46ミリオンドルでニュー・ワールド・ピクチャーズ(NWP)に売却。このNWPもまた眉唾で、当時の社長は買収交渉中にマーベルがDCコミックスではないことに気づき、「買うのはスーパーマンじゃなくてスパイダーマンだって!?そんなB級ヒーロー買ったって…」と途中で中止を叫んだという話があるほど、無理解な資本家たちの政局の具になっていた感じがあります。マーベルの価値を実際にワンステージ上げたのは、そのNWPから1989年に82・5ミリオンドルで買い取ったペレルマンです。
ペレルマンの挑戦と失敗
今を思えばこの数十億円規模での取引はあまりに安く思えますが、当時の米国のアメコミ市場の地位の低さ、その中でマーベルの不安定な経営などを考えると、それほどバリューがつかなかったこともさもありなん。ペレルマンはここから「ミニ・ディズニー」に向けて急激に攻勢をかけます。1992年にトレーディングカード2番手のFleerを286ミリオンドルで買収、1993年にAvi Arad率いる(のちにプロダクションIGの米国支局長、バンダイナムコの米国アドバイザーにも就任する業界大物!)玩具デザインメーカーToy Biz買収、1994年にイタリアのスポーツ・エンタメグッズ企業Paniniを150ミリオンドルで買収、1995年にカードメーカーSkyBoxを150ミリオンドルで買収し、キャラクターを商品化する「メディアミックス型」への変貌を遂げます(1995年には830ミリオンドル売上のうち本業の出版は17%に過ぎず、カード、玩具、子供向けステッカーで2割ずつ稼ぐような、コングロマリットに成長していました)。また競合となるHarvey ComicsやMalibu Comicsを買収し、DCコミックスにさらに差をつけます。
こうした積極攻勢の結果、89年に82・5ミリオンドルの時価総額はなんと1993年には3300ミリオンドルへと30倍規模に膨らみます。ただ、焦りすぎた成長は根付きにくいもの。900ミリオンドル近い負債による急激なM&A成長はひずみをもたらします。90年代半ばのトレーディングカード市場の急落などを受け、マーベルの会社価値は泡沫に帰します。IPO後の91年の3ドル弱から、1993年末に35ドル近く付けた株価は、94〜95年と10〜15ドルまで下落、96年の倒産間際には当初3ドルも割りかねないほどに凋落していました。その弱点を突かれ、債権を買い集めた乗っ取り屋との経営権争いになり、結果として96年の倒産を選択します。60年間守り抜いた伝統とキャラクターカタログは、直近10年の急激なアップダウンに振り回され、頂点となった93年から5年持たずに倒産、債権放棄となったのです。
図1でマーベルの売上をみてみると、80年代まではあくまで100億円未満の一出版社でしかありませんでした。その成長はバンダイや小学館、ディズニー、マテルなどほか日米のエンタメ・玩具・映像企業からみるとずいぶんと緩やかです。結果、1ビリオンドルを目指す総合エンタメ企業となるペレルマンの挑戦に構造的な体力がついていかず、倒産。マーベルのキャラクターカタログの本当の価値がみえてくるのは2003年のソニーピクチャーズによる「スパイダーマン」以降の話、ということになるのでしょう。
救世されたマーベル
乗っ取り屋アイカーンとの経営権争奪戦は結局AviAladのToy Bizが横やり救済する形で、マーベルコレクションはクリエイターたちの手に再び還ってくることになります。図1で1997年〜2001年までずっと赤字続きであったこと、苦しい時代でであったことがうかがえます。第72回でみてきたように、これはまさにソニーピクチャーズが買収後の米国経営移譲の失敗で忍従を強いられた時代と重なり、まさにソニーの米国映画での成功と、マーベルの復活は時期を一つにしているのです。

さてこの時期のリーの動きはというと、80年代以降映像化に乗り出しながらマーベルキャラクターのスポークスマンとして様々に動き続け、同時に多くのビジネスマン・投資家から食い物にされるという経験を味わい続けました。「第二のマーベル」となるべく、ドットコムバブルの中、オンラインでコミック配信できる会社を2000年に作りましたが、早すぎた挑戦で26ミリオンドルもの投資を溶かしながら売上は1ミリオンドルも行かず大失敗。その年のうちに破産宣告となって、訴訟問題になるも、悲しいかな財務情報にすらタッチできなかったリーは「張り子の虎」のように投資家・経営陣に騙されていたということで無罪放免。
マーベルから常に冷遇され続けてきたとみるリーは、長きにわたってマーベルとロイヤリティの訴訟を抱え続けていきましたが、年1ミリオンドルに過ぎなかったリーの収入が2005年のマーベルとの和解によって10ミリオンドルを超える金額になってきたあたりで、ようやく停戦となります。販売数の詐称は日常茶飯事、会社が買い上げた著作権をいくら使おうと、といった風情の初期米国出版業界の経営者たちの対応をみると、常に過酷な労働環境が取りざたされる日本のマンガ業界もそれほどでもないのでは…と思わざるを得ません。少なくとも米国と比較すれば、日本の出版社は著作者に肖像権をもたせ、作品の顔は作者であって出版社が影にいる、というスタンスを貫いてきたことは、なぜ米国の20〜30倍のコミック市場を日本が作れたのかの背景につながっているのではないか、と思います。
次回は21世紀のマーベルの復活と、ディズニー買収からMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)につながる話を展開する予定です。