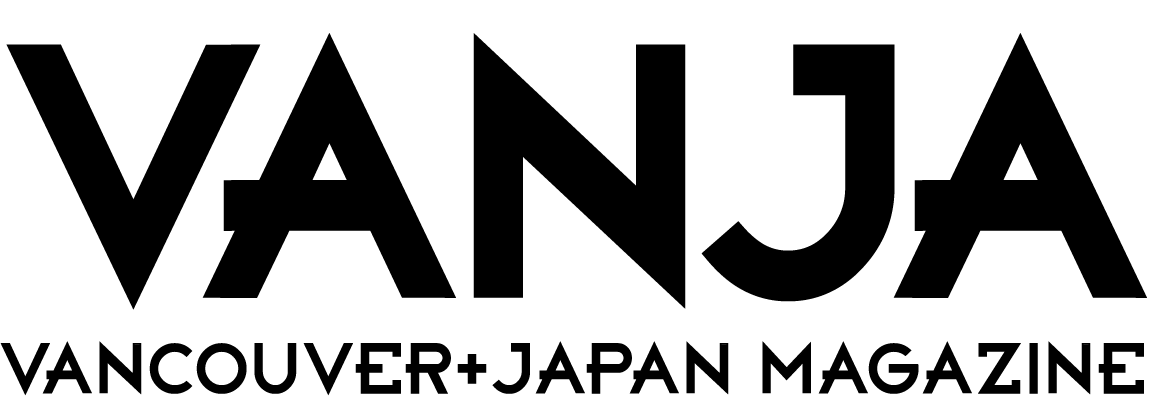オムニバス映画『十年 Ten Years Japan』の舞台挨拶に訪れた早川千絵監督
2022年5月のカンヌ国際映画祭でカメラドール特別表彰に輝き、6月に日本で劇場公開されて話題になった早川千絵監督の長編デビュー作『PLAN 75』が、9月のトロント国際映画祭でも上映された。本作の元になった同名短編作品は、5人の新進監督による短編オムニバス映画『十年 Ten Years Japan』の一編として2018年に日本で劇場公開されている。短編制作から長編化に至った経緯や、映画監督になるまでの過程について、早川監督にお話を伺った。
映画『十年 Ten Years Japan』での短編制作から長編『PLAN 75』の制作に至るまで
――『十年 Ten Years Japan』の短編『PLAN75』から長編の『PLAN 75』を制作することになった経緯を教えてください。
もともと長編で作ろうと思っていたのが2017年のことで、そのときは自分一人で考えていただけでした。プロデューサーもいなくて、どうやったら映画化できるかなと考えていた矢先に水野詠子プロデューサーから、『十年 Ten Years Japan』というプロジェクトがあるので、興味があったら出してみないかとお話をいただきました。10年後の日本社会を描くことをコンセプトに、是枝裕和監督が総合監修で5人の監督に短編を撮らせる企画でした。ちょうど『PLAN 75』がそのコンセプトに合うと思ったので、長編を作る前にパイロット版のような形でまずは短編を作ってみようと思いました。また、プロのスタッフと組む機会が初めてだったので、いきなり長編を作るより、短編を作ることで学ぶことができるんじゃないかという気持ちもあり、企画を出しました。もともと5人くらいの登場人物がいる群像劇だった長編を短編化するに当たり、登場人物を1人に絞って、18分の尺に収まる話にしました。
――もともと長編を作ろうとしていたところを、1人に絞って削っていくことは難しくなかったのでしょうか。
群像劇のうちの1人、一部を撮るのが、むしろ面白かったというか、それだけでも成立するように話を変えていくのがすごく面白かったです。
――もともとの群像劇は、今完成した長編作品とはまた違うのでしょうか。
何人かの主人公は重なっていますし、いくつかの物語や場面はそのままですが、当時から4年かけて脚本を書いていったので、最初のストーリーからは変わっています。最初の脚本は十分に練れていなかったので、それに比べて深みが増したと思います。
――1人に絞って作った短編を経て、最初の構想をブラッシュアップした長編に生まれ変わった感じでしょうか。短編『十年 Ten Years Japan』の監督5人のうち、こんなふうに短編と同じタイトルで長編化されたのは早川監督の作品だけですが、始めから長編化したい意向があったのでしょうか。
はい、ありました。そのことはプロデューサーにもずっと伝えていて、『十年』が完成した時点で、『十年』を一緒に作った水野プロデューサーが、長編版も一緒にやりましょうと言ってくださいました。短編を作る過程で信頼関係ができていて、お互いにこの人だったら一緒にやりたいと思えたのも大きかったと思います。水野さんは、ずっとこの『PLAN 75』を長編化するべきだと信じていてくださったので、それは大きな心の支えでした。
――もともと長編の脚本を削って短編にしたのなら、短編には入れられずに削った部分を長編化するときに戻す過程もあったのでしょうか。
そうですね。短編は尺が短いので、1人の人物を掘り下げて描くことはできないですし、解決策や物語の起伏、余白などを描くには短すぎるので、そういうところを長編ではもっとじっくり描きたいと思っていました。
――長編では、短編から俳優やスタッフが一新されていますが、どのように決まったのでしょうか。
長編は、短編とは登場人物が変わるので、あえて変えたというよりは、結果的に変わることになりました。「キャストを一新して」と書いている資料があるので、あたかも同じキャラクターを別の役者さんで作り直したかのように誤解されることがありますが、そうではないんです。短編のときには別の家族の話だったところが、長編ではまったく別の人たちが出てくるので、新しい役者さんにお願いすると最初から決めていました。
脚本を書き終えた段階で、一番の要となる主役の女性のミチを誰にお願いしようかと考えたとき、どんどん追い詰められていく主人公なので、これを観た人がかわいそうだとか惨めだと思うような人ではない主人公にしたかったんです。どんな状況になっても、どこか凛とした強さがあって、人間的な美しさがある主人公であってほしいと思って。そうすると観ている人も、この人に死んでほしくないとか、自然に感情移入できるんじゃないかなと思っていました。
そうした主人公にイメージがぴったり合うのは倍賞千恵子さんだと真っ先に思い浮かんで、ご連絡させていただきました。すると、まず監督と会ってから決めたいと言われたので、会う時間を作っていただき、私がどうしてこの映画を作りたいか、どういう主人公なのか、といったお話をさせていただきました。
――本作は、高齢の方が自ら死を選ぶような物語なので、それをすんなり受けてくださったのだろうかと気になっていました。
このコンセプト自体に拒否感を示されるかもしれませんし、無名の新人監督の小さな作品に、倍賞さんのような国民的大女優の方が出てくださるんだろうかと不安ではありました。でも幸い、この作品の趣旨をご理解くださいました。「プラン75」のコンセプト自体はものすごく酷い話だけれども、最後のミチの選択が、このラストがあるから出演を決めたのだとおっしゃっていました。
短編と長編の物語について
――「プラン75」という架空の制度も含め、そもそもこんな物語を考えた経緯を教えてください。
ここ20年くらいの間に、日本で自己責任という言葉がすごく聞かれるようになりました。助けを求めたくても求めづらい雰囲気があり、人に迷惑をかけてはいけないという意識が強く、「迷惑をかけた」とされる人がバッシングを受けるような社会の風潮が、どんどん強くなっているなと。政治家や著名人が差別的な発言をしたり、生活保護のバッシングがあったり、社会の不寛容さに対する憤りを感じていました。

そんな中で、2016年の夏に相模原の障がい者施設の事件が起こり、ものすごい衝撃を受けたんです。人の命を生産性で語るようなことは事件以前からありましたが、あの事件はそういう世の中で起こるべくして起こったような気がして、ものすごい危機感を覚えました。このまま社会が人の命を軽視する方向に進んでいけば、「プラン75」のようなシステムが生まれ得るのではないかと感じ、今これを映画にしたいと思ったんです。
――長編の冒頭には、まさしくあの事件を想起させる場面がありました。短編では、少子高齢化で高齢者の比率が上がる中で人減らしをするのだな、としか思いませんでしたが、長編で冒頭のシーンが入ると、だいぶ印象が変わりました。でも、そもそもそちらが出発点だったのでしょうか。
冒頭のシーンを入れるか否かはぎりぎりまで迷いました。まだ記憶に新しい事件なので、心を乱される観客が多くいるのではないかと大きな懸念がありました。でも、この映画を作ろうと思った大きなきっかけになった事件であり、「プラン75」の根底にある思想は、冒頭の事件の犯人の主張と相通じているということを表現するためにも必要なシーンと判断し、最終的に入れることに決めました。
――短編では、高齢者自身が「プラン75」の制度利用を選択する理由は明確に描かれていませんでしたが、長編では比較的健康な高齢者が雇用機会や金銭的な問題を理由に制度を利用する姿が描かれていました。どちらかといえば、健康に問題を抱える人のほうがこの制度を利用しそうに私は思ったのですが、高齢者の背景事情をあのように設定した理由を教えてください。
もし、病気が治らなくて余命がわずかだからこの制度を選ぶという人の物語にしたら、まあそうだよね、と観ている多くの人が納得すると思います。身体が動かなくなったら死にたくなるものだろう、と容易に想像する人が多いからです。それでは映画を観る人に新たな視点や気づきとか驚きみたいなものが生まれないだろうと思っていたので、それは最初から描くつもりがなかったんです。
こういう制度が世の中に存在するがゆえに、その選択を取らざるを得なくなってしまう様々な状況の人々が存在するということを、観た人に感じてほしいと思いました。これは安楽死の是非を問う映画ではありません。もっと大きな目でこの社会を見たとき、こういったシステムを国が作ってしまうことの問題を描きたかったんです。
――「プラン75」の広報活動が妨害される場面で、短編では妨害する人の姿がはっきり描かれていましたが、長編では妨害する人の姿は明確に描かれていませんでした。長編では、なぜそのようにされたのでしょうか。
磯村勇斗さん演じる市役所で働くヒロムは、最初まったく悪気がなく、「プラン75」のシステム側で働く人間でした。でも叔父と出会い、だんだんと自分がやっていることの先で相手がその後どういう道をたどるのかを意識し始め、自分が組み込まれている仕事やシステムの実態に徐々に気づいていきます。
あの液体を投げつけられるシーンは物語の終盤で、彼がすでに罪悪感のようなものを感じ始めています。「プラン75」に抗議する何者かが彼に実際に投げつけているのかもしれないし、彼がそういう夢を見たのかもしれない。彼が罪悪感を持ち始めたことで、誰かに責められているような彼の潜在意識の現れかもしれない。もっと大きなものから、断罪されているような意識が生み出した彼の妄想かもしれない。そういうことを、どちらにも取れるように表現したくて、長編ではあえて投げつけた人を映しませんでした。
投げつけられるものは、短編では卵だったのを長編では赤いトマトジュースにしました。トマトジュースは、飛沫が彼にかかるところが、冒頭の事件で返り血を浴びている犯人に通じています。「プラン75」の制度と冒頭の事件とで、やっていることは変わらないということを映像で表現したかったのです。
長編映画『PLAN 75』の国内外での上映について
――国内外での上映で、長編はカンヌでカメラドール特別表彰に輝き、今回トロントにも出品されました。長編デビュー作にもかかわらず世界的に評価されているのがすごいことだと思います。この現状に対しては、今どんな心境でしょうか。
完成までにすごく時間がかかったので、焦りがありました。その間にコロナもあって長編制作はどんどん延び、なかなかお金が集まらず、いつ作れるんだろうと焦りましたが、遠回りして時間をかけた分、脚本はどんどん良くなりました。その間に出会えた人もいましたし、結果的に回り道をしてよかったなと思っています。待って長くコツコツやった分だけ、ご褒美が大きかったのかなと。関わってくれた人は沢山いるので、その人たちに対する恩返しになったことがすごく良かったなと思っています。

――カンヌは今年の話ですが、制作は5年以上前からの話ですよね。短編から長編化し、国内外での上映へと広がっていく過程で、取材が増えたり舞台挨拶に呼ばれたりと最近になって状況が加速度的に変わってきているのではないでしょうか。
やはりカンヌに行ったことと賞をいただいたことで、取材をものすごく受けるようになって、最初は大変でした。今はちょっと落ち着いてきたんですけど。
――今回の取材日程を取っていただくときも、大変お忙しくされていて、こんな状況で次の作品を作れるのだろうかと少し思っていました。
長編は5月に完成したばかりなんですよ。カンヌの数日前とか一週間前とか。ついこの間完成したような気持ちなので、もう次回作を考えているんでしょ、とよく言われますが、いやいや最初の1本が終わったばかりだよ、と思っています(笑)。
――カンヌへの出品は、完成する見込みの段階でエントリーされたのでしょうか。
そうですね。音とかは全然できてない段階で、編集がかろうじて形になった段階のものを観てもらっていました。
――カンヌで上映されて観客の反応があり、その後も国内での舞台挨拶などで、いろんな声を受けたのではないかなと思います。それで感じたことや気づかされたことなど、あれば教えていただけますか。
カンヌでフランスのメディアから取材を受けたときによく言われたのが、もしこういうシステムがフランスで導入されるとなったら、ものすごい反対運動が起きて、デモもするだろうし、大変なことになると思うけれども、この映画の中で描かれている日本人は、すんなりこれを受け入れているように見える、ということでした。そこがすごく不思議に見え、かつ、とても日本人らしく見えた、という感想が結構多かったですね。
――確かに日本だと、仕方ないと諦めながら受け入れそうな気がしますね。そこまで自分の力では変えられないし、みたいな。
そうなんですよね。従ってしまうというか、諦めみたいな。それがこの映画で描きたかったもののひとつでもあります。日本全体を覆っている諦めや従順さというか。自分の頭で考えることをやめ、決められたことには従いがちなところがあるんじゃないかと。それは今に限らず、昔から日本人の特性としてあるような気がしていて、すごく危険だなと思います。あえてそう描写したので、そういうところも結構伝わっているなと思いました。
――日本人のそういうところが、ちゃんと海外で受け止められているということですね。そのあたりの日本国内での反応はどうでしたか。
その点を特にということはないけれども、本当にリアルで、あり得そうという感想をもらいました。こういうシステムをとても耳触りの良い言葉で打ち出して、例えばコマーシャルだったり職員が説明する言葉だったりで、とても便利でこんなサービスがあって、と良いことしか言いません。でもそれは言葉の言い換えで、本質的なことは、「あなた死んでもいいですよ、死んでください」ということなのに、それを耳触りの良い言葉に言い換えていることに対して、すごく気味の悪さを感じます。現実社会でも、日本でそんなことがあると感じている人が多いんじゃないかなと思います。そういう点でもすごくリアルだったという感想をもらいました。
映画監督を目指したきっかけ、アメリカへの大学進学、自身が影響を受けたものについて
――映画監督を目指したきっかけと、これまでに影響を受けてきたものを教えてください。
中学生くらいから映画が作りたいと思っていて、アメリカの大学の映画学科に入りました。でも、そのときはまだ英語ができなくて。映画はみんなで作らないといけないのに、コミュニケーションを取るのにこの英語力じゃ映画学科ではやっていけないと思って、すぐに専攻を写真に変えたんです。それから大学では写真をやりながら、でも映画がずっとやりたかったのでビデオカメラを自分で買って、ビデオアートのような作品を作っていました。
大学を卒業してから日本で助監督になるか、日本の映画学校に通うことを考えていた矢先に子どもを授かり、その後出産を経て日本へ帰国し、仕事を始めました。映画をやっていくと思っていたのに、急に人生の計画を変えないといけなくなり、10年ほどのブランク期間は悶々と過ごしました。
でもずっと映画を作りたくて、会社に勤めながら夜間の映画学校に1年間通うことにしました。そこで撮った卒業制作の短編がカンヌ国際映画祭の学生部門に入選し、ぴあフィルムフェスティバル(PFF)のグランプリに選ばれたことをきっかけに映画への道が少しずつ開けていきました。『十年 Ten Years Japan』に声をかけてくれた水野プロデューサーとも、最初のカンヌで知り合いました。

――大学で映画の勉強をしよう、といきなりアメリカに行ったんですよね。日本で大学受験して、みんながたどりそうな一般的なコースから、高校卒業の時点でいきなりポンと外れたわけですよね。そのときは、映画を勉強するならアメリカだな、という感じだったのでしょうか。
それもありましたが、高校で大学受験の勉強を始めたとき、日本の受験システムに引っかかりを覚えてしまって。当時、大学は入るのが難しくて、入った後はみんな勉強しないで遊ぶという印象が強かったんです。今の大学生はもっと真面目に授業に出ていると思いますけど、当時はそんなイメージがありました。こんなに受験勉強で労力と時間をかけて、難しい英文法を勉強しても、英語を話せるようにならないような教育システムはおかしい、と単純に疑問を持ってしまいました。
受験してどこかの大学に入って、4年後には就職活動で人と競争してどこかの会社に就職して、という決まりきった未来が見えてしまった気がして嫌だったんです。なので、もしアメリカに行けば、まったく自分が想像できない展開が待っているんじゃないかと期待したというか。
それまでまったく海外留学に興味がなく、むしろ怖いと思っていたくらいなんです。でも受験に対する疑問をきっかけに、入学後にすごく勉強して卒業するイメージがあったアメリカの大学のほうが、ずっと理にかなっているじゃないかと思って。1年くらい短期留学してもたぶん英語をしゃべれるようにならないけど、4年大学に行けばなんとかなるんじゃないか、とすごく単純な考えでした。
――中学生くらいから、映画を作りたいと思っていたんですよね。
そうですね。作りたいとは思っていたんですけど、子どもの頃は、監督が何をするのかわからなかったんです。どういう仕事かわからないし、映像が好きだから撮影カメラマンになりたいような気もして。それで「カメラマンの仕事」みたいな本を買って読んだりしていました。監督が何をするかよくわからなかったけど、映画を作りたいから、監督か撮影カメラマンか編集の仕事がやりたいなと、漠然と思っていました。

――こんな映画を撮ってみたいとか、こんな映画が好きとか、ありますか。
中高生の頃は、日本だと相米慎二監督だとか、あとは、クシシュトフ・キェシロフスキー監督とかが好きでしたね。ミニシアターでやるようなヨーロッパ映画を観に行ったりして。なんかよくわからないけど、惹かれるなと。あとはレンタルビデオができていたので、VHSを借りて観たりしていました。
――わりと昔からずっと映画を作るほうに興味が向いていたんですね。日本の映画界で、出産を経て映画を作ろうと思うと、なかなか大変だと思いますが、そこは最初にアメリカの大学に行って向こうでの技術があったからやれている部分があるのでしょうか。
全然ないですね。行き当たりばったりで。アメリカで映画を学んだわけでもないですし。映画のことは全然勉強していないし、自分で撮っていたのもビデオアートみたいな感じで独りで撮っていたので、仲間もいなかったですし。だから、日本で小さな映画学校に行ったときに初めて映画作りを仲間とやったんです。それがすごく楽しくて。
それまでは、なかなか一歩が踏み出せなかったんです。子どもがいるからとか、仕事があるからとか、できない言い訳ばかりしていたのは、どこかで一歩踏み出すのが怖かったのだと思います。こんなに映画が好きでやりたいと思っていたけど、映画を作り始めて才能がないことに気づいたら嫌だなとか、意外と好きじゃないかもと思ったらどうしようとか、失敗したらどうしようとか。かなりぐずぐずしていました。でもいざ始めたら、ものすごく楽しくて。もうこれはプロにならなくていいから、映画を一緒に作る友達が3、4人いれば自主映画は作れるし、趣味で1年に1本撮って歳を取っていけばいいや、くらいの境地になったんです。でもその卒業制作が、いろいろと幸運に恵まれ、その流れに乗っかっていった感じです。
――そこに乗っかって、今ここまで来たわけですよね。その中で、最初の楽しさみたいなものは、変わりないですか。
変わらないですね。すべてのフェーズで、映画を作るのって大変だけど、なんて面白いんだろう、と思います。面白いし、自分ひとりで作るわけじゃないから、それを一緒に作る人と共有しながら感動したりするのも、すごいなと。作る過程でもこんなに心が動いて感動するもので、できた映画を観たときに心を動かされるお客さんもいて、それってすごいことです。うまく言えないですけど、世界中にこれだけ映画にとらわれてしまう人が多いだけあるなと思います。
今後の映画制作について
――今は1作目が完成したばかりで次回作はまだ、とおっしゃっていましたが、今のお話を聞いていると、次も必ず何かを作るんだろうなと思いました。
それはそうですね、はい。作ると思います。まだ具体的には、ふわっとしたものしかないんです。ただ、1本目が決してわかりやすい映画ではなく、ストーリーもそんなに起伏があるわけでもなかったので、そういう映画でも観てくれる人がいるんだろうかと少し不安があったんです。でもお客さんの反応を見たらそんなことはなく、ちゃんと伝わっているのが分かりました。自分がやりたいことや好きな映画を作っていて大丈夫だと確信できたので、今後も自分が観たい映画を作るんだろうな、作っていくのかな、と思います。
――自分が観たい、作りたいもので企画を作って、それに出資してくれる人を探して、という感じでしょうか。日本でオリジナルな企画を通すのは大変だと思いますが、カンヌでの受賞もあるので難しくはないのでしょうか。
今回いろんな幸運が重なって『PLAN 75』が興行的にも成功したので、2本目は1本目に比べるとハードルは下がるんじゃないかなと思います。でも3本目以降はわからないですね。そこで大コケしたらまた戻ると思いますし。
――最後にトロントの読者にメッセージをお願いします。
トロント国際映画祭では遅い時間の上映だったにもかかわらず、満席に近いほどたくさんの方が来てくださり、上映後にとても熱心に質問してくださったのが印象的でした。北米での配給も決まったので、トロントにお住まいの皆様にもぜひ観ていただきたいなと思います。
米ニューヨークの美術大学School of Visual Artsで写真を専攻。短編『ナイアガラ』が2014年カンヌ国際映画祭シネフォンダシオン部門入選、ぴあフィルムフェスティバル(PFF)グランプリ受賞。短編オムニバス映画『十年 Ten Years Japan』(2018)の一編を長編化した『PLAN 75』で商業映画デビューし、カンヌ国際映画祭カメラドール特別表彰を授与された。
『PLAN 75』
75歳以上で自ら死を選択できる制度「プラン75」が整備された近未来の日本。貧困や健康の問題を抱える高齢世代は制度の利用を検討し、雇用に窮する若年世代は悩みつつも制度を支える側に回る。
監督・脚本:早川千絵
主演:倍賞千恵子、磯村勇斗、たかお鷹、河合優実、ステファニー・アリアン、大方緋紗子、串田和美
©2022「PLAM 75」製作委員会/Urban Factory/Fusee