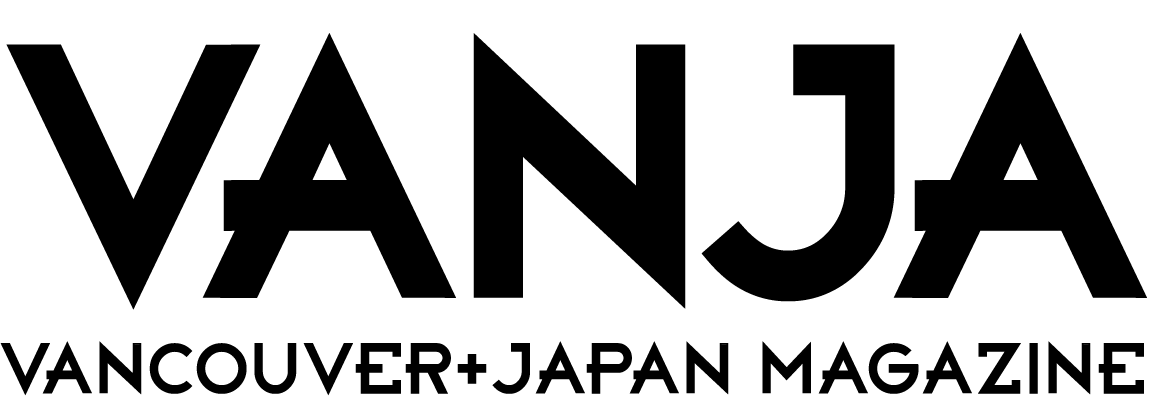“在留資格が得られないことで未来が見えない、そんな人生選択の過程にいる10代の物語”

カナダ初の日本映画専門の配給会社Momo Films Inc.が今年7月に設立され、その配給第1作目が『My Small Land』である。本作は2022年のベルリン国際映画祭でアムネスティ国際映画賞のスペシャルメンションに輝き、日本でもロングランとなった。本作が長編映画デビューながら大きな注目を集める川和田恵真監督に、お話を伺った。
日本で難民申請をしながら暮らすクルド人を取り上げた理由
――日本で難民申請をしながら暮らすクルド人家族を描くこの作品の企画は、どのように始まったのでしょうか。
7年ほど前まで、クルドの存在自体を知らなかったんです。その頃、イスラム国と戦っている女性兵士の写真を見て、クルド人の存在を知りました。そのとき、どうして自分や家族の居場所を守るために自分たちで戦っているんだろう、と疑問を抱き、興味を持つようになりました。調べるうち、日本にも2000人ほどが暮らしていること、難民申請が認められず大変苦しい状況にあることを初めて知りました。そこから、どうしてそうなったのか、もっと知りたいと思って彼らに会いに行ったのが始まりです。
いろんな家庭を訪問する中で、これをドキュメンタリーとして伝えるか、フィクションとして伝えるかと考えたとき、客観的な伝え方ではなく自分事として見られる物語を作りたいと思って、フィクション映画の企画を立てました。
――日本で難民の問題はたくさんあると思います。その中で、なぜクルド人を取り上げたのでしょうか。
当時、難民申請者の中でも、クルド人は本当に一人も認定されたことがなかったんです。難民申請者はそれぞれに状況が違うと思いますが、他の民族だとそれぞれのケースで見てもらえているように思えました。ところがクルド人だけは、その裏にある国との友好関係といったところで、あの国から来たクルド人は難民認定できないという見方をされているように思いました。ただ、つい最近のことですが、ようやくクルド人が難民認定されたので、その状況も変わる兆しがあるのかなと思います。
――そのニュースを見たときには、この映画の影響があるのかなと少し思いました。
自分ではなかなかそこまで思えないですけど、でも本当に、良い兆しを嬉しく思います。
クルド人って「世界最大の少数民族」という不思議な言い方をされています。最大の少数民族なのに自分たちが安心して暮らせる居場所を持てず、居住区はあるけれど、そこさえも攻撃されて安心できる場所ではありません。世界各地に逃れて散らばって暮らしていて、根っこの強さみたいなものを感じる民族です。でも同時に、様々な大国に翻弄されてきた歴史があり、いざというときに守ってもらえず、国って一体何だろうという強い問いかけを感じました。それは、自分がミックスルーツで、自分の国や居場所って何だろうという幼い頃からの自分にとっての大事な問いとも結びつくものでした。
また、私がクルド人に初めて会ったとき、あなたはクルド人ですかと聞かれたんです。それまで日本で、外国人ですかと聞かれることはありましたが、ある民族から自分たちと同じじゃないかと思ってもらうことはなく、自分がクルド人からクルド人かと思われたことが、自分にとって驚く経験でした。いろんな人に会って、あなたはクルド人だと言ってもらう中で、すごく心の扉が開かれているんだなと感じ、クルド人が自分にとって大事な存在になっていきました。
――最初、クルド人のルーツを持つ監督だからこんな作品を撮ったのかなと思いました。でも川和田監督自身はそうではないですよね。監督がミックスルーツの物語を作るところは理解できるものの、なぜクルド人を選んだのかなと不思議でした。
基本的に、自分自身や自分と同じものを描くことへの関心より、もっと知りたいことへの関心がモチベーションになっていると思います。自己表現で自分のことをそのまま描くことにはあまり関心がなく、どちらかというと映画作りを通して知るとか出会うことに興味がありました。
社会問題と青春映画の両輪を持つ物語ができるまで

――本作は、難民問題の厳しい現実を描くと同時に、少女を中心とした青春映画としても見ごたえがあり、そのバランスが素晴らしいと思いました。この物語はどのように作り上げていったのでしょうか。
取材をする中で特に自分の心に引っかかったのが、若い女性達がどこを目指せばいいのかが見えないことでした。男性は解体業に就いている人が多くいたものの、女性は誰も職に就けておらず、幼い頃に来日して日本で長く育った子も増える中、在留資格が得られないことで未来が見えず、その中で頑張れる子もいればドロップアウトしてしまう子もいました。そんな姿を見て、これは人生選択の過程にいる10代の子たちの物語にしたいと思いました。話を聞きながら実情をベースに物語を立てていく中、多くの子が抱える悩みとして、自分がクルド人であることを周囲に言えていないことがありました。一方で父親や家族には、子供にクルド人らしくあってほしいという望みが強くあり、板挟みになっている。私自身ミックスルーツということもあって、そこにすごく心が動き、大事に物語を作っていきたいと思いました。
――外国で育って来日した親世代と日本で生まれ育った子供たちの、バックグラウンドや思いの違いも、丁寧に描かれていると感じました。特に父親と少女と妹弟との言語の違いに現実味が感じられましたが、これは取材から浮かび上がってきたのか、それともご自身の経験が関係しているのでしょうか。
どちらもあります。取材していく中で、親と子が同じ言語で話せない家族や、誰かを挟まなければ会話ができない状況を見て、世代間で文化にギャップを抱える家庭生活の影響を感じました。私も、父親の一番の母語である言葉を自分自身が話せず、自分にとっての母語は父親が一番わかる言葉ではない状況にあり、本当に伝えたいことをどう伝えるか、コミュニケーションが難しい時期がありました。そういうところも影響していますし、自分が会った人の中にも様々なグラデーションを感じたので、それを姉弟に反映させて描きました。
――この姉弟もお父さんも、本物の家族を起用されていて驚きました。キャスティングはどのように決まったのでしょうか。また、最初に家族のキャスティングがあって、今のお話のようなグラデーションが決まったのか、それとも物語が先にあって、そこに3人の子供たちが当てはまったのか、なども教えていただけますか。
当初、難民申請中の当事者の出演を考えていましたが、企画を進める中で、いつどうなるかわからない不安の中、メッセージ性の強い映画に出演してもらうことの危うさに自分自身気づいていきました。そこで方針を変え、異なるバックグラウンドでも、この物語を共有する部分を持つ人に出演してもらおうと考え、あらゆるルーツを持つ人に集まってもらってオーディションを始めました。それで来てくれたのが嵐莉菜さんでした。5か国のミックスルーツを持つ彼女と話したとき、自分がどこを母国と言っていいのかわからない、母国を持っていないみたいだ、と言っていたんです。そのとき、この物語やクルドの根底にあるものに、どこか通ずるものを持っているんじゃないかと感じて、彼女と一緒であれば物語に向かっていけると思いました。
そこから家族のオーディションを開始したとき、本当の家族にご応募いただいて、出演が決まっていったんです。お父さん候補は他にもたくさんいましたが、実際の映画のシーンを演じてもらったとき、嵐莉菜さんが一番引き出された相手が実のお父さんでした。そこから実のお父さんにお願いする流れになり、妹弟役もそれぞれオーディションで決まりました。
そのとき、すでに脚本はある程度できていましたが、当時はまだ姉妹間のグラデーションを考えていました。そこから設定自体を変え、妹は自ら日本語しかしゃべらず、一番小さな弟は、お父さんがまだ希望を捨てきれず言語を教えようとしているけれど十分習得できておらず、ただ日本語もすごく習得できているわけではなく、一番何人かわからなくなっている、そんな存在にしようと思いました。そういう形で、言語の描き分けを考えました。
――キャスティングを決めながら脚本にも反映していったのでしょうか。
そうですね。かなり内容は変わりました。キャスティングが決まってから、キャラクター自体も本人たちの持っているものを生かして変えましたね。今回は特に、本当にお芝居の経験がないキャストだったので、それぞれが本来持っている魅力を借りて作らせてもらいました。
――本作では、少女の家族との関係の他に、男の子との二人の関係が軸になっていて、青春映画としても素晴らしく、二人の関係はキャスティングによる効果が大きいのではと思いました。オーディションで選ばれたのでしょうか。また、青春映画としてのフィクションの部分は、どんな風に作っていったのでしょうか。
主人公の嵐莉菜さんもそうですし、聡太役を演じてくれた奥平大兼君もオーディションに来てくれて、選びました。
奥平大兼君がオーディションに来てくれた当時、17歳くらいだったと思いますが、まだ青年になり切っていない感じが残っている男の子で、純真なところがありました。だからこそ、オーディションで女性と話す場面を見せてもらったときに初々しい会話ができていて、すごく魅力的だなと思いました。特に役者をやっている男の子だと、17歳くらいになると慣れているなと思うことも多く、それもひとつの良さだと思うんですけど、奥平君はそうじゃない姿を見せてくれました。自分の言葉で話してくれるのが魅力的で、フラットに物事を見ている感じや、本人が知りたいと思っているからこそ真っすぐに質問する感じなど、等身大の素朴さや率直さを彼本人から受け取って、当て書きしていきました。
あと、聡太がどんなことに興味がある子かというキャラクターづけができていなかったところに、奥平君は絵が好きで美術に興味があると言っていたことから、スプレーで絵を描くシーンや橋の上で手の跡をつけるといった大事なシーンも補完できました。本当にキャスティングによってできていった映画だなと強く思います。
――本作では、ごく当たり前に外国人家族が暮らしている光景が多かったと思います。食事のシーンとか他愛ない会話とか。そういうところは意識的に取り入れていたのでしょうか。
日本で生活して日本に慣れている部分もあれば、自分たちが暮らしてきた慣習もそのまま大事に生きている部分もあって、それって大切にしたいことだなと思って。郷に入れば郷に従えというところもあるんですけど、人がそのまま望むように生きられること、違いを認め合うことも、これから共生していく社会には大事なことだと思うので、そういうところは映画で表現できたらいいなと思っています。
――監督ご自身は、日本で生まれ育って、文化的には日本の風習の中で育ってきたのでしょうか。
そうですね。ただ、父親は日本にまるっきり同化しているわけではなく、自分の食べたいものを作って食べたりしていて、他の日本家庭の食卓には出ないものを食べていました。逆に日本家庭だと当たり前にあるものがなかったり。例えば仏壇とか。そういう曖昧な、ミックスな感じの中で生きてきました。
――学校の同級生とのシーンなど、日本の学校でのちょっとした疎外感や、その中での些細な気遣いなど、とても細やかに描かれているなと思いました。それで、監督のバックグラウンドは一体どうなっているのかと気になっていました。
自分の感覚もありながら、自分が目にしたクルド人の子たちの間で普通に根づいているしゃべり方なども入れました。一方で、本当に十人十色で、言葉がしゃべれる子もいれば、しゃべれない子もいます。特に今回の主人公はその狭間にいて、どちらの言葉もしゃべれるけれど、どちらかと言えば読み書きは日本語で、でもそんな状況だからこそコミュニティの中にいる他のクルド人の生活に必要な雑務を請け負う立場になってしまう。それは現実にあって、でも自分の経験にはないことでしたが、彼らの姿を見て描きたいと思ったことでした。
――取材をされて、いろんなグラデーションがあった中から、あの家族に落ち着いたのでしょうか。
そうですね。特に来日した年数などから設定を考えていく中で、自分の目に魅力的に映った取材対象の方をベースにさせてもらいました。
メインモチーフの石と、タイトルの絵柄が意味するところ

――この映画では、石が何度も出てきました。サーリャと聡太の関係でも、お父さんと弟との関係でも、最後のシーンでも、石がすごく印象的だなと思いました。どんな思いで取り上げていたのでしょうか。
取材する中で、日本に持ってくることができた家族写真を見せてもらっていたとき、クルドの土地に石がたくさんあるのが印象的だったんです。これは、ぼんやりとした抽象的な感覚になるのですが、どこにでもある石を見て、違うのは場所だけだなとか。どこにあっても石は石だけれども、持つ人によってどこの石か違って、それは考え方次第だなとか。そんなことを思いながら想像する中で、ここで学校に通うときには必ず石が落ちているだろうし、お父さんを思い出すんじゃないかな、などと発想してシーンにつなげていきました。
――冒頭で『My Small Land』のタイトルが出るところでは、タイトルを囲む雲のような線の絵柄が出ますよね。あれは何だろうと思っていて、もしかすると埼玉県の形だろうかと思いました。そうでしょうか。
そうですね。埼玉の形でもあり、クルドの居住区の形にも少し似ているんですよ。あと、この映画でメインモチーフになる石もイメージしました。サーリャやお父さんが、それぞれ、くっきりとではないけれど、おぼろげにでも自分が暮らしている場所のイメージを描くような、そういうイメージで作ってほしいと伝えて、作ってもらいました。
――最初、雲みたいな形だなと私はのんきに見ていましたが、これが埼玉県だとしたら、あの線画は、そこから自由に出られなくなる一家の切実な壁に見えてきました。そこに、当事者と、無関係な外の世界の人々との温度差が感じられるようで、すごいタイトルデザインだなと思いましたが、今のお話を聞いて、もっと多くの意味が込められていたんだなと驚きました。
埼玉を知らない人から見たら、本当になんだろう、っていう「?」から始まると思います。クルド人の居住区で暮らしている人から見ると、少し居住区に似ているかな?という感じでしょうか。線を引くこと自体にこの映画のメッセージもあるので、それぞれ観客のみなさんなりに、観て何かを感じてもらえたら嬉しく思います。
若くして初監督の企画を実現するまでの道のりと、今後のこと
――今、日本の映画界で若い人がオリジナルの脚本で企画を通して映画を作るのは、かなり難しいと思います。今回の企画が実現するまでは、どうだったのでしょうか。
そうですね。今回のように外国人が主人公で、主演するのは映画が初出演で有名な人でもなく、さらに社会的なテーマを含むとなると、難しいところはありました。でも、これを近くのシネコンで観てもらえるような映画にするからこそ意味があると私は思っていたので、そこは変えずに企画を出して内容を考えていきました。ただ、企画のかなり早い段階で釜山国際映画祭のAsian Project Market (APM)に持っていき、そこで海外からの反響を得たことで、この映画を作ろうという波に乗れたところがあります。私よりひとつ年下のプロデューサーが頑張って、いろんな人を巻き込んで進めていってくれました。
――釜山国際映画祭のAPMで評価され、映像化される前の企画段階で支援を受けられるような状態になったのでしょうか。
そうなんです。企画賞みたいな形で、その賞自体が制作の直接的な後押しになったというより、それが得られたことによって作品に見込みがあるというか、手ごたえみたいなものを得ることができたのが大きかったと思います。
――では、そこから出資を募るのも楽になったのでしょうか。
とはいえ大変だったと思いますが、その賞があるのとないのとでは違ったと思います。まったくの新人の知らない作品ではなく、こんな賞をもらった作品なんだと少しでも関心を増してもらえたと思います。
――その後ベルリン国際映画祭でも受賞され、日本国内の映画館で長らく上映されて、今こうしてカナダでも劇場公開されます。デビュー作としてはすごいことだと思いますが、この現状に対して、今どんなお気持ちでしょうか。
作品が形になった後からは、本当に観ていただいた方の力だなと思っています。いろんな感想や応援をいただいたことで上映が長く続けられ、こうしてカナダでも上映していただけるのは、観ていただいた方の後押しだと思うので、自分の手を離れたところで大きくなっていく子供のように思えます。それぞれに、どんな感情でもいいので受け止めてもらえたら嬉しいなと思います。
――今回、長編映画はデビュー作に当たりますが、取材し、脚本をキャスティングに合わせて書き直しながら進めていく手法は、これまでに何か経験があったのでしょうか。または先輩方から教わったとか。
特にないですが、助手でついていた是枝裕和監督の姿を見ていたことは大きいと思います。取材で得たことをすぐに脚本に活かして脚本が変わり続ける、撮影に至っても変わり続ける、ということを見ていたので、それに対してあまり抵抗がなかったですね。その時々の作品で是枝さんのやり方も違うと思いますけど、今回私はこのようなやり方で挑戦してみようと思いました。
――是枝監督からは、若いうちにしか撮れないものがあるから20代のうちに早く撮りなさいと言われるとか、西川美和監督のインタビューか何かで見たことがあります。川和田監督のご年齢を考えると、そんなことも言われたのでしょうか。
そうですね。是枝さんはそういうことを言いますね(笑)。撮影時、私はまだどうにか20代で、何か20代で撮れるようにと言われていました。たぶんご自身の初監督が30代になってからだったこともあると思うんですけど、できるだけ早い時期に作品を作ることを是枝さんは応援してくれますね。今はいろんな監督がいますし、人生の経験があったからこそ初めて撮れる作品もあると思うので、本当に年齢がすべてかという疑問もあるんですけど、自分は幸福にも今の年齢で初めて撮りたいと思った作品を撮らせてもらえたので、すごく良かったなと思います。
――是枝監督の場合、子役に対しては先に脚本を渡さず現場で演技をつけていくといった話を聞きますが、今回どうだったのでしょうか。
脚本を渡して練習してもらう感じではありませんでした。ただ、是枝さんと違うのは、ワークショップを数ヶ月前から行って、その中で内容をある程度伝えていったことです。今回、一番下のロビン役だけその方法を採ったのですが、一度やったことをよく覚えていて、現場で違うことを言うと、変わったじゃないかと指摘されるんです。変えたんだよと説明するんですが、数ヶ月前にやったことをとてもよく覚えていることに驚きました。
――ワークショップをやっていると、本物の家族だけど普段とは違う家族を演じる難しさみたいなものは、簡単に乗り越えられたのでしょうか。
やはりバックグラウンドが違うことは大きくて、難民申請が認められていないクルド人の家族だという状況を理解してもらうために、当事者の方に実際に会ったり、ご自宅に伺わせてもらったりしました。そういう時間を持つ中で、本人たちが気になったところをピックアップしながら背景について理解を深めてもらいました。物語を演じる点では、かなり各キャラクターに合わせた脚本にしていたので、無理をしているところは少なかったかなと思います。
――登場人物に役者自身のキャラクターを反映しているから、ということでしょうか。
はい。かなり近いです。だから、父と娘が最後に向き合う入国管理局での場面では涙が止まらなくなるなど、本当のお父さんがそういう状況になっているからこそ感情がより強く出ていました。主人公の嵐さんにとっては、やりやすくもあり、やりにくくもあったんじゃないかと思いますが、こちらとしてはその状況をそのまま撮らせてもらいました。
――これほど素晴らしい長編デビュー作だったら、次回作はどうなるのかと気になっています。今後の企画や、これから作っていきたいものがあれば教えていただけますか。
そのときどきの自分が社会に対して抱いている疑問や違和感を発端に作っていけたらいいなと思っています。ただ、こういう入国管理局の話や社会問題にこだわるより、いろんな海外ルーツの人やマイノリティの人がたくさん暮らしていて、そういう人が当たり前に登場してくる作品を作りたいと思っています。海外の作品を観ていると、ごく当たり前に混じり合って出てきますが、なかなか日本ではまだナチュラルに出てくることがないなと思うので、それは大切にできたらいいなと思います。
海外での反応について

――海外の映画祭でもたくさん上映されていますが、海外でどんな風に受け止められているのでしょうか。海外の反応を受けて、何か感じることはありましたか。
私が直接行くことができたのはベルリン国際映画祭だけですが、ベルリンでは、日本の物語ではあるけれど自分たちと何も変わらない物語であるように観てもらえたと感じました。今、こういうテーマを扱った映画は多いと思いますが、難民になった先、何年も暮らしたその先を描いたものとして、ドイツや他の国で実際に暮らしている方々に共感してもらえるところがあったかなと思います。
――ミックスルーツの監督が日本で暮らす中で、こういう思いをされているのかなと私は映画本編から感じるところがありました。そういう点で、監督ご自身に対する海外での反応はありましたか。
私がミックスルーツだからという特別な反応はなかったと思います。むしろ日本で上映したときのほうが、そういう点について質問をもらうことがありました。海外では、どこに行っても様々なルーツを持つ人がいて、インタビュアーの方から、実は僕も移民ですとか、実はこういうルーツで同じような思いをしてきましたとか、何度もそういう言葉をもらいました。海外に行ったときのほうが、特別じゃないんだなってことを一層感じましたね。
監督を目指したきっかけや、影響を受けた作品について
――映画監督はそもそも何がきっかけで目指されたのか、いつから目指そうと思っていたのかなど、教えていただけますか。
映画やドラマは親の影響で幼い頃から大好きで、何か携わりたいという思いはありましたが、監督になるという発想はずっと持っていませんでした。高校生のとき、たまたま手に取った本がシナリオで、小説のつもりがシナリオを買ってしまったんです。そこから、これだったから関われるかも、これをやってみたい、と思ってシナリオを書くようになりました。
大学生になって、それをサークルで映画にしようと思ったとき、じゃあ誰が監督するかといったら自分がやるしかなくて。あ、自分が監督するんだ、って(笑)。だから結果的に監督にならざるを得なくて始めました。自分が監督に向いているとは思わなかったんですけど、いろんな人の力を結集してものづくりをしていく面白さだったり、それを外の人に観てもらえたときの反応の大きさだったりが忘れられなくて、やっぱりこれは自分の道にしたいなと学生時代に思って、目指すようになりました。就職試験も一応受けたもののうまくいかず、そのまま卒業してしまいました。
それからしばらく経ってから、是枝さんが助手を募集していたことがきっかけで、是枝さんの現場や他の映画の現場に行くようになり、自分の企画を考えて今回に至りました。
――監督が影響を受けてきた映画や小説などを教えてください。
映画ではケン・ローチ監督が、社会にある違和感や疑問から描いているようでありながら、あくまでも人間と人間の関係を見せていくからこそ胸に迫るところがあって、大好きな監督のひとりです。『わたしは、ダニエル・ブレイク』とか、大好きな作品です。
あと、日本映画で行定勲監督の『GO』があります。脚本が宮藤官九郎さんで、日本に暮らす在日朝鮮人の方と日本の女の子のボーダーを超えた恋の物語です。なかなか自分が在日であることを打ち明けられない様子が描かれていて、それは今回の作品を作る上でも私が参考にしたひとつでした。
トロントの読者に向けた見どころとメッセージ
――カナダ、特にトロントは移民が多く、そんな土地柄で本誌読者の日本人や日系人は、マイノリティの立場からこの作品に共感するところが多いのではと思っています。この作品で、特にこんなところを観てほしいという点はありますか。
この作品の中にはいろんなボーダーがあり、家族の中にもボーダーがあれば、人種のボーダー、物理的に越えられない線を引かれてしまうボーダーもあります。どの国にいても、きっと国ごとにいろんなボーダーがあると思うので、観ていただく方の近くでご自身に置き換えながら考えていただけたら、どこかでご自身の視点を見つけていただけたら嬉しいなと思います。
――最後に、トロントの読者にメッセージがあればお願いします。
この映画がトロントで上映されることを、心から嬉しく思います。トロントも、移民や難民の方々が暮らされている街だと思うので、どのようにこの映画が観ていただけるのか、とても気になっています。ぜひ感想をお聞きできたら嬉しく思います。
日系文化会館(JCCC)
10月4日 19時〜
TIFF Bell Lightbox
11月9日 19時〜
Vancouver Cinematheque
11月4日〜11月6日 19時〜
*日時は予定ですので詳しくは各映画館のHPをご確認ください。
川和田恵真監督プロフィール
1991年、千葉県生まれ。イギリス人の父親と日本人の母親を持つ。大学在学中に制作した映画『circle』が東京学生映画祭で準グランプリを受賞。2014年に「分福」に所属し、是枝裕和監督の作品等で監督助手を務める。2018年の第23回釜山国際映画祭Asian Project Market(APM)でアルテ国際賞を受賞。本作が商業長編映画デビュー作。
『My Small Land』(原題:『マイスモールランド』)

埼玉県に暮らすクルド人の高校生サーリャは、幼い頃に一家で難民として来日して以来、日本で暮らしている。大学進学を目指してコンビニでバイトをしながら、ごく普通の高校生活を送っていたはずが、難民申請が不認定となったことで在留資格を失い、生活が一変する。
監督・脚本:川和田恵真
出演:嵐莉菜 奥平大兼 藤井隆 池脇千鶴 平泉成
©2022「マイスモールランド」製作委員会
配給: Momo Films Inc. : momofilms.com