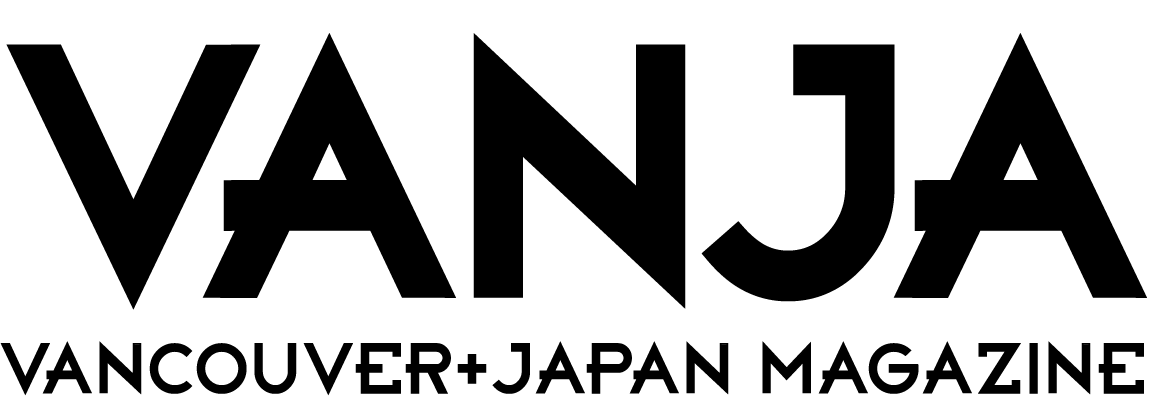河瀨監督の作品は、『萌の朱雀』(97)以来、絶え間なくトロント国際映画祭で上映されている。最新作『朝が来る』(20)は、直木賞作家の辻村深月さんの同名小説を映画化したもので、今年のカンヌ国際映画祭の公式作品にも選出された話題作。ちょうどトロント国際映画祭と同時期に開催される、なら国際映画祭を控えていた河瀨監督に、最新作の話題から映画祭への思いまでお伺いした。
今年のトロント国際映画祭への出品と日本での劇場公開について
―『朝が来る』は、カンヌ国際映画祭の公式作品に選出され、サン・セバスチャン映画祭とトロント国際映画祭で上映されます。トロントへの出品も早々に発表され、世界中からとても評価されていると感じます。現在の心境をお聞かせください。
今年の映画祭はベルリンまでは開催していましたが、4月頃から全世界的に中止もしくは延期になってしまいました。感染者を一定量に抑えられているということで、秋口の映画祭が皮切りと言ってもいいと思います。そんな中でカンヌのレーベルをいただいたと同時に、トロントにいち早く招待していただいて、カンヌの役割と世界の映画祭の役割がすごく見えてきたと思います。映画というエンターテイメントの世界が、コロナ禍においてどうしても発表の場を失ってしまう中、映画祭が連携して発表の場を設けていただけるというのは、作家にとってとてもありがたいことですね。
―これまでも監督が新作を発表されるたびにカンヌやトロントで上映されていますが、トロント国際映画祭に、他の映画祭との違いは何か感じますか。
私の映画はカンヌで最初に上映されることが多く、ヨーロッパを中心に広がっています。トロント国際映画祭は北米最大級の映画祭なので、トロントで上映されることで北米の皆さんに観ていただける機会が増え、そこから北米大陸の皆さんに観ていただけるのが、すごくいいことだと思っています。ディレクターのキャメロン(注:トロント国際映画祭の共同代表でアーティスティック・ディレクターのキャメロン・ベイリー氏)がいつも上映してくれていて、『萌の朱雀』以来ずっと呼んでいただいている記憶があります。数年前の『あん』では樹木希林さんも一緒に呼んでいただいて、とてもいい思い出ですね。
―『朝が来る』は、もともと6月公開の予定だったところが春先に公開延期となり、その後10月公開が決まりました。すでに宣伝活動も進んでいたのではないかと思いますが、公開延期でどのような影響がありましたか。
日本は3月から自粛状態になっていて、公開延期は宣伝をかけるピーク直前のギリギリのところでした。もちろんチラシやポスターは完成していて、6月5日の公開日も入れて印刷していたので、刷り直さなければいけないことにもなりました。映画館が閉鎖されてしまうと延期せざるを得ないのですが、6月5日公開の延期を判断するということは、コロナの感染者数だったり陽性率だったり、政府はどう思っているのか、映画館はどう考えているのかなど、さまざまな人たちがそれぞれの立場で決定していかなければいけないところにありました。その中で10月23日の公開が決定したということが、その時点ではやっぱり一番安心できたことでした。
あとは、エンターテイメント業界すべてだと思いますが、公開延期に伴って仕事がなくなっている状態があります。昨年1年間、構想から考えると数年にわたって作り上げた映画が、回収をする興行の段階になって、その機会を奪われてしまうということは、かけたお金が回収されないことになってしまうので、すごく打撃ですよね。そこはもう本当に私だけではなく、すべての映画関係者が頭を悩ませているところじゃないかなと思います。とはいえ、それで何もしないということではなくて、公開することで待っていてくれる皆さんの心を温めることができると思うので、トロント国際映画祭が開催すると決定したことに意味があるんじゃないかなと思います。
―トロント国際映画祭への出品が決まってから、日本の劇場公開日が決まったのでしょうか。
日本の劇場公開日が決まったのは、トロント国際映画祭への出品が決まったのと同じくらいの時期じゃないかと思います。カンヌレーベルが決まったのが6月頃で、その後トロントも決めてくださいました。日本の公開日が決まったのと、どちらが先だったかわかりませんが、トロントへの出品が決まったから劇場公開日が決まったわけではないと思います。ただ、日本の映画の興行を担う東宝系映画館のTOHOシネマズでは、東宝系の自主製作の作品から公開していくことが多い中、私たちの映画のようなインディペンデント映画の10月公開がいち早く決定したのは、少なからずカンヌやトロントの影響があったかとは思いますね。

映画『朝が来る』について
―これまで監督の作品はオリジナルが多く、原作の映画化は少ない印象がありました。今回、辻村深月さんの原作を映画化することになった経緯を教えていただけますか。
原作を読んでくれないかと言われて読み始めたとき、私自身の出自に関わるようなことも、どこかで感覚的にすごく似たようなエピソードがありました。小説を映画化するに当たって、とても映画化が難しい小説だなとも思いましたが、辻村深月さんの世界観もとても大好きだったので、映画化を決めました。
―辻村深月さんの小説は言葉で感情を緻密に描く作風で、監督の映画は映像に感情を緻密に乗せる作風という印象があります。『朝が来る』文庫版に寄せられた監督の解説では、小説をとても緻密に分析されていると感じましたが、脚本を書く際、どう映像化されるかを緻密に設計されるのでしょうか。
そうですね。私の中では完璧なまでに緻密に設計するんですけど、現場ではもっと詳細なものが加わってくるんですね。それは俳優の中に宿っている感情なんですけど、緻密に計算したストーリーの中で、それをどういうふうに加えていけば次の展開により深くリアリティを持って構築できるかということを考えます。
―以前に別のインタビューで、順撮りされていると拝見しました。これまでに撮ったところをどうつなげていくかと計算しながら、撮影していくということでしょうか。
そうですね。人の人生がコントロールできないのと同じで、俳優たちの人生もそこにあって、本当に抜き差しならない感情が宿ってくるので、自分たちで緻密に計算したからとは言えコントロールできるものではありません。順撮りによって俳優たちに偽りがなくなるので、やっぱりそれを優先させるというか、そういう現場を作っていきます。
―ただ『朝が来る』の場合、時間が過去に戻ったり、いろんな登場人物のいろんな年代の場面が交錯したりといった構成になっていました。そういうところはどのように組み立てて撮っていかれるのでしょうか。
撮影のときは、あらゆる可能性を考えて撮っているので、それをまあ素材というのであれば、あらゆる可能性が考えられるものを撮ります。そして編集の段階で、あらゆるパターンを構築していきます。
―映画の舞台について、小説では主人公の少女が暮らす町は宇都宮でしたが、映画では奈良が舞台でした。これまでも監督の作品は奈良を舞台に撮られていますが、今回、少女の暮らす町を奈良にした理由や思いを教えていただけますか。
やっぱり自分にとって地の利がとてもいいのと、その土地の持つ空気感が違う場所、特徴の違う場所、という点から奈良を選びました。小説では夫婦の住まいも都心部の武蔵小杉ですけど、映画ではあえて湾岸の辺りのタワーマンションにしました。奈良に関しては、海がない山あいの地方都市という感覚で、映画において明らかに空気感が違います。そういうことが、日本だと、ああこれは奈良だな、東京だな、湾岸だなというふうに思えて、とてもリアリティを持ちます。それだけで距離感みたいなものが出せるし、出会ったこともない風景の中で、登場人物たちがそれぞれの特徴を持って関係していくことになるので、非常にドラマチックです。

その一方で、この作品は世界中で見ていただくので、例えばカナダの皆さんは、奈良がどこにあるのか、湾岸のタワーマンションがどこにあるのか、正直わからない人もたくさんいると思います。とは言え、明らかに生活様式が違っていたり、明らかにその土地の持つ空気感が違っていたりするというのは、映画を観ていただければわかると思うので、そういう意味で奈良を選びました。
そして地の利がいいというのは、たとえば少女ひかりが暮らす場所だったり学校だったり、そういう場所は私がこれまで暮らしている場所なので、お付き合いの中から非常に撮影がしやすいというのがありました。私が暮らす場所に俳優たちが暮らすことで、よりそれがリアリティを持ってくるというのはあると思います。
―それは、撮りたい映像に合致する場所がすぐに思い浮かんでくるといったことでしょうか。
撮りたい映像が浮かんでくるのはもちろんなんですけど、撮りたい映像だけで組み合わせると、リアリティがなくなるんですよ。俳優が暮らした上でリアリティがあるということは、例えばこの道をまっすぐに行って右に曲がれば学校があるとか、それに嘘がないっていうことなんですよね。それに撮影そのものが、その街全体が映画のセットというような感覚で、俳優の皆さんに提示することができます。自転車を走らせるのはこの道とか、ここをこう走っていけば巧(たくみ)の家に行くとか。そういう映画的リアリティを、俳優たちが嘘偽りのない街の様子を体現するということが、とても重要です。
―それを体現してもらうに当たって、監督ご自身に地の利がある場所で撮影することが活きてくるということでしょうか。
そうですね。今回の映画の場合、全国6箇所で撮影しているので、それを2ヶ月で撮り切るには、日本全国を本当に行脚しているんですね。映画のクルーたちが、旅をしている。その中で、私にまったく地の利のない場所を、製作スタッフから「こういうところがいいですよ」と教えてもらって撮影するのと、少なくとも、ひかりの暮らす場所を地の利のある奈良にするのとで、その中にもリアリティが出てくるんですね。それを組み合わせることで、より日本を知っていくことになるんじゃないかと思います。
映画業界での女性の活躍や、今後の映画界について
―近年、トロント国際映画祭を主催する団体では「Share Her Journey」という女性の映画製作者を支援する取り組みを積極的に進めています。世界的にも女性の映画製作者が活躍できる環境を整えていこうという動きが見られますが、日本の映画業界の状況についてはどのように感じておられますか。
映画業界の中でそういった取り組みが行われるということは、ほとんどないと思いますね。私自身が体験していないという感じなんですけど。ただ、私は今、なら国際映画祭をやっていて、十代の子たちの映画製作ワークショップを今まさにやっているところなんですけど、12人の受講生の中で11人までが女性なんですよ。だから、本当に映画を作りたい女の子たちがすごく増えているなと思っています。
―応募者に女の子が多いということですか。
そうですね。ほとんど女の子です。なら国際映画祭のユースプログラムは、後進の女性を育てようと思って作っているわけではないんです。ただ、応募してくる方に女性がとても多いです。
―他に何か監督が後進の女性が活躍できるよう取り組まれていることはありますか。
世界的にマイノリティ(少数派)の女性の人たちが活躍できる機会を、という意味で、ユネスコさんの取り組みがあります。特に女性であることと同時にアフリカの地域で映像の活動をされている10人の作家の方々を奈良にお呼びして、「Grand Voyage with Africa」と題してアフリカ人女性監督たちがワークショップを行うものです。今年3月に実施しようとしていましたが、コロナの関係で延期になっていまして、来年の同じ時期に開催の予定です。
―最近は世界的に状況が変わりつつありますが、これまで河瀨監督以前には女性監督がすごく少なかった印象があります。苦労も多かったことと思いますが、監督にとってはどんなことが一番大変でしたか。
すべてが大変でしたね。学生時代もクラスの中に2人くらいしか女性はいませんでした。映画を製作するときにも、私の世代だと二十代で結婚をして出産をするというのが普通だったりすると、なかなか両立はできません。三十代になっても、子育てと映画監督としての仕事を一線で続けていくというのは、なかなか周りのサポートがないと難しくて。
同じ世代の男性がある意味自由に動き回っている姿を見ると、私自身はそれを積極的にやりたいとは思っていないけれども、やっぱりチャンスとしては男性のほうが、より多くのところに自由に行けるというふうに思ってきた世代ですね。私自身は子供のことがとても大切なので、地元で暮らしながら、できる範囲の中でやるという選択をしてきましたけれど。
でもそれも含めて、自分なりに工夫して、そのときそのときの最善策を取りながらここまで来ましたね。でもそれは決して簡単な道ではなくて、創意工夫で茨の道みたいなところを切り崩して歩いてきたんじゃないかと思います。やらなくてもいいことをやらなきゃいけないとか、そういうこともあったと思います。でも、往々にして物事というのは、すごく辛い部分においてできたことが自分のスキルにも変わっていくので、私はそういう体制に対して文句や不平不満を言う時間があるんだったら、自分で創意工夫をして、自分の作品を作り続けられる方法と、それに協力してくれる人を募ろうというふうにしてここまで来ました。
ただ、それは決して簡単ではないから、やっぱりなかなか女性が増えない現状があると思いますね。それを本当に仕事にして自立してやっていくには、さまざまな壁があるんじゃないかとは思います。
―そんな大変な中でも監督ご自身で脚本を書き、オリジナルな映画を1~2年に1本のペースで作り続けておられますよね。そうなると常に複数のプロジェクトを並行して実施されていると思いますが、どんなふうにうまくマネジメントされているのでしょうか。
スタッフに任せられることの振り分けを明確にするということだと思います。これは男女区別なく言えることで、女性だからこそということではないのですが、物事すべてを自分だけではできないので、本当に適材適所、それを得意とする人たちに作業を振り分けながら、自分の行きたい道を切り拓いていくような、少し俯瞰した目を持つことだと思います。自分の今立たされている現状に、とにかくやみくもに突っ走っているだけだとすごく疲れてくるし、一体何が問題点なのかということも見えなくなってきます。どんどん沼にはまっていく感じになると思うんですが、少し俯瞰して物事を見ると、問題点が浮き彫りになります。じゃあその問題点を解決するために何をすればいいのかというのは、決して自分だけが四苦八苦することではないということがわかってくるので、そういう視点でやってきました。
―今、コロナの影響で、映画製作には従来とは全く違う困難も出てきていると思います。そんな中でも映画製作を続けていくために、ご自身のことも後進のことも、どうすればうまくいくのか、何かお考えがあれば教えていただけますか。

今は私にとっては、この十年来作ってきた「なら国際映画祭」というプラットフォームです。今年、コロナ禍ではありますが、トロント国際映画祭と同じように配信などを駆使して、五十数本の映画ではあるものの、私たちも上映と配信の機会を設けています。そうすることで、なんとかより多くの人たちに映画を知ってもらい、知ってもらった中で勇気や希望を伝えることができればと思っています。これは本当に継続していくことが大切なことだと思います。その中から、先ほど言ったような若い世代の人たちが、どんどん自分事としてクリエイティブな世界に入ってきてくれて、自分自身が活躍できる場を見つけてくれることがとても大切だと思っています。
映画のみならず音楽や小説や絵画や、美術展などもそうですが、そういう芸術に触れる機会を人々から奪っていくコロナは、なにかこう人間を暗闇に落とし込んでしまうことにもなりかねません。人の心を満たす芸術の存在が、より多くの人たちに伝わる方法を私自身も模索しながら、そのプラットフォームとして、なら国際映画祭を奈良で開催することに、今は注力しているところです。
今年は、「宝物はなんでしょう?」という、「宝物」「トレジャーハント」をテーマにしています。いつもトロント国際映画祭と同じ時期なので、同じ9月に日本とカナダで芸術を通してコミュニケーションを取りながら、トロントで自分の作品を上映していただくと同時に、私も奈良で世界中の作品を日本の方たちに観ていただくという活動をしています。それでコミュニケーションを取っていくという地道なことを、やめないということが大事なんじゃないかなと思います。
日本映画の世界進出について

―監督の作品は世界の映画祭でたびたび上映されていますが、なかなか他の日本の監督の映画が世界に出て行かないように感じています。日本映画がもっと世界に出ていけるようにするにはどうしたらいいのか、何かお考えがあれば教えていただけますか。
いっときは日本映画のブームがあって、出ていたと思うんですね。たとえば私だったり是枝さんだったり、新世代って言われた私たちが二十代や三十代のとき、日本映画のブームもあって、トロントで特集していただいたこともありました。そんなふうに日本映画ってカテゴライズされることも強い力を持つと思いますが、やっぱりひとつひとつの作品に力がないと、その広がりは期待できないと思います。私たち日本人が、日本だからこその作品を世界に届けたいと思うような、そういう感性を持つのはすごく大事なことだと思います。
それが配給されるとか世界に流通されるという方法については、今はセールスカンパニーが世界への販売ルートを開拓していくんですけど、そこにも実は限界があるような気がしています。例えば北米に得意なセールスカンパニーだと、そのカンパニーが気に入る映画がカナダで公開されることになります。その窓口の役割となるカナダに強いセールスカンパニーの人に、日本の映画をどんどん知っていただいて、何が興味を持ってもらえるのかということを考えていかないといけません。その広めていくための窓口が、今はもしかしたら狭いのかなというふうに思います。日本はやっぱり島国で、文化が外に出づらいように思います。
近年はアニメや漫画の分野で、世界に日本の文化が伝わっていると思いますが、かたやオリジナル脚本の映画となると、出口が開拓されていないなと思います。そこは、プロデュースとセールスが結びつくルートを開拓しないといけないと思うんですよね。私は、今はもう映画を作るだけ、そこに注力してしまっているので、見てもらうためにはルート開拓というのはすごく重要だと思います。
―トロント在住の日本人から、こんな力添えがあったらもっとうまくいきそうだなといったことは何かありますか。
日本人コミュニティーの皆さまには、もっと日本の今のオリジナル作品が観たいと声を上げていただくことで、双方向の効果が得られるように思います。それには期待したいです。
―最後にトロントの読者にメッセージをお願いします。
『朝が来る』は、日本の今の現実を克明に表現した映画でもあります。普段日本にいても見えづらい部分も描いていて、そこからは決して現状を嘆くだけではなく、その先の未来に光を灯したいというふうに思ってこの作品を作ったので、ぜひカナダでも見ていただけたらなと思っています。また、なら国際映画祭もトロント国際映画祭と同じ時期に開催しています。今回は配信でも様々な作品を見ていただけたり、さまざまな奈良の風景を楽しんでいただけたりしますので、ぜひHPをチェックしていただいて、いつか奈良を訪れていただければと思います。
河瀨直美監督プロフィール
奈良を拠点に映画を創り続ける。一貫したリアリティの追求はカンヌ映画祭はじめ各国の映画祭で受賞多数。代表作は『萌の朱雀』『殯の森』『2つ目の窓』『あん』など。映画監督の他、CM演出、エッセイ執筆などジャンルにこだわらず表現を続け、故郷の奈良において「なら国際映画祭」をオーガナイズしながら次世代の育成に力を入れる。東京オリンピック公式映画監督。2025年大阪・関西万博プロデューサー。
『朝が来る』
(英題:True Mothers)

子供に恵まれず特別養子縁組で子供を迎え入れた夫婦と、その子を育てられず手放さざるを得なかった産みの親の少女。6年後、若い女が子供を返してほしいと夫婦のもとに現れる。(カンヌ国際映画祭公式選出作品/2020年10月23日(金)日本公開予定)
監督・脚本: 河瀨直美
出演: 永作博美、井浦新、蒔田彩珠、浅田美代子
原作: 辻村深月著「朝が来る」(文春文庫刊)
配給: キノフィルムズ/木下グループ