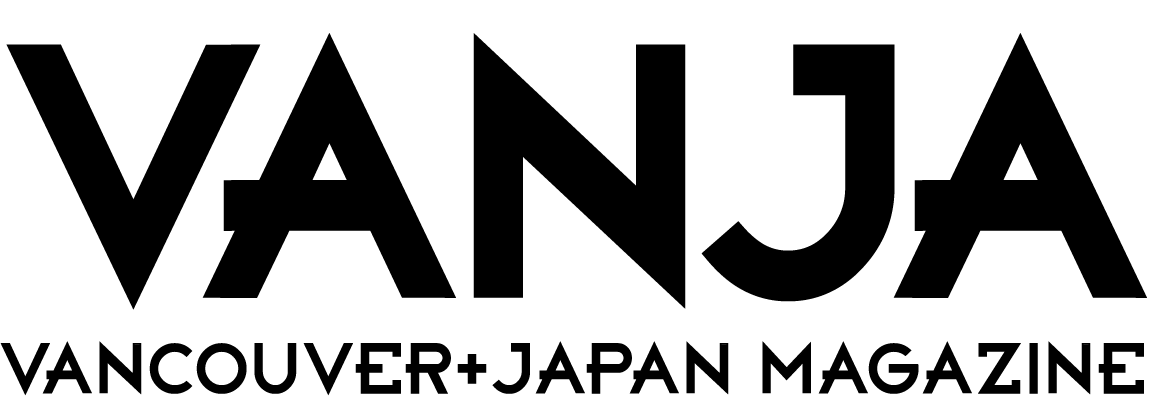シリーズ累計1000万部を突破した清水茜原作の超ベストセラーコミック『はたらく細胞』──体内で起こる感染症やアレルギー、ケガといった様々な出来事を、赤血球や白血球たちの奮闘として描くユニークな世界観は、2018年のTVアニメ化を機に一大ブームを巻き起こし、数々のスピンオフも誕生。その人気作が待望の実写映画化となり、2024年12月に日本で劇場公開された。
実写版では、赤血球役に永野芽郁、白血球(好中球)役に佐藤健、そして彼らの体内で奮闘を支える高校生・日胡(にこ)役に芦田愛菜、その父・茂役に阿部サダヲという豪華キャストが集結。笑って泣けて学べる「メディカル・エンターテインメント」として幅広い世代の支持を集めた。
そんな話題作が、カナダ・トロントで開催された「トロント日本映画祭2024(Japan Film Festival Toronto)」のオープニング作品として、6月12日にカナダ初上映を迎えた。今回の上映には、監督の武内英樹氏とともにプロデューサーの田口生己氏も来加し、現地ファンや海外メディアとの交流が実現。さらに翌6月13日からはNetflixでの世界配信もスタートし、本作は今まさにグローバルな広がりをみせている。
『のだめカンタービレ』『テルマエ・ロマエ』『翔んで埼玉』など数々のヒット作を生み出してきた武内監督が、今回のトロント訪問を機に、海外上映の手応えや「武内ワールド」の制作秘話、そして映画作りに込めた思いをたっぷりと語ってくれた。
海外映画祭で実感した「笑いは国境を越える力」

―2012年の『テルマエ・ロマエ』はトロント国際映画祭のガラプレミア作品に選出され、私も当時現地で観客の熱い反応を体験しました。監督ご自身は現地には行かれていませんが、その後に海外からの反響も届いたかと思います。また『はたらく細胞』はサンディエゴでも上映されたと伺いました。日本の作品でありながら、海外の観客が「文化の違いを超えて笑って楽しんでくれる」感覚を、どのように感じてこられましたか?
武内監督: 日本だと、あまりお客さんが声を出して笑うことって少ないじゃないですか。でも海外の映画祭に行くと、本当に皆さんよく笑ってくれるんです。フランクフルト、ロサンゼルス、上海、シカゴなど色々な映画祭に招待していただきましたが、どこでもゲラゲラと大きな笑い声があがる。そのリアルな反応を直接感じられるのは、監督冥利に尽きるというか、本当に幸せなことですね。毎回海外の映画祭はとても楽しませてもらっています。
世界中で通じる「わかりやすさ」と「発想の飛躍」

ー監督が考える、「武内作品が海外でも受け入れられるエッセンス」とは何だと思われますか?
武内監督: なんで受けてるんでしょうね(笑)。でもやっぱり、わかりやすさ、シンプルさっていうのはあると思います。共感できる要素がちゃんと詰まっているというか。特に今回は「体の中の話」ですから、人種とか民族とか全く関係なく、世界中どこにいても共通のことですよね。風邪をひいたらくしゃみが出る、お腹が痛くなる、ガンになる…そういうのは誰にでもあることなので、そういう意味ではとても分かりやすいテーマなんだと思います。
ーきっと今日のトロントの上映でも、たとえば「うんち」のシーンではみんなゲラゲラ笑っていそうですね。
武内監督: ああいうところは今のところ世界中どこでも共通でウケています(笑)。
ーせっかくなので田口プロデューサーにも伺いたいのですが、プロデューサー目線で見て、武内監督の作品が海外でも受け入れられている理由はどんなところにあるとお考えでしょうか?
田口プロデューサー: 私も今回、武内監督とは初めてお仕事をご一緒させていただいたんですが、やっぱり一番スペシャルだなと感じたのは、その発想の飛躍の仕方ですね。普通の監督さんではなかなか思いつかない発想を持っていらっしゃるというのがすごく大きいと思います。
今回の『はたらく細胞』も、原作は漫画なんですが、とても真面目というか、学習要素もしっかりあって、勉強にもなるし面白いという作品ですよね。そこに、たとえば「肛門でうんちを押し合う」とか、そういうコメディ要素を監督は自然に入れてくる。
それ以外にも、たとえば過去の作品でも人が投げ飛ばされるシーンで、人形を使って飛ばしたりするんですね。普通だったら、ちゃんと人を飛ばさなきゃってなるところを、あえて人形にして笑いに転化する。そういうアイディアが本当に面白いなと感じます。
こういう発想の飛躍が、やっぱりどの国の人が見ても笑えるポイントになっていて、海外でも広く受け入れられている理由のひとつなんじゃないかと思っています。
原作の世界観を守るために――キャスティングへのこだわり

ー俳優陣それぞれの個性とキャラクター造形が自然に融合しているのがとても印象的でしたが、本作は「体内ドラマ」と「父娘の現実ドラマ」という二重構造が重なり合い、そこにユーモアとドラマの絶妙なバランスが流れています。監督がこれまで大切にされてきた「笑って泣ける作品」という魅力が、今回もすごく伝わってきました。もともと原作にも確立されたキャラクターの魅力がありましたが、映画という新たな表現の中で、スケール感や感情の振れ幅、俳優さんたちの個性をどう融合させていくかは、とても繊細な作業だったと思います。監督として、こうした全体の演出設計や制作プロセスで意識されたこと、特にこだわられたポイントをぜひお聞かせいただけますか?
武内監督: 原作ものをやるうえで一番大事なのは、やっぱり原作のイメージに合っているかどうかというところなんですよね。だからキャスティングがすごく重要になってくるんです。原作ファンのみんながそれぞれ「最大公約数的なキャラクター像」を持っているわけで、そこから大きくズレてしまうと、一気に拒絶反応が起きてしまうんじゃないかと思っています。
たとえば、「ああ、この人がキラー細胞を演じるのならイメージ通りだよね」「マクロファージだったらこの人だよね」という、みんなが納得できるポイントを探していく作業がとても大事になります。そこを探り当てるのがすごく大変な作業で、ズレないように的確にキャスティングしていくのが、ものすごく重要なポイントだったと思います。
国境も争いも越えて──エンターテインメントが持つ「つなぐ力」

―世界では今もなお戦争や争いが続き、分断や差別が加速しているようにも感じます。そうした時代だからこそ、私は改めて「エンターテインメントが持つ力」がとても重要だと感じています。多くの映画監督も「想像力と物語が人を救う」と話されています。
監督はこれまで『翔んで埼玉』『テルマエ・ロマエ』『はたらく細胞』と、ユーモアを通じて人間社会の複雑さと滑稽さを描いてこられました。こうした混沌とした時代の中で、エンターテインメントが果たせる「笑いと希望の役割」について、お考えをお聞かせいただけますでしょうか?
武内監督: まあ、現実の世界では近隣の国同士で仲が悪いなんて言われたりもしますけど、映画祭に呼んでいただいて行ってみると、そういう国の人たちもすごく作品を受け入れてくれて、めちゃくちゃ笑ってくれたりするんです。
本当に「エンターテインメントに国境はないんだな」と、つくづく感じますね。作品を作りながらも、そうやって国境を感じずに笑い合ったり、悲しみを共有したりできるというのは、やっぱり映画の力だと思います。少なくとも、映画人同士はこうして仲良くいられる世界でありたいなといつも思っています。
『はたらく細胞』は観客自身の物語でもある

ーまさに今回トロントで上映される『はたらく細胞』のように、様々な役割の細胞たちが協力し合う物語です。そういった意味ではどんなメッセージを届けられると思いますか?
武内監督: 作品の中でも、それぞれの細胞が個性を持っていて、それぞれに与えられた役割を背負って生きていますよね。それは人間も同じで、やっぱり共通するところがあると思っています。少し国家にも例えられるようなところもあって、細胞も、体を維持するためにそれぞれの仕事を全うしている。だからこそ、どんな仕事であっても自分の生業に誇りを持って全うすることが大事なんだということですね。
田口プロデューサー: 意外と原作もそうなんですが、体内の話でありながら、実はメタファー的に「この世界全体の話」にもなっているんです。細胞ひとつひとつが、実は観客や読者自身の物語でもある、という構造になっていて。だからこそ、たとえば接客を頑張っている人だったり、辛いことがあっても日々頑張っている人だったり、観ている人の心にどこか重なる部分がある作品なんだと思います。それがこの作品の一番のテーマだと考えています。
作品づくりを支える「背骨」と制作現場の発見

ーそうした方向性は、プロデューサーとして作品を作る初期段階で監督とすり合わせていくものなんですか?
田口プロデューサー: そうですね。作品を作り始める時に必ず「この映画を一言で説明すると何なのか?」という問いにしっかり答えられるようにしておく。これは最後までブレてはいけない、とても大事な軸なんです。もちろん作品というのは、見る角度によって言いたいことが変わって見える部分もありますが、作っていく中で「本当に自分たちは何を伝えたいのか?」を常に確認しながら進める必要があります。
実際、製作を進めていくと「意外と違ったかもしれない」と気づくこともあるんです。だからこそ、最初に監督とプロデューサーで「ここが作品の背骨だよね」という部分をしっかり決めておく。そこは絶対に守る、という意識で進めています。
ーなるほど。最後までぶらさずに守る、と。
武内監督: その「背骨の部分」は絶対に守るんですけど、作っていく途中で新たな気づきが生まれることもあります。「あ、原作の中にこんな面白さが潜んでいたんだな」って。そういう新しい発見が膨らんでいくのも、すごく楽しみにしている部分ですね。だからあまりガチガチに固めすぎずに、背骨はしっかり持ちながらも、巡り合ったアイデアや、制作中に出てくる色々な困難を一緒に乗り越えながら作っていくのが面白いんです。
この『はたらく細胞』の制作でも、実際にやっていく中で色々な発見があって、それをどう映像にしていくかを、言葉では説明しきれない部分も含めて、デザイナーやアーティスト、カメラマンたちと相談しながら、だんだんとキャラクターや映像の世界観が形になっていきました。そこが制作していてとても楽しかったですね。
旅が教えてくれた「多様性」と「幸せとは」
ー監督は学生時代から世界を旅され、アメリカ横断やアジア各国も巡ってこられました。若い頃の旅そして旅を通じて感じた「世界の多様性」や「価値観の違い」が、映画づくりや人生観にどんな影響を与えていると思いますか?
武内監督: 20代の頃は本当に日本が一番景気のいい時代、バブルの真っ只中だったんですよね。1980年代、90年代は、どこへ行ってもアジア人というとほぼ日本人、という時代でしたし、アジアでは日本語しか使わずに旅ができていました。
当時のアメリカは、今とはまるで違っていて。レーガン大統領の時代で、アメリカ経済は結構悪くて、ロサンゼルスやニューヨークなんかも本当に荒廃していたんです。その頃、日本企業がロックフェラーセンターを買ったり、コロンビア映画をソニーが買収したりしていて、アメリカでもかなり対日感情が複雑だった時代でした。
それに、旅をしていると国によって法律が全然違うというのもすごく感じました。日本でだったら人生終わってしまうようなことが、ある国では普通にOKだったりする。じゃあ「法律って何なんだろう?」とか「そもそも正しさって何だろう?」と考えさせられたりもしました。
イタリアに行けばみんな陽気で楽しそうだし、ドイツに行くとみんな険しい顔をしていて、ちょっと日本人に似てるなと思ったり。民族性とか国家とか、そういう違いを体感できたのは、ものづくりをする上でも今すごく役に立っています。
やっぱり「何が正義で、何が悪なのか」を多角的に見られるようになるには、旅はすごく大事だと思います。ネパールにも行きましたけど、最貧国といわれながらも、そこに住む人たちの目が本当にキラキラしていて美しかった。貧しくても、もしかしたらこっちのほうが幸せなんじゃないかなって思ったりもしました。アメリカに戻ってきて、みんながドルを追いかけているのを見ると、「本当の幸せって何なんだろう?」って考えさせられるんですよね。そういう経験は、やっぱり今の作品作りにも少なからず影響しています。
フジテレビ退職の決断と「世界に通じる映画監督」への挑戦

ー人生100年時代とも言われる今、日本でもキャリアや生き方を見つめ直す人が増えています。一方で日本は依然として「正社員文化」「年功序列」「転職リスク」といった社会構造の中で、生きづらさや不安も指摘されています。監督もフジテレビの早期退職制度を活用して、大きな決断をされました。これまで築いてきたキャリアを一旦手放す勇気は、どのように生まれたのでしょうか?
武内監督: 自分としては、やはりもっと早く映画を撮りたかった。どうしても会社にいるとドラマ制作が中心になってしまうので、そこから早く脱却して映画を本格的に撮りたいという思いがありました。
それと同時に、日本の映画をもっと海外に知らしめたいという気持ちも強かったです。昔は黒澤明監督や小津安二郎監督のように、世界でも有名な日本の映画監督がたくさんいました。そこに少し寂しさを感じていて、自分は世界に通用する映画監督になりたい、そう思って会社を辞めました。
現場はまるで文化祭──「楽しさ」が作品の魅力に

ーその経験を経て今、「働くこと」「キャリア」というものをどのように考えていらっしゃいますか?
武内監督: あまり「働いている」という感覚がないんですよね。毎日自分の趣味をやっているという感覚です。もちろん現場は大変なことも多いですが、それでも楽しい仕事をさせてもらっているというのが正直なところです。現場に行くと「今日も楽しんで面白い映像を作ろう!」という気持ちになる。しかも昔からの仲間たちと一緒に作品を作れるという喜びもあって、本当に毎日が趣味の延長線上みたいな感覚で仕事をしています。もちろんそこには田口さんのように、ちゃんとストイックに線を引いてくれるプロデューサーがいてくれるからこそで、自分はその中で自由に踊らせてもらってる感じですね。
田口プロデューサー: でもやっぱり一番大事なのは、作る人――つまり監督が現場で楽しそうにしている作品って、絶対に楽しい作品になるんですよ。作っている本人が笑っていないのに、笑える作品なんて作れないですから。監督が楽しんでいるからこそ、自然と現場にも笑いが生まれて、それが作品にも表れてくるんだと思います。
武内監督: スタッフも毎日、文化祭をやってるみたいな感じですよ(笑)。自分はその文化祭実行委員長みたいな役割ですね。
田口プロデューサー: 現場でモニターを見ていても、みんな本当に笑ってますからね。さっき監督は「毎日遊びに行ってるみたいだ」って冗談めかしておっしゃってましたけど、でも僕から見てもそういう現場の雰囲気があることは、逆にすごく安心できるんです。
武内監督: 田口さんはどちらかというと学級委員長というか、生徒会長というか(笑)。映画作りもそれぞれ役割があって、バランスが必要なんですね。
海外に出たからこそ見えた「日本の強さと魅力」

ー今の若い世代や海外に飛び出してチャレンジする方々にアドバイスするとしたら、どんな言葉をかけたいですか?
武内監督: うーん…今、日本からカナダに来ている人たちだったり、日本から海外に出ていこうとしている人たちに対して、ということですよね。自分もこれまで67カ国くらい旅をしてきたんですが、若い頃はやっぱりアメリカやヨーロッパ、カナダに憧れて旅をしていました。でも、行けば行くほど逆に日本の良さに気づくようになったんです。
食べ物は美味しいし、電車は時間通りに来るし、格差も少なくて、夜に女性が一人で歩けるぐらい治安もいい。街も清潔で、改めて「なんでみんな日本の文句ばっかり言ってるんだろう?」と思うようになりました。
もちろん、イタリアの景色に憧れたり、カナダの大自然でスッキリしたくなったり、そういう魅力は各国にあるけれど、トータルで考えたら日本ってすごく恵まれている国だと思うんです。歴史も世界で一番長い部類で、例えば日本の国家の歴史はギネスに認定されていて、2600年(学術的にみても少なくとも1500年は続いている)。それに続くのがデンマークで約1000年、イギリスで1000年ちょっとくらい。こういうことを実は日本人自身があまり知らないんですよね。
学校でもあまり教えられてこなかった部分もあるんですが、自分たちの国のことをもっと学んだり、調べたりすることで、日本の良さや自分たちのルーツに気づけると思います。そして、その素晴らしさを海外でも現地の人たちにもっと広めていってくれたら嬉しいなと思いますね。
Netflixで世界配信スタート

ー明日(6月13日)からNetflixで世界配信が始まりますよね。
武内監督: 誰が観ても理解できるストーリーだと思うので、どんな反応が返ってくるのか今はとても楽しみです。今日がトロントでの最後のスクリーン上映になりますし、僕自身もスクリーンで観るのはこれで見納めになるので、すごく楽しみにしています。
ー田口さんはプロデューサーとしては今どんなお気持ちですか?
田口プロデューサー: 監督はこの作品で何度か海外に行かれていますが、私は今回が初めての海外上映立ち会いなんです。実際に海外のお客さんの反応を生で見るのは今日が初めてなので、すごく楽しみにしています。
次回作はすでに完成──世界への新たな挑戦
ー次回作として、全世界配信を予定した大型連続ドラマの制作が決まっていると伺いました。これまでの映画とはまた違うスケールや制作スタイルになるかと思いますが、どんな作品が予定されているのか、現時点でお話しできる範囲で教えていただけますでしょうか?
また、国際配信という新たなフィールドに挑まれるにあたって、監督ご自身が今どんな手応えや楽しみを感じていらっしゃいますか?
武内監督: 作品の詳細については、まだお話しできる段階ではないのですが、『はたらく細胞』に続いてまた世界配信できる作品が作れたことに、今は本当に喜びを感じています。「日本でもここまでできるんだ」ということを、世界にももっと知ってもらいたいという思いで、一生懸命つくりました。もう作品自体は完成していて、あとは編集を終わらせるという感じです。