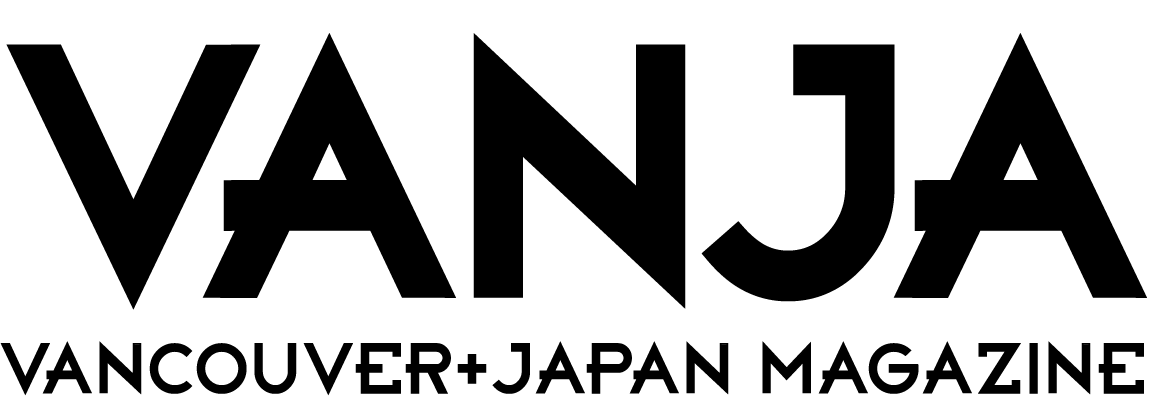ジャルジャル・福徳秀介氏が小説家デビュー作として描いた恋愛小説『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』。その繊細な世界を、大九明子監督が圧倒的なリアリティと優しさで映画化した。萩原利久、河合優実、伊東蒼ら若手実力派が演じるのは、不器用に迷い続ける若者たちの日常の揺らぎ。人生の岐路でふと交差するセレンディピティ――偶然の出会いと選択の積み重ねが、静かに心を震わせていく。フィクションと現実のはざまで「生きること」を静かに肯定し続ける監督の視線は、観る者の胸にそっと寄り添う。今回は、原作との向き合い方、若きキャスト陣の魅力、そして監督自身が迷い続けた経験を交えながら、本作に込めた思いをじっくり語ってもらった。

萩原利久・河合優実・伊東蒼──3人の若き才能が交差する現場での輝き

―本作では、萩原利久さんの揺らぎ続ける繊細な芝居、河合優実さんの自然体の強さと存在感、伊東蒼さんの余白に滲む情感といった3人それぞれがとても印象的でした。監督は撮影前、それぞれにどんなイメージを持たれていましたか?そして実際に現場での3人の姿を教えて下さい。
萩原利久くんは、彼が14歳の時に短編ドラマで一度ご一緒していて、その時はオーディションで出会ったんです。すごく面白い子だな、いい子だなと思い選びました。そこから時間が経って、当たり前ですけど、すごくしっかりした男性になっていて。ぐっと背も伸びて。でも、あの頃の可愛らしさとか透明感はそのまま残っているんですよね。すごく真摯に仕事に向き合う姿勢は、14歳の時からずっと変わっていなかったです。

たとえば、私が「ちょっと違うな」「こういう感じかな」と伝えると、「承知しました」とすぐに応えてくれるんです。やり方もすごく面白いなと思います。
河合優実さんは、2年前にNHKの連続ドラマで初めてご一緒しました。「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」で主演を務めていただいて。その前から映画などで拝見していて、魅力的な高校生の俳優さんだなと思ってキャスティングさせてもらったんですけど、そのNHKのドラマでの演技を見て「とんでもない実力の方だ」としっかり感じました。なので今度はぜひ映画でご一緒したいと思ってお声がけしました。
NHKのドラマの方は、家族が色々な悲劇に見舞われるけれども、それを笑い飛ばしながら明るく生きていく、コメディー要素の強い作品だったんです。でも今回はそういう要素は全くなくて、映画におけるヒロインというポジションです。ただ、主人公の都合のいいヒロイン像というのが私はすごく抵抗があって、そういうヒロインではなく、ひとりの人間として、主人公が恋をする相手を描きたかったんです。彼女ならそれをやりきってくれると期待してオファーしましたが、見事に応えてくれました。
伊東蒼さんについては、私は片山慎三監督の『さがす』を観て大ファンになって、いつかご一緒したいと思っていたんです。今回、彼女は関西出身ということもあって、関西弁ももちろんネイティブで、初めてオファーさせていただいて出演してもらいました。実際にご一緒して感じましたけれども、彼女も本当に底知れない力を持っていて、生まれながらの俳優という感じがします。力まず自然にそこにいるんだけど、ものすごい磁場みたいなものを持っている。すごい俳優さんだなと改めて思いました。
ー本作では「セレンディピティ」という言葉がキーワードになっています。登場人物たちは偶然の出会いやふとしたきっかけの中で少しずつ道を見つけていきます。こうした「偶然が運んでくれるもの」「出会いが人生を少しずつ動かしていく感覚」は、監督ご自身の人生観ともどこか重なる部分があるのでしょうか?
そうですね。極端なことを言うと、もう毎日がセレンディピティの積み重ねというか。あのとき右に行ってたら違った、左に行ってたら違った…そういう選択を知らず知らずのうちに重ねてきて、今があると思うので、そうですね。まあ、人生イコール、セレンディピティみたいなところがあるのかなとは思います。
原作との距離感とキャラクターを描く喜び

─本作は男性作家による原作小説がベースとなっていますが、同じ物語であっても、作り手の立場や人生経験によって、人間関係の描き方や心の機微は自然と変わっていく部分もあると思います。大九監督は脚本も手がけていますが、キャラクターの心情や関係性を描くにあたり、原作と向き合う中でどのような部分を自然に受け止め、どのような部分でご自身の視点や解釈を重ねていかれたのでしょうか?

全作品に言えることなんですけど、「すり合わせ」とか、小説に忠実にということはあまり考えていないんです。そもそも、小説やコミック、原作へのリスペクトというのは必ずしもそれをそのまま映像化することではないと思っている感じです。批評的な視点もあってしかるべきだと思いますし、「この小説を私がどう読んだのか」という姿勢も入ってしかるべきだと考えています。
今回もまさにそうで、原作はほとんど全編にわたり小西の視点で描かれている小説なんですね。小西がいる場所にしか桜田もさっちゃんも存在していないという構造です。でも私はあえて、彼女たちが単独でいる場面を膨らませて描くようにしました。
桜田については、一人でいるシーンはあまり入れていませんが、一つだけ妄想のシーンで小西の頭の中に出てくる「ひとりの桜田」を入れました。小西が怯えて、桜田が自分を罵倒している妄想シーンですね。あれは一見すると事実のようにも見える撮り方をしています。
さっちゃんに関しては、大学のシーンやバンドの練習シーンなどを加えています。小説にはなかった彼女の内面を補うことで、いわゆるボーイ・ミーツ・ガールの「ボーイ側の視点」だけでなく、「ガール側もちゃんと生きて輝いている」という部分を描きたいと思ったんです。
─ストーリーを膨らませていく時は、自然に「ポン」と浮かぶ感じですか?

そうですね、意外とそんな感じです。小説を読んでいるときに「ここはちょっとこうしたくないな」と思ったり、批評的な視点が自分の中に入ってくるんですね。そういう時に、それを無視して作る方が、逆に原作へのリスペクトがないと私は思っていて。リスペクトしているからこそ、その小説の真髄に深く迫っていくには、そういう批評的な感覚が必要だと思っています。なので、「ポンと浮かぶ」という表現は、意外と近いかもしれません。
今回で言うと、さっちゃんというキャラクターはネタバレになるので詳しくは言えませんが、とても悲劇的な運命を背負っている登場人物です。でも、彼女を都合よく現れて、都合よく消えていく存在にはしたくないと思いました。彼女をどれだけ輝かせられるかが、この映画を私が引き受ける理由になるかな、と考えていました。
─監督自身の中にある人間観察や日常の違和感を脚本段階からじっくりと育て、演出へと繋げていく作業は、まさに大九作品ならではの魅力にも感じます。この「自分で書く」ことの喜びや苦しさ、また他の人に任せない理由──そのあたりの創作の核心について、今あらためてどんなふうに感じていらっしゃいますか?

私はこれまで何本もやってきた中で、やっぱり「これ以外に自分が映画を作る方法はないな」と思うようになってきました。シナリオを書きながら、私にしか見えていない映像があって、それを文字化していく作業なんです。
小説を読んで「このシーンを撮りたいな」と思ったときに、そのシーンがパッと浮かぶんです。なので、頭から順番に書いていくというよりは、まず浮かんだそのシーンを書いてみる。そこから「このシーンにたどり着くには、こういう構成が必要だな」と再構成を考えたり、「ここに足りないシーンがあるな」と思って加筆していったりしています。何本か作っていくうちに、だんだん自分でもわかってきた感じがあります。自分の向き不向きのようなものが見えてきたというか。「この映画を撮るなら、このスタイルだな」と、自然とそういうふうに固まってきたように思います。
「今、この時代に映画を撮る」ということ

─監督は「命のことばかり考えていた時期にこの脚本を書き始めた」と語られています。まさに今、世界ではガザやウクライナをはじめ、日々多くの命が失われ、分断と暴力が繰り返されています。この時代に映画を撮る者として、「映画にできること」「映画にしかできないこと」は何だとお考えでしょうか。
そうですね、世の中にはこういうことがあるんだということを、フィクションの世界の中でも盛り込んでいく──それが映画にできることだと思います。今回もまさにそう考えて盛り込んでいきました。
現実の世界とフィクションの世界である映画は、互いにフィードバックし合いながら変わっていけるものだと信じたいというか……そうでも考えないと、やっていられない、という思いもあります。世界の悲劇のような現実に直面したときに、自分にできることは何なんだろう、と考えてしまう。たとえば、何も感じていないわけではないけれど「自分には何ができるのかわからない」と思っていた若者が、目の前でデモ行進を見たときに「一緒に歩いてみよう」と思う──そんなふうに何か小さなアクションを起こす若者の姿を、フィクションの中でも描いていきたいと思ったんです。現実と地続きになるような映画になればいいなと思いながら、そうしたシーンも描きました。
こういうことを描くのに、私は上手でなくてもいいと思っているんです。むしろ、ラブストーリーの中に突然こういう要素が入ってくることに拒否反応を示す人もいるかもしれませんが、でもそれくらい唐突に、私たちの日常の中にもこうした出来事は存在しているんですよね。新聞を開けば毎日のようにそうした情勢が報道されています。日常の中に、こうした悲劇は確かに存在していて、それを見ようとするか、見まいとするかは本人次第なんだと思います。
だからこそ、映画にはそういうものを「刮目させる力」があると信じています。下手でもいいから、今回はしっかりと盛り込もうと思って描きました。
BGMを使わずに描く、静けさの中のリアル

─大九監督の作品では、言葉にならない感情を「音」や「沈黙」が静かに支えているように感じます。本作でも、登場人物たちの呼吸や生活音、わずかな間や静けさが、感情の揺らぎをよりリアルに浮かび上がらせていたように思いました。監督は今回、音や沈黙をどのように意識し、物語の中に息づかせていかれたのでしょうか?
 私は普段から映像を作るときに音で遊ぶのがとても好きで、コメディ的に音を付けて遊ぶことも好きですし、逆に音を突然奪って「無音の世界」みたいに表現することも好きなんです。音の表現力には、まだまだたくさんの可能性があると思っています。
私は普段から映像を作るときに音で遊ぶのがとても好きで、コメディ的に音を付けて遊ぶことも好きですし、逆に音を突然奪って「無音の世界」みたいに表現することも好きなんです。音の表現力には、まだまだたくさんの可能性があると思っています。
今回の作品は、「初恋クレイジー」という音楽がとてもキーになる曲として登場する映画だったので、いわゆるBGM(登場人物の心情に寄せた劇伴)は一切使っていません。映画というと通常は、劇伴があって登場人物の感情を音楽が支えるものが多いと思いますが、今回はそれを全く使わずに、現場で実際に鳴っている音、たとえばCDで流れている音や、演者が実際に演奏している音楽、大学のどこかから聞こえてくる学生たちの練習の音──そういった音だけで構成しました。
いつものように音で遊ぶというよりは、音を生き生きと貼り付けたり、時にあえて奪ったりしながら、音そのものが感情表現として作用する作品にしました。
物語を世界に届けるということ

─日本の青春映画や恋愛映画は、感情を抑えた表現や「言えなさの美学」みたいな要素があると思うのですが、監督として、作品を海外に届ける際に「外国人観客のわかりやすさ」や「文化的迎合」を意識する部分はありますか?それとも、むしろ日本的なまま描くことこそが、今の海外の観客に届く力になるとお考えでしょうか。監督ご自身の国際的な受け止められ方への意識について、お考えをぜひお聞かせください。
それはもう国によってまったく違いますし、毎回本当に面白いなと思っています。今日も実は、カナディアンの皆さんがどんな反応をするのか、すごく楽しみにしています。
私自身は、あまり「国内だけ」とか「誰に向けて」といったことは強く意識していません。誰かに向けて作るというときに、「世界のどこかの誰か」に向けて作っている感覚はどこかにあります。なんとなく遠くの方を見ながら、そちらに照準を合わせて作っている感じですね。その手前にある色々な要素は、あえてピントを少し鈍らせて、遠くを見ているような気持ちで作っています。なので「日本の観客はこういうのは好まないだろうからやめよう」という発想はあまりなくて、むしろあえてちょっと挑発してみよう、ということはたまにあります。
今はSNSの時代ですから、配信などでご覧になった海外の方が、その国の言葉でSNS上で感想や質問を投げかけてくれたりすることもあって、本当に嬉しいですね。グーグル翻訳を使ってお返事したりしています。
─ヒットの定義も難しいですよね。
本当に難しいですね。分かりやすく言えば、映画館の上映館数や興行収入が配給会社的には「ヒット」と呼ばれる指標になると思います。おかげさまで今作も、日本ではまだロングラン上映が続いています。規模としては決して大きくない、100館にも満たないような規模感ですが、それでも配給会社はとても喜んでくれています。
─監督ご自身の中の「ヒットの定義」は?
「届くべき人に届いたかどうか」、それがヒットかどうかの基準かなと私は思っています。私の作品はいつも賛否両論が起きがちなんですが、今回も今までで一番そういう振れ幅が大きくて、私としてはすごく面白いなと思っています。不思議ですよね。想像していなかった反応もたくさんいただきますし。たとえば、今回の作品では私の女性キャラクターへの愛がちょっと強すぎたのか、主人公のファンの方──萩原利久くんのファンの方から「主人公がちょっと悪者っぽく描かれている」といった声をいただくこともあります(笑)。
変わりゆく時代の中で──映画館への愛と若者へのエール

─監督のSNS固定ポストでも映画館への愛情が伝わってきます。やはり監督は映画館愛が強いのでしょうか?
やっぱり映画館が本当に好きだったところから始まって、気がついたら映画監督になっていたという感じなんですよね。暗いし、一人になれるし、それだけでもスペースとしてすごくありがたい場所なのに、そこで映画まで観られるなんて、なんて素敵なんだろうと思っていました。
─時代はどんどん、たとえばNetflixに代表されるような配信中心の時代に移ってきています。こうした変化の中で、監督は今あらためて「映画館で映画を観る」という体験をどのように捉えていますか?
そうですね。だからこそ残っていてほしい、映画館という文化を守ってほしいという気持ちはすごくあります。やはり映画館に行くこと自体が、今はもう私の年代でもある程度「特別なこと」になりつつあります。私の親世代の頃は、もっと映画が身近で、テレビよりも映画のほうが安くて、みんなバンバン観に行っていた時代でした。私の若い頃も、今よりは映画館の数も多かったですし、ミニシアターブームの全盛期でもありました。映画館という場所は、本当に自分を支えてくれた大切な場所でしたね。特に20代の頃は、なおさらそう感じていました。
─実際に監督ご自身も、就職して仕事に追われながら迷い続ける中で、ようやく映画美学校で映画に向き合い始めたと伺いました。今の20代・30代にも、「自分は何者になれるのか」「これでいいのか」と悩む若い人たちがたくさんいるように思います。
監督ご自身の経験を振り返って、こうした「悶々とする時期」をどう過ごし、どう向き合えばよいと思われますか?
あの…少しずつ楽になりますので、みなさん、あんまり深刻になりすぎずに、ぼちぼち苦しんでください、っていう感じですかね。