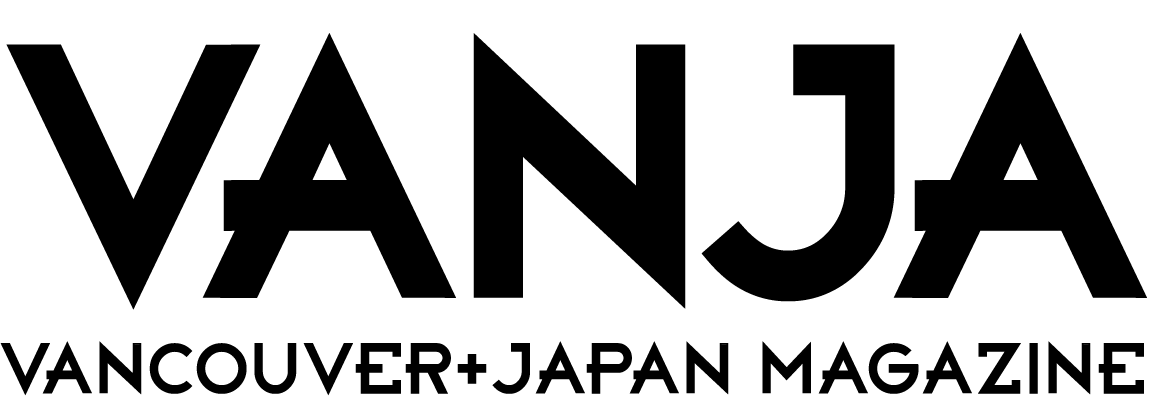エンタメ業界とユーザーから取り残される新聞メディア
新聞メディアはエンタメ業界から「置き去り」にされているようにも感じます。なぜなら新聞はテレビよりも出版よりも古い、江戸時代の瓦版から始まっていた「最初のマスメディア」であり、そこには商業性の入る余地がない、とされてきました。市民の目から政治を監視する「ジャーナリズム」とそれによる国民の「教化」、そこにはエンタメ性と商業性を置き去りにした、メディアとしての矜持があります。
エンタメ業界は基本的には「売れるものを届ける」ものです。人々がお金を出してでも視聴したい楽しみたいと思うものを、テレビや映画、ゲームで提供していきます。だから人々の嗜好が変わればそれにあわせて提供するものも変えますし、移り変わるトレンドのなかで右から左に揺れ動く。ヒットしたものがあれば、どんどんそれを真似していく。
ですが、新聞は「スクープを取ること」が競争優位性を獲得する条件でした。政治・経済という当時の国民の関心事を、5大紙のなかでどうやって自社だけが獲得するか。それは読売新聞の渡邉恒雄記者がそうであったように時の首相や首相候補者と密な関係性をもち、誰よりも「権力の中枢に近づいておくこと」が必要でした。
新聞はめずらしいほどコンテンツと販売の分離が明確です。「ジャーナリズム」としてはある意味それが正解で、販売に有利なコンテンツを作ろうとしてしまうと政治や国際といったテーマから遠ざかります。そもそもラジオ・テレビ欄を一面にもってきたのは新聞が〝大衆〟と迎合した結果でしょうし、この2020年代をもってもなお一面を政治が飾り、(視聴率は高い)社会面が奥のほうに追いやられているのは、新聞社が「コンテンツで売っているわけではない」という強いプライドの現れでしょう。ただそうはいっても政治経済は1990年代までは関心事であり続け、そこに人々がお金を払って知りたいと思わなくなったのは2000年代に入ってからの傾向でしょう。
市場の「箱庭化」により築いた世界最大の新聞市場
21世紀に入って如実になってきたコンテンツとニーズのミスマッチ、それでも売上をある程度維持してきた日本新聞産業の秘密は(日本のテレビと同様に)限られたプレーヤーでの競争環境で「箱庭化」したことでした。第二次世界大戦のメディア統廃合によって毎日・朝日・読売・産経・日経の5大紙に統合され、それらが日本全国に販売代理店網を敷き、競争によって、また戦後の好景気と教養主義によって「新聞をとることが当たり前」という日本文化は世界でもまれにみる巨大な新聞市場を築きました。
いまだに全世界で購読者世界一は20年前の1000万部から数字を900万部まで落とした読売新聞、2位は660万部の朝日新聞、3位でようやく米国のUSA Todayが410万部です。毎日新聞も日経新聞も世界トップ10に入っているので、米国・インド以上に日本は「巨大新聞メディア市場」があるとすれば世界シェア5割近い、最大の新聞大国です。

新聞離れを救っているのは「新聞コンテンツの面白さ」では決してなく、「ビジネスモデル」です。新聞の中身自体が人々の関心事でなかったことは、2000年代に入ってヤフーなどネットニュースが代替していった過程で証明されています。なにも日本全国どころか世界各首都に支社をはりめぐらせ、高い記者給与と出稿待遇で獲得してくるニュース記事がたくさん見られていたわけではありません。テレビの視聴率同様に、それが「見えなかった」というだけの世界で、ウェブでPVが明確になると(公開されてはいませんが)ユーザーの関心が、自分たちが必死に獲得し、書き上げているものとは違うということに気づき始めました。図1にみるように、この10年で50%はいたはずの新聞紙を主要ニュースソースとする人々はもう2割を切りました。ネットポータルやSNS、キュレーションメディアですでに8割の人は十分になってしまっている。新聞社のネットメディアである必要すらありません。
それでも新聞の売上はこの10年思ったほどには落ちなかった。これは「新聞の月額購入の解約」が思ったよりも敷居が高かったことによります。むしろ新聞離れは、「新居に引っ越した」「進学した」など生活のフェーズが変わった人が再度新聞をとらなかったという「消極的な退行」によって起こり、それがゆえに売上減少はずいぶんなだらかに進みました。
全世界でも市場は半減、デジタルでふさぎきれない落ち
日本は「世界最大」新聞市場ですが、「世界最先端」新聞市場でいえば米国かもしれません。リーマンショック後に壊滅的なダメージを負った米国新聞社はこの10年身震いするような改革を進めてきました。2005年にピークの600億ドル市場であった米国は、15年で広告売上が5分の1になり、雇用者も半減以下になるような(2008年7万人いた記者職が現在は3万人強と6割が解雇されています)荒療治のピボットを必要としました。日本の200億ドル市場は、販売がメインの日本の新聞社は雇用者をそれほど減らさず(2万人強は「解雇」より「新規採用しない」ほうに集中し、実は1割も減っていない)、もはや日米で本当に同じ産業にいるのか?というほど対極的な状況です。


日米以外も含めた全世界の新聞市場の傾向は図2でみるとおりです。この10年は衰退傾向がとまらず、徐々に増えていくデジタル(広告・定期購読)では支えきれず、現在は10年前から半減しての1000億ドルを割りそうなところです。コロナはむしろ新聞市場の衰退を加速させました。
デジタルはなぜ起死回生の一滴にならないのでしょうか?これは我々も実感のある「アナログダラー、デジタルペニー」と同じ現象で、新たにデジタルで同様のコンテンツを消費しようとなると、どうしてもそれを「高い」と感じてしまいます。人々はデジタルなものに一定以上の単価を支払うことに抵抗を示します。GAFAのサービスが無料を基本とし、かつECがコモディティの安売りを前提として普及したこともそれを助長しているのでしょう。
こうなると日本のような高齢化社会はむしろ有利に働いています。New York Timesが週2ドル、月8ドルといった低単価でサブスクをしているのに対して、日経新聞はいまだ紙で4900円、電子版ですら4277円。紙の定期購読でしみついた価格帯を維持し、米国新聞紙の4〜5倍の単価を守っています。それですら、日経電子版のユーザー数は成長をみせており、すでに有料会員80万人強、年間400億円近い収益が得られています。代替のネットサブスクニュースであるNewspicksがいまだこの状況でも一覧性のある日本経済の網羅的報道という確立したポジションで、月額課金ユーザーは成長傾向。80万人を超えるユーザーから年300億円以上ものデジタル収益を得られるようになっています。
かたやバズフィードやNewspicksのような新興メディアの対象は40代以下の、月500円課金に慣れたデジタルリテラシー層です。月1500円と日経に比べて3分の1のお得な価格帯でもこの年齢層には高すぎる、というジレンマがあり、課金者20万人あたりで頭打ち感がおこりはじめ、なかなか伸びません。これがゆえに、デジタルの成長が軽視され、アナログからの転換を「遅らせること」が、今は経営の優先順位が強くなってしまう原因でもあります。
デジタルメディアの成功例、ニュースは今後誰のものになるのか
この20年、マスメディアは皆つるべ落としのような市場下落に直面してきました。音楽から始まり、出版も雑誌は半分以下に落ち、家庭用ゲームもモバイルを例外に落ち続けます。デジタル化はその救いにはなりません。彼らもまた「デジタルは下落の支えにはならない」という状態で、ジリ貧を味わってきました。
しかし、兆しが変わったのはこの2年です。まず動画配信の課金者が増え、映像業界が潤います。電子マンガはついに紙の低減をカバーし、20年前を超えるマンガ市場に成長します。家庭用ゲームもオンラインのソフト売上が昨対比で2倍になります。7〜8年前から大手が取り組むようになり、ずっと苦しい中でデジタルシフトした成果がこの2年に急激に跳ね返り、市場はすでに底を打っています。
そうした動きが1番遅いともいえる新聞産業は、いまだ下落市場ではありますが、すでにその減速が緩んできております(というか定期購入はもう減らず、広告はこれ以上ないところまで落ちて底を打った状況)。このままいけばあと数年で新聞もデジタルが下支えをし、回復傾向になることは大方予想がつきます。
すでに米国では明確な成功例が出始めています。20年以上前からデジタルシフトを手掛けてきたワシントンポストの事例もありますし、図2のようにNewYorkTimesはすでに「デジタルサブスク」「デジタル広告」が全体売上の半分以上のシェアになってきています。2021年の売上は昨対比30%増で、会社としてもすでに2012年度を超えるレベルまで育ちました。
すでに市場の「先」がみえはじめたなかで買収攻勢は過熱化しています。2018年にMeredithがTimeを28億ドルで買収したのを皮切りに、2019年にVICE MediaがRefinery29を4億ドルで買収、2020年BuzzFeedがHuffpostを呑み込み、各社がデジタルメディアの先にユーザー基盤をもつ会社を次々に包含しようとしています。
こうした中で、日本の新聞・ニュース業界はどうなっていくのでしょうか?いまだ危機が緩く、雇用も守られる日本の新聞業界。ヤフーニュースで記事が安く買いたたかれたり、Smartnewsやグノシー、Newspicksといった新興メディアも勢いを伸ばしているものの、いまだ1桁小さい売り上げ規模で「絶対的な脅威」にはなりえていない状況。10年前、いや20年前から叫ばれていた「新聞社崩壊」はいまだに起こっていません。こうした中で日本の新聞社は今後どのような方策を練るべきなのか。
メディアの本質は「伝えること」ですが、伝えて影響されることで人の行動は変わります。その先に、本を買ってさらに情報の精度をあげたり、関連する商品を購入して身の回りにおいたり、何かに入会して体を鍛えたり、転職したり。
新聞が「伝えること」に特化した分、その後人々の行動がどう変わるかについてあまりに無関心すぎました。メディア産業の本質は人の視線を集めることではなく、人の視線の先にある「関心の変容」です。変容した関心の先でビジネスを行うのはいまやGAFAの専売特許となり、その出先で注目を集めるためだけに「コンテンツとしてのニュース」が使われている状態です。
今後新聞メディアはどのように生存を図るべきか。あくまで視線集めと教条的な100年前のポリシーにしがみつく限りは、この業界はオペラや歌舞伎のようにブランドとレガシーに支えられて、そして本来的なジャーナリズムの役割は徐々に育つ若者ユーザーとデジタルメディアに徐々に覇権が握られるのではないか、と感じます。「ユーザーの視線と関心の先を掴めるか」、そこにニュース産業の次の可能性がある気がしてなりません。