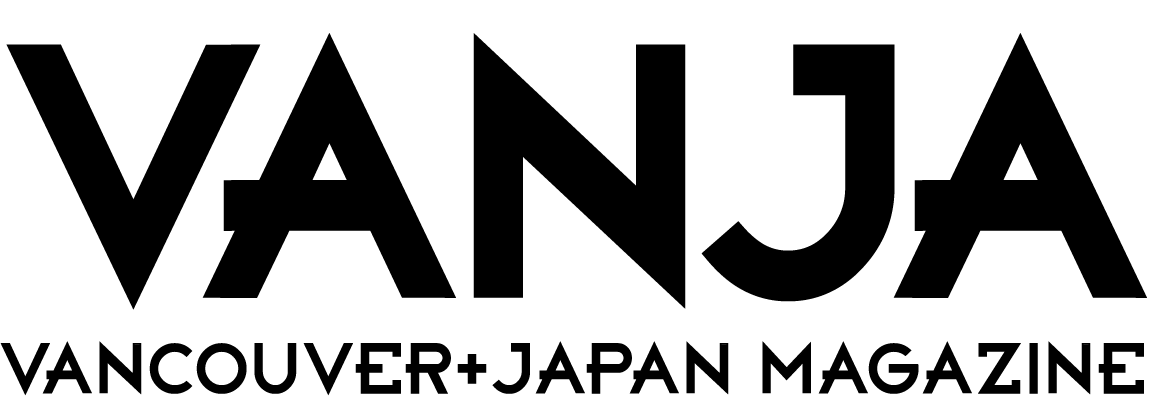ドメスティックランキングは米>日>中
これまで映画市場における世界3大国家、米国(1兆円)・中国(1兆円)・日本(0.2兆円)の3つの市場の違いについて分析してきました(第83回参照)。今回はそれが「どこの国で作られた作品か」という、いわば映画としての自給自足率を図ろうという試みです。図1において各国市場の映画消費がどのくらいアメリカ(ハリウッド)映画と、国産映画に依存しているかを見ていくと、意外なことに気づきます。国産映画が国内市場5割以上を占める国は、実は世界中でも片手ほどしかありません。米国とインドが国産9割(規制があるイランは10割)、その後に続くのが日本の6割、そして中国と韓国です。

ほとんどの国は「8〜9割はハリウッド映画」「国産映画は1割以下」という水準におさまります。図1は映画市場規模も大きく、国産映画制作も盛んな上位42か国のデータですので、世界200数か国全体でいえばさらに左上に多くの国が偏っている結果になることでしょう。映画で有名な欧州諸国もまた、ハリウッド比率がとても高い。100年前は映画の都であったフランス、そして言語や文化で米英とは差別化された経済圏をもつドイツやスペイン・イタリアといった国ですら、国産映画の割合は2割前後といったところ。1千億円規模の映画興行市場を持ちながらも、結局それらの先進国ですら市場の6割以上はハリウッド映画によって生み出されています。
ここまで考えると、(コロナ前は)約4兆円の市場があった世界映画市場ですがら、その内実は1兆円の米国市場と、追加で約2兆円は「ほぼハリウッド映画だけを消費するその他の国の興行市場」であり、国産映画が消費されるような余剰となるものは1兆円分もないのではないか、という気がしてきます。つまり、世界各国で映画は作られていると言いながら、「国産映画がマジョリティをとっている地産地消のアジア巨大市場(印・中・日・韓)」のみがその帝国主義的なカバレッジから逃れられており、それ以外の「西欧で国産2〜4割、ハリウッド影響7割未満で防いでいる西欧先進国(英・仏・独・露・西・伊)」と「その他国家:映画市場≒ハリウッド市場(その他100数十か国)」の3つにしか分けられないということになります。世界の映像市場における米国の影響力の大きさに、ただただ震撼するばかり。
しかしここでもう一つの特異点に気づきます。実は世界で最もドメスティックなのは米国です。国産が9割近い米国に比べ、むしろ中・韓・日のほうが国産映画による市場が6割に「抑えられ」、それ以外はハリウッドだけでなく様々な諸外国の映画を消費しているからです。消費者としての質でみたときに、米国人よりも、こうした東アジアの国のほうが生産者・供給者・消費者としてバランスのとれたポートフォリオにある、ということもできます。
もう一つ、個人的に面白いのはマレーシアの位置づけです。国産1割ですが、ハリウッドも2割、そこにインド映画と中国映画や韓国映画といった多様な映画消費がなされており、まさに世界の中立的な交流点がこのマレーシアに存在しているように思えます。以前は西欧とアジアの緩衝地帯である、トルコ・イスタンブールがまさにこの役割を担ってきました。21世紀では、台頭するアジアに対する欧米諸国という構図が如実になり、東アジア・南アジアの交流地点でもあり、仏教・キリスト教・イスラム教の交わるところでもある「マレーシア」は実に面白い市場になる可能性を孕んでいます。
映画とナショナリズム
映画はナショナリズムとともに発展してきました。19世紀末にこの映像メディアの発展は「国民教育」として重宝され、特に当時の日本にとっては「映画を導入すること」は欧米型のナショナリズムと植民地主義を学ぶこととほぼ同義でした。1894年にリュミエール兄弟が映画をはじめて撮影した日から、日本においても最初の映画撮影が行われたのは実は3年後である1897年でした。かなり早いです。いかに日本が欧米のような帝国主義を築き上げようとしていたかが垣間見えます。それに対してほかのアジアで最初に映画が撮影されたのは北京(1905年)、朝鮮(1919年)、台湾(1925年)と、それぞれ日本からかなり遅れており、日露戦争の前にもすでに日本が欧米とかなり近い経済的な距離にいたことも伺えます。
また映画の発展形態もその国の独自の文化を根付かせます。第一次世界大戦の戦火を逃れ、多くのクリエイティブな人材が「何もない安全な荒野」を求め、アメリカにわたり、そして西海岸にたどり着きました。ラスベガスやハリウッドといった地域はこの1920年代に世界の西端の何もない空間として映画づくりに重宝されていきました。だが、日本にはすでにどっしりと根付いた芸能の歴史があります。映画館が「劇場」と呼ばれていることからもわかるように、それまでの演劇と音楽の影響を多分に受けた日本映画は、いかに歌舞伎などの舞台から人材を引っ張ってくるかに苦慮した歴史があります。歌舞伎で「女形」が禁じられていたために、日本映画も初期は「女優」を出すことすらためらわれた時代がありました。女優の供給源は主に「新劇」と言われる新興の演劇集団でした。
しかし「国産」は長らく、チープな粗悪品という状況が続きます。フランスと米国を中心とした「西洋映画」は上流階級が見るもの、「国産映画」は下流階級が見るもの、という明確な序列がありました。娯楽の米国映画、芸術の欧州映画、歴史教育のアジア映画というのが長らくの映画消費の位置づけでした。80年代はアニメが子供の見るものだと倦厭されてきていましたが、90年代と00年代のジブリの活躍などを通して大人がお金を出してみるものに変わっていったのと同じく、名作と大作と消費者の習慣化によって徐々に国産と輸入モノに差がなくなってきたのは21世紀に入ってからのようやくの傾向といっても過言ではありません。
図1でみるように「国産映画」はとても希少なことです。それが芸術として根付き、一つの創作活動として認められ、大衆があえてハリウッド映画ではなく、国産映画を見る文化が生まれるには長い長い時間を要しました。こうした表現の自由を、単純なコンテンツのリッチさのみでハリウッド映画のみに奪われ、「国産映画産業がない」ほとんどの国に対して、確かに個人的には危機感を抱かずにはいられません。
「言語」と「政策」はハリウッドの絶大なる影響力を和らげる緩衝材として機能しています。文化浸透度というのは高すぎると高すぎるがゆえに阻害要因が起こります。すなわち「通じるからこそ、単純に良質なものに流れすぎる」。これは消費者視点で言うとメリットしかありませんが、産業育成という観点にとっては絶大なデメリットになります。いわばBリーグを育てようと必死になっているときに、国境も言葉も人種の阻害要因もないためにMBAから選手がバンバン流れてくるような状態です。日本はあっという間に「米国製品の有望な輸出市場」となることでしょう。それはいわばカナダやオーストラリアと同じく、米国市場と同じラインナップが並ぶだけの市場になってしまいます。
40年ぶりの映画産業大再編時代

そもそもハリウッドも含めて映画自体が「重要産業」となったのは、実はそれほど古い話ではありません。1980年代に入ってからの話です。図2をみると、世界映画興行市場規模が数千億円から兆円規模へと羽化するのと同時に、平均制作コストもグンと上がっていきます。これはVHSなどのホームエンターテイメントのパッケージ販売や地上波・ケーブルテレビといった映像メディアが映画コンテンツを購買しはじめた時期と重なります。90年代から00年代はまさに「映画の栄華時代」ともいうべき状況で、1本〝平均〟でも30~40億円の制作コストがかけられ、そしてほぼ同じ額の興行収入を稼ぎます(この50%がメーカーに入るのでこのままだと半分赤字ですが、それをパッケージや番組販売などの二次流通でカバーしていきます)。
2020年代はまさにこの1980年代からの「映画の栄華時代」の再来ともいえる、「映画の再定義の時代」に入ります。すなわちネットフリックスやアマゾンといったIT大手がコンテンツ制作に積極化し、「映像」自体の出し口が「映画館・スマートテレビ・PC・スマホ」と多様化します。映画館の2時間、テレビの1時間、スマホの30分といった具合に、これまでのように「尺と制作費で区切られた動画共存の時代」はもはや終わりを告げ始めています。〝映画〟ではなく、〝映像作品〟として、映画館は1つの選択肢にしかならなくなりました。
2021年はディズニーの『ブラック・ウィドウ』が東宝・東映・松竹の3大シネコンから締め出しを食らい、ほとんど日本で上映されていないという「事件」が起きています。これはディズニーが映画封切りと並行してディズニープラスでも動画配信を開始するという決定に対するボイコット運動であり、映画館と動画配信の戦争の幕開けでもあります。これを偏狭な日本興行からの圧力と易々と片付けるべき話ではありません。なにせ気を抜くと、映画業界のみならずテレビ視聴からネット視聴までハリウッド映画に視聴者を奪われることも起こりえるからです。この切り替わりのタイミングで「国産」を単なる消費というより、産業のプロセスとして組み込めるかどうか、まさにここから10年の試金石となるタイミングが今と言えるでしょう。