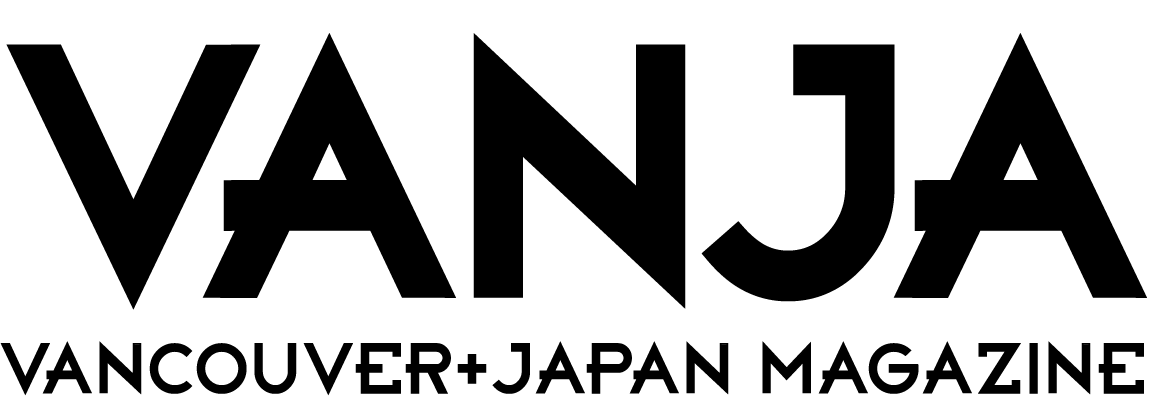1980年代衰退期にあった映画業界
日本の映画史上「スタジオジブリ」の偉業をおいて右に出るものはそうないでしょう。出す作品はすべて2桁億円以上のヒット、『千と千尋の神隠し』は興行収入308億と、いまだ日本の映画史上もっとも売れたタイトルとして輝いています(ちなみに2位『タイタニック』262億、3位『アナと雪の女王』255億、4位『君の名は。』250億、5位『ハリー・ポッターと賢者の石』203億。こうみると2~4位を大きく引き離す、断トツトップですね)。今回は「スタジオジブリ現象とは何だったのか」についてみていきたいと思います。
そもそも映画業界において「アニメ」というジャンルが台頭しはじめるのは1980年代に入ってからの話。正直1980年代の日本映画業界は、時代遅れコンテンツとして他に大きく引き離される時期にありました。新聞も出版もテレビもゲームもアニメも玩具も、あらゆるエンタメコンテンツが飛躍した1980年代という時代、日本映画市場は1659億(1980年)→1719億(1990年)とほとんど規模を変えていません。しかも邦画でいうと912億→712億とむしろサイズ減になっていく有様。『E.T.』『インディ・ジョーンズ』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』など、むしろ洋画のヒット作でなんとかサイズを維持していたジリ貧の業界でもありました。
そうした時代において、1978年『さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち』は邦画配給収入2位の21億円、はじめて「子供がみるアニメ」が映画業界に頭角をあらわすきっかけを創り出したタイトルです。続く1979年には『銀河鉄道999』が16・5億円と邦画で第1位となり、その後1980年代に入ると『ドラえもん』シリーズが10億越えを連発し、春のアニメ映画が定番化しはじめます。VHSの登場で劇場以外の収入も期待されはじめ、アニメというサブカルチャーに陽の光があたりはじめるタイミングがジブリの始まりです。
出資社タイアップによるプロモ力強化
1985年にひっそりと吉祥寺で創業されたスタジオジブリは、1978年『アニメージュ』などを発刊していた徳間書店がスポンサーとなってアニメ制作を行う会社でした。現在ではCCCグループとなっている徳間書店は、映画会社の1社大映の買収もしており、当時KADOKAWAとともに業界を牽引する出版・映画業界の雄の1社でもありました(ちなみに創業者の徳間康快は豪放磊落を絵に書いたような人で、その起業家としてのストーリーはめちゃくちゃ面白いです)。
宮崎駿監督は東映のアニメ部門にも所属していた人でしたが、それを拾い上げて作品づくりを支援したのが徳間康快でした。親交の深かった東映元社長の岡田茂は「ウチ(東映)もそうだが、確実な収益を期待したら、アニメのターゲットは子供向けになってしまう。万が一、映画でコケても、キャラクター・グッズの売上げで補填することができますから。ところが徳間は、最初から大人の鑑賞に耐えられる作品を創ろうとした。これが、宮崎駿の才能の開花に繋がったのだからね」と語っているように、このスポンサーの存在なくしてジブリはありません。
1984年『風の谷のナウシカ』や1986年『天空の城ラピュタ』、1988年『となりのトトロ』はまだ数多くあるヒットアニメの1つでしかありませんでしたが、その頭角が現れるのが1989年『魔女の宅急便』の興収42・8億で『ドラえもん のび太の日本誕生』を抑えて邦画1位に輝きます。この作品は当時のアニメにはめずらしく、テレビ局の日本テレビだけでなくヤマト運輸という出資社を入れて、タイアップを行った作品でした。この時代からジブリアニメはブランドのあるいわゆる「ナショナルクライアント」を出資社に迎え入れ、共同でプロモーションを行う手法をとりはじめます。映画プロデューサーである鈴木敏夫の辣腕があらわれはじめる時期でもあります。
1991年『おもひでぽろぽろ』で広告代理店の博報堂を迎え、1992年『紅の豚』では日本航空。この作品は広告費9億円でしたが、日本航空自身がプロモーション協力を行うことで28億円の広告効果があったと鈴木氏も回顧しています。それまでであれば1人の観客に映画館にきてもらうのに1000円くらいかかる広告予算を投じていたものが、実費としては300円を切るところまで持っていきます。専門としての声優を使うのではなく、知名度の高い俳優や有名人を起用するのもまたジブリならではのタイアップの一環の一つでもあります。
1994年『平成狸合戦ぽんぽこ』からはスタジオジブリ自身が出資社に名を連ね、自社もライセンス事業に乗り出します(アニメでは、実際につくる「制作」とお金を出資して実質その版権の所有者になる「製作」が区別されます。それまではジブリもただお金をもらって作る会社であり、『紅の豚』以前のキャラクターの所有権は持っていません)。
とまらぬビクトリーロード、制作委員会は定番化
これらの興行収入50億円前後でも十分なヒットメーカーではありましたが、文字通り「桁が違う」歴史的偉業へとのステップを踏んだのが1997年『もののけ姫』です。なんと興行収入193億。この時点では日本映画史上もっとも売れた映画となりました。この作品から広告代理店枠で入ったのは電通で、そのプロモーション力も大きく貢献しての前人未踏の作品となりました。
図1が創業以来の作品とその製作者=出資社を表した図です。『もののけ姫』以降は時代の潮目が変わります。1999年『となりの山田君』から海外配給で協力体制にあったディズニーが入り、次の『千と千尋の神隠し』では東北新社や三菱商事が入ります。冒頭で述べたように、この作品はいまだ誰にも破られていない300億円超えの記録を打ち立てています。

その後の快進撃はもはや語る必要がないものかと思いますが、2006年『ゲド戦記』からは交互に出資となっていた電通と博報堂が同時に出資するようになります(『風立ちぬ』からはADKグループのD-rightsまで入り、日本の大手代理店3社ともが出資するというなかなか見ない座組にもなっていきます)。この座組が基本的には2008年『崖の上のポニョ』以降も、2010年『借りぐらしのアリエッティ』、2013年『風立ちぬ』、2014年『思い出のマーニー』へと続いていきます。
縮小すれど解体せず。スタジオジブリよ、永続なれ
ではなぜ快進撃を続けるスタジオジブリは縮小されなければならなかったのでしょうか。2014年8月にスタジオジブリは大量リストラを行います。その制作陣のほとんどが退社し、いまは別のアニメ制作会社に移りました。限られた数字ではありますが、図2で総資産と純利益を比べてみると、『鉄腕アトム』から続く老舗東京ムービーを吸収したセガグループTMS(トムス)とほぼ近いサイズです。2008年や13年などヒット作に呼応して純利益が20〜30億円規模にはねているのもわかります。

数百億円の大ヒットを出したとしてもそれがスタジオジブリの収益に反映されるわけではありません。前述の出資社で配分されるにあたって、300億円の興行収入も半分以上は劇場と配給会社の配分ですので、制作委員会には約35〜45%で100億円超が入ってきます。それは出資比率に応じた按分もされるので、「スタジオジブリ」単体としては30億円の純利益となっても納得できる数字です。逆にTMSやIGポートの純利益にそれほど変動がないのは、タイトルへの出資額の頻度・割合もありますし、ジブリの爆発的ヒットがイレギュラーすぎるという事情も手伝っています。
こうしてみるとジブリも2014年に業績がものすごく悪かったわけではありません。ただ、宮崎駿監督が作品をつくらないと宣言したところから、300人規模の大きいスタジオを維持するわけにはいかなくなったのでしょう。アニメ制作会社は大量に人を抱えています。人数が多いほうが制作体制が潤沢なわけですが、それは繁忙期も休閑期もひとしく人件費を抱え込むことになります。まして人が多いから案件をとってこないととどんどん思考が逆転して「作るためのヒトではなく、ヒトのために作る」といったことが起こります。これはテレビ番組制作でもゲーム開発でも同じですね。
スタジオジブリそのものは現在も続いていますし、版権収入も今後過去の作品の海外展開にあわせて増減していくことでしょう。上記のようにスーパープロデューサーのもとで数百人が歴史的な作品をつくるという体制自体が恒久的に続くものではなく、1980年代半ばから30年にわたって日本の映画業界の先頭をはしってきたスタジオが作品を量産しなくなるという事実は、残念この上ないです。ただジブリが築いた、ユーザーの映画館に行く消費習慣そのものは『名探偵コナン』や『君の名は。』『天気の子』といった次の世代の大ヒット作に向けて連綿と続いており、この業界を大きく飛躍させた立役者の偉業はいまだ我々の中に残っているのです。